「津城跡」もそうだったのですが、伊勢側のお城造りでは、
「多聞跡」というのがあって、その下に堀がある(あった)。
二つのお城を見ただけなので一括りにするわけにはいきませんが、
その「多聞跡」は歩くことができます、怖いもの見たさで歩きますが、
やっぱり「水」はなくても足は竦みます でも歩く…
でも歩く…
「石垣の高さ」では伊賀上野城の方が圧倒的です!
ちなみに、伊賀は「防御型」のお城で、「大阪方面の見張りのため」の城だったそうなので…


伊賀上野「高石垣」と「伊賀上野跡縄張り図」(※「上野城と城下町」より)
しかしここ「松坂城跡城内」の石垣も変化に富んでいて複雑だし見ごたえがあります。
そこんところを紹介できればいいなぁ…と。
では、もう一度「表門跡」からスタート、今回は「本丸」に潜入です。
その1:「表門跡」、「助左衛門御門」から「本丸下段」へ
 「松坂城跡碑」
「松坂城跡碑」
市役所の通りから入って正面に、
主碑は裏千家の千宗室の揮毫(キゴウ)、松阪開府390年記念に昭和53年(1978)に建立。

ここから入城しますが、この写真の右側には

 「井戸跡」
「井戸跡」
この場所からすでに松阪市内東方面一望です。
 「表門跡」
「表門跡」
ここを「左」へ

 「助左衛門御門」
「助左衛門御門」
ここから「本丸の下段」に入ります。
真っ直ぐ進めない「門跡」などは「桝形構造」といわれる出入口が続きます
ここで、松坂城跡案内図②を、

「多聞跡」「櫓跡」がいっぱいです、おおよそ水色部分が歩いたところ。
城内その①:「月見櫓跡」~「中御門跡」
先ず、本丸下段の「多聞跡」から松阪市内を見てみる…
 南方面
南方面

 東方面、遠くに「海」…
東方面、遠くに「海」…
「月見櫓跡」



※本丸下段東角にあった2層の櫓。台所棟などがあったが17世紀中ごろに大破、とのこと。
「櫓跡」から「表門」を見下ろしてます、怖いです
一旦、下に降りて周りの「石垣」を見ながら、


「中御門跡」へ、これでもか!と曲がります。



蒲生時代の「野面積み」石垣です、まだ続く石段



やっと「本丸(上段)」に来ました。
真ん中奥に見えるもの「本丸跡」、実は「井戸跡」です。
 ふつう、覗きませんよね
ふつう、覗きませんよね
でも、井戸は大事だと思います、どこのお城でも「井戸」は「命の源」かと。
次に、「きたい丸 多聞跡」へ上がります
 ここからは南側になります
ここからは南側になります
城内その2:「きたい丸」~「松坂城梅林」~「角櫓跡」


手前の建物「本居宣長旧宅(鈴屋)」、城内南側の「石垣」
「きたい丸」とは、
※本丸の西にあり、曲輪の名称は、松坂城を完成させた3人目の城主、古田重勝の子どもの幼名「稀代丸」にちなみます。
東西南北の各角に櫓が配置されています、とのこと。
ここは「松坂城梅林」となっており、春が待ち遠しいところです。



では、ちょっと楽しみな北側の「角櫓跡」へ
しかし、多聞跡を歩いたり、下に降りたりとなかなかの運動量になりますが、
振り返ると「ここを歩いたの?」という狭さです
この経験は貴重だと思いました。

さぁ、再び「多聞跡」を歩きつつ景色を堪能しましょう~
「角櫓跡」から



「石垣注意!」です…
西から北にかけて~~



知らない名前の山ばかりですが、とても分かり易く、
形も同じように書いてもらってあるので有難いです
北側にはグラウンド、遠くに「鈴鹿山脈」の雪



もう、石垣を覗きつつ、ゾクゾクゾワゾワしながら撮ってました(笑)。
長くなりました、ちょっと休憩を入れて…
ではまた
「多聞跡」というのがあって、その下に堀がある(あった)。
二つのお城を見ただけなので一括りにするわけにはいきませんが、
その「多聞跡」は歩くことができます、怖いもの見たさで歩きますが、
やっぱり「水」はなくても足は竦みます
 でも歩く…
でも歩く…「石垣の高さ」では伊賀上野城の方が圧倒的です!
ちなみに、伊賀は「防御型」のお城で、「大阪方面の見張りのため」の城だったそうなので…


伊賀上野「高石垣」と「伊賀上野跡縄張り図」(※「上野城と城下町」より)
しかしここ「松坂城跡城内」の石垣も変化に富んでいて複雑だし見ごたえがあります。
そこんところを紹介できればいいなぁ…と。
では、もう一度「表門跡」からスタート、今回は「本丸」に潜入です。
その1:「表門跡」、「助左衛門御門」から「本丸下段」へ
 「松坂城跡碑」
「松坂城跡碑」市役所の通りから入って正面に、
主碑は裏千家の千宗室の揮毫(キゴウ)、松阪開府390年記念に昭和53年(1978)に建立。

ここから入城しますが、この写真の右側には

 「井戸跡」
「井戸跡」この場所からすでに松阪市内東方面一望です。
 「表門跡」
「表門跡」ここを「左」へ

 「助左衛門御門」
「助左衛門御門」ここから「本丸の下段」に入ります。
真っ直ぐ進めない「門跡」などは「桝形構造」といわれる出入口が続きます

ここで、松坂城跡案内図②を、

「多聞跡」「櫓跡」がいっぱいです、おおよそ水色部分が歩いたところ。
城内その①:「月見櫓跡」~「中御門跡」
先ず、本丸下段の「多聞跡」から松阪市内を見てみる…
 南方面
南方面
 東方面、遠くに「海」…
東方面、遠くに「海」…「月見櫓跡」



※本丸下段東角にあった2層の櫓。台所棟などがあったが17世紀中ごろに大破、とのこと。
「櫓跡」から「表門」を見下ろしてます、怖いです

一旦、下に降りて周りの「石垣」を見ながら、


「中御門跡」へ、これでもか!と曲がります。



蒲生時代の「野面積み」石垣です、まだ続く石段



やっと「本丸(上段)」に来ました。
真ん中奥に見えるもの「本丸跡」、実は「井戸跡」です。
 ふつう、覗きませんよね
ふつう、覗きませんよねでも、井戸は大事だと思います、どこのお城でも「井戸」は「命の源」かと。
次に、「きたい丸 多聞跡」へ上がります
 ここからは南側になります
ここからは南側になります城内その2:「きたい丸」~「松坂城梅林」~「角櫓跡」


手前の建物「本居宣長旧宅(鈴屋)」、城内南側の「石垣」
「きたい丸」とは、
※本丸の西にあり、曲輪の名称は、松坂城を完成させた3人目の城主、古田重勝の子どもの幼名「稀代丸」にちなみます。
東西南北の各角に櫓が配置されています、とのこと。
ここは「松坂城梅林」となっており、春が待ち遠しいところです。



では、ちょっと楽しみな北側の「角櫓跡」へ
しかし、多聞跡を歩いたり、下に降りたりとなかなかの運動量になりますが、
振り返ると「ここを歩いたの?」という狭さです

この経験は貴重だと思いました。

さぁ、再び「多聞跡」を歩きつつ景色を堪能しましょう~
「角櫓跡」から



「石垣注意!」です…
西から北にかけて~~



知らない名前の山ばかりですが、とても分かり易く、
形も同じように書いてもらってあるので有難いです

北側にはグラウンド、遠くに「鈴鹿山脈」の雪



もう、石垣を覗きつつ、ゾクゾクゾワゾワしながら撮ってました(笑)。
長くなりました、ちょっと休憩を入れて…
ではまた




























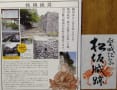
















































































































 して、
して、


















