前回(→こちら)の続き。
1992年の第50期名人戦は中原誠名人を相手に、挑戦者の高橋道雄九段が2連勝でスタート(第1回は→こちらから)。
この結果を見て、われわれ観戦者は少しばかり、ザワザワすることになる。
「あれ? これちょっとヤバくね?」
中原が2連敗していることではない。
高橋道雄の強さは、将棋ファンなら先刻ご承知のところで、タイトル戦で挑戦者が2連勝するのもよくあること。
ふつうなら、むしろこれでシリーズが盛り上がると、呑気にかまえているところなのだ。
では、なぜ平静でいられないのか。
「中原の矢倉」が、ここまで通じていないからだ。
これは第1話の名人戦における「神話」(→こちら)同様、またも説明が必要だが、昭和の将棋界では「矢倉」というのが将棋の王道ととらえられていた。
米長邦雄永世棋聖の有名なセリフ、
「矢倉は将棋の純文学」
のように、矢倉を極め、それで勝ってこそ真の王者である、という思想というか、「信仰」のようなものが支配的だったのだ。
今の感覚では「へー、そうなんやー」くらいのものだが、このフレーズこそがまさに、このシリーズを語るキモ。
いわば昭和の矢倉戦法は、野球における「エース」という存在。
マンガ『ダイヤのA』でいえば(今、久しぶりに読み返してハマっているのです)、青道高校が初戦に降谷暁、2戦目に沢村栄純を立て必勝を期したところ、その両方とも落としてしまったようなものなのだ。
ただ負けただけでなく、「チームの柱」が試合をつくれなかったことは、今後の展開が見えなくなる意味でもショックがある。
こうなると興味津々なのは、中原先手で戦われる第3局の戦型。
ふつうに考えれば、選ぶのは矢倉である。
敗れたとはいえ、やはり中原にとっては最大の得意戦法であるし、なにより先も言った通り、
「矢倉で勝ってこそ名人」
という縛りもある。エースが打たれた借りは、エース自らが返すしかない。
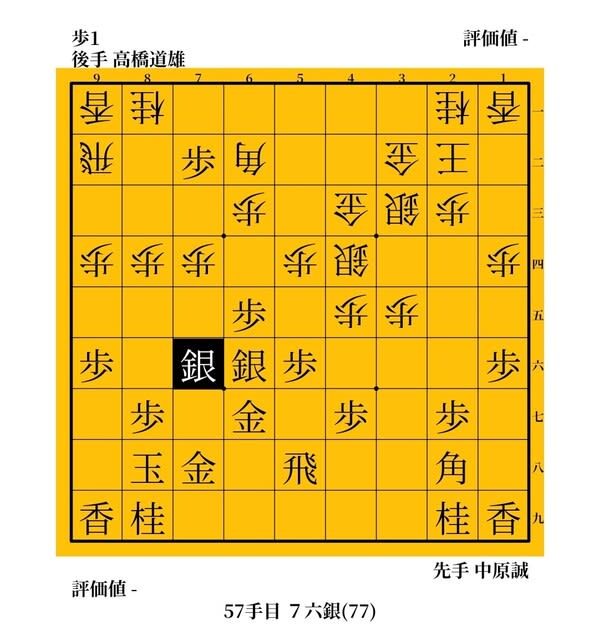
七番勝負、第1局の再掲。
「こういう将棋」で勝たないと、第一人者たる資格はないというわけ。
また、中原はおだやかに見えて、相当に意地っ張りな面もあり、ライバル米長邦雄との勝負では、ムキになって矢倉を連投させたこともあった。
七番勝負で勝つには4勝しないといけないのだから、どっちにしろ、いつかは「高橋の矢倉」をブレークしないといけないわけで、それならここで、となるのは自然なところではある。
ただ今回、そんな簡単な話だろうかというのは、なんとなく感じられるところだった。
まず、高橋道雄は強い。
将棋の実力は周知としても、この大舞台で持てる力を存分に発揮できる精神が、いかにも頼もしい。
矢倉の強靭さも評価できる。
名人中原相手に2連勝、そこに名人挑戦プレーオフの南芳一九段戦、谷川浩司四冠戦も含めれば、高橋の矢倉はトップ棋士に連勝中で、特に先手番のそれは無類の強さ。
それは「意地」「プライド」といったもので、突破できるほど甘くないのではないか?
万一負けでもしたら、3連敗のカド番で、今度は後手番から高橋の矢倉を受け止めなければならない。
それはもう、実質終わりのようなものである。
もうひとつ、選択をややこしくしているのは、先手番だと中原には
「中原流相掛かり」
という、もうひとつの得意戦法があったこと。
谷川浩司から、名人位を奪い返す原動力となったこの戦型は、当時まだ(今でも?)定跡が整備されておらず、力戦のようになりやすい。
初見での対応力や戦法との相性、経験値の差がハッキリと生きるわけで、「スペシャリスト」中原に分があるのは間違いないところなのだ。
ふたたび『ダイヤのA』でいえば、青道には降谷、沢村に続いて、3年生でリリーフ経験も豊富な、サイドスローの川上憲史投手がいるようなもの。

1985年の名人戦第6局。
▲45桂と単騎ではねるのが、「中原流相掛かり」の見せ場。
こんなんで攻めがつながるかと、首をひねりそうになるが、△88角成、▲同銀、△42角の受けに、▲14歩、△同歩、▲24歩、△同歩、▲77桂と巧みに手をつないでいく。
△54銀と逃げると、▲53桂成、△同角、▲24飛のきれいな十字飛車が決まる。
渡辺明名人も学んだ盤面を広く見た構想で、谷川から名人奪還に成功する。
勝負にこだわるなら、流れを変える意味でも、ここは相掛かりが有力だが、それではどうしても「逃げた」というイメージが付きまとってしまうリスクもある。
「降谷、沢村で試合を作ってから、リリーフエースの川上にスイッチ」
なら必勝パターンだが、
「エース2枚が通じないから、リリーフの3年を緊急登板」
では、作戦的にも気持ち的にも、完全に後手に回ってしまっている。文字通り、
「ピッチャーびびってる、ヘイヘイヘイ!」
まさに「名人の沽券」にかかわってくるのだ。
野次馬の私ですら、「どうすんねやろ?」と感じたのだから、当事者である中原名人は苦悶に沈んだことだろう。
矢倉だと、勝てば視界が一気に開けるが、負ければほぼゲームセット。
相掛かりだとチャンスは多いが、腰が引けていることを露呈してしまうことになる。
ここへきて、王者の条件である、
「矢倉で勝ってこそ名人」
という言葉が、中原にとっては大きな圧、いやもっといえば「呪い」のように重くのしかかってくることになる。
大注目の第3局。
初手は、果たして……。
(続く→こちら)

























