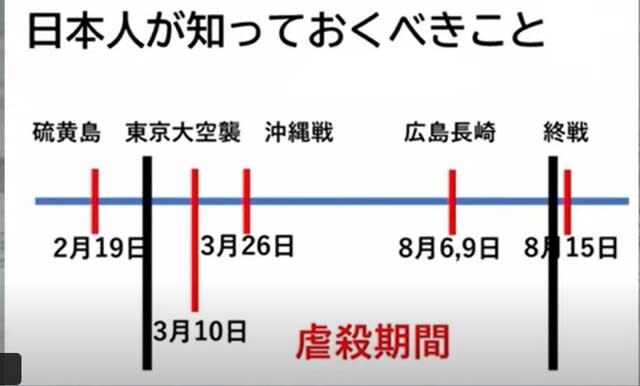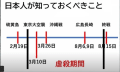朝日新聞社刊行の初版『鉄の暴風』と沖縄タイムス社刊行の第2版の、両者の「まえがき」を比較すると極めて興味深いことが分る。まずは沖縄タイムス刊の第2版の「再刊行について」の全文を引用しよう。
再刊行について
二十年が、あっというまに経過した。正しくは二十五年だが、この戦記(否沖縄人にとって受難の記録)を上梓してもはや二十年である。
今年は安保七〇年である。そして沖縄返還を具体化するために日米共同声明の公表後幾月がたった。
ところが、わたくしたちは、佐藤首相のいう「沖縄の戦後」が終わったとは少しも考えたくない。そして、一方では、権力の手で再び日本再軍備強化の気配さえおぼえる、きょうこの頃である。
沖縄人が「反戦・平和」を叫ぶ真の理由は、ここにある。当時、沖縄にあって戦乱のルツボに叩きこまれた人たち約四〇万の非戦闘員たちのうち、辛うじて生き残った人たちは、百万といわれる沖縄の現人口の何割かを占めるほどの寥々たるありさまである。戦後の若い世代は勿論、二十年の歳月は、沖縄人が陥ったあの狂乱怒涛時代を知らぬ人たちとの間には一種の断絶さえつくろうとしている。七十二年復帰を控えて、あえてこの記録を再上梓するゆえんである。
旧「鉄の暴風」は内容を一切元のまま、むしろ復刻の形で再び世に問うたわけだが多少、一部の章句を訂正した。(牧港篤三)
引用:鉄の暴風 – 沖縄戦記、1970年6月20日第2版沖縄タイムス発行
上記の引用から第2版の発行目的が明確だが、注目すべきは「むしろ復刻の形で再び世に問うわけだが多少、一部の章句を訂正した。」と書かれた部分だ。それは初版と第2版を比較すると明白なので、その訂正した部分を引用し、初版と第2版を比較すると初版と第2版との目的の違いよく分かる。
■初版の「まえがき」から削除された文言
以下は『鉄の暴風』初版のまえがき。
まえがき
こゝに、米軍上陸から、日本軍守備隊が壊滅し去るまでの、住民側から見た、沖縄戦の全般的な様相を、描いてみた。生存者の体験を通じて、可及的に正確な資料を蒐集し、執筆し、書きおろし戦争記録として、読者諸賢におおくりするものである。
軍の作戦上の動きを捉えるのがこの記録の目的ではない、飽くまで、住民の動きに重点をおき、沖縄住民が、この戦争において、いかに苦しんだか、また、戦争がもたらしたものは、何であつたかを、有りのまゝに、うつたえたいのである。このことは、いかなる戦場にもなかつたことであるし、いかなる戦記にも書かれなかつたことである。
最高度の破壊的科学兵器による立体戦、しかも、前線も銃後もなかつた沖縄戦は、残酷な近代戦が、最も圧縮されたかたちにおいて行われた、唯一の実例である。陸、海、空の立体陣を布いた攻撃軍の前に、日本軍守備隊が、地下戦術で終始した、この戦闘では、一方は、質量ともに圧倒的な化学兵器の破壊力に自信をもち、他方は、自然洞窟豪の堅牢さに信頼をかけて、物量の限界を見とゞけようと、空しい期待に一縷の望みを託するだけだつた。
それに、逃げ場のない幾十万の住民が、右往左往して、いたずらに砲爆弾の犠牲となり、食に飢え、人間悲劇の極致を展開した。沖縄には、自然の洞窟が、いたる処にあつた。また、直ちに掩蔽壕になりうる堅固な墓があつた。住民は、洞窟から洞窟へ、墓から墓へ、わずかな荷物を抱えて、死の彷徨をつゞけた。あるいは、一族が、先祖の墓の中で死を待ち、あるいは、一つの洞窟の中に、何百の老幼男女が、押しこまれて、陰惨な生活をつゞけた。砲爆撃のあい間をみては、食を、水を、漁りに、穴を匍い出して、負傷したり、死んだりするものが続出した。
沖縄戦が終了したとき、ことに激戦地たる、沖縄島の、中南部は一木一草もとゞめぬほど、赤ちやけた地肌を表わしていた。そして、辛うじて死をまぬがれた人々は、極度の緊張と、営養失調と、不自然な壕生活のために、生きた人間の姿とは、思えないほどだつた。それは、人間の体力を維持するには、余りに無理な、ながい疲労と、不潔と、暗黒の生活だつた。死ぬことを教えられて、しかもたえず、死の恐怖に戦慄しつゝ、生を求めつづけようとした人間の、最悪のあがきであつた。こゝに、どたん場までおい詰められた人間の、いろ〱な姿がある。こゝに真実の物語がある。
もちろん、われ〱は、日本軍国主義の侵略戦の犠牲となつたが、われ〱がいわんとするものは、もつと、深いところにある。
『民族を超えた、人間としての理解と友情。』われ〱は、それを悲願し、永遠の平和を冀求する。さらに、われ〱沖縄人としては、すぎ去つた『悪夢のような戦争』を、忘れることなく、もう一度、当時を顧みて、一つの猛省の機とし、併せて、次代への新らしい発展を期する資料となし、後世に傳えて、再びあの愚をくりかえさぬよう熟願したい。
幸か、不幸か、当時一縣一紙の新聞紙として、総ゆる戦争の困苦と戦いながら、壕中で新聞発行の使命に生きた、旧沖縄新報社全社員は、戦場にあつて、つぶさに目撃体験した、苛烈な戦争の実相を、世の人々に報告すべき責務を痛感し、ついに、終戦四年目の、一九四九年五月、本書編纂を、旧沖縄新報社編集局長、現沖縄タイムス社理事豊平良顕【監修】、現沖縄タイムス社記者伊佐良博【執筆】、旧沖縄新報社記者、現沖縄タイムス社記者牧港篤三【執筆】、の三名に托し、一年を経て、上梓の運びに至つた。前述のごとく、この記録は、軍の作戦上の動きを捉えるのが目的ではなく、あくまでも、住民の動き、非戦闘員の動きに重点をおいたという点、他に類がなく、独自な性格をもつゆえんである。なおこの動乱を通じ、われ〱沖縄人として、おそらく、終生忘れることができないことは、米軍の高いヒューマニズムであつた。国境と民族を超えた彼らの人類愛によつて、生き残りの沖縄人は、生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏みだすことができたことを、特筆しておきたい。
1950年7月1日 – 沖縄タイムス社しるす
■『鉄の暴風』の初版は、米軍の出版許可が不可欠だった
上記の引用から明白に分かる事実は、初版の”まえがき”の最後の太字の部分が第2版から削除されていること。
削除の理由は、敵国の米軍を「高いヒューマニズム」や「人類愛」などとあまりにもあからさまに褒め上げてしまっては、『鉄の暴風』が米軍のプロパガンダとして書かれた事実がバレると懸念したのだろう。
しかし、いくら沖縄タイムスが隠蔽を企てようとも、『鉄の暴風』が意図する「人類愛に満ちた米軍」と「残虐非道な日本軍」という米軍に媚る表現は必要不可欠だった。 初版の当時は、米軍の検閲(ニミッツ布告)を通らないと出版は許可されなかったからだ。
第二版が「米軍を忖度」する記述を削除した理由は他にもある。
つまり初版当時は沖縄戦の悲劇を語るにも”米軍への忖度”が無ければ、出版は許可されなかったことを暗示しているが、第2版が出版された1970年6月20日、はすでに初版後20年も経過しており、今さら米軍に「高いヒューマニズム」などと忖度する必要がなくなっていた。
噛み砕いて説明しよう。朝日新聞は沖縄タイムスが持ち込んだ『鉄の暴風』の出版を当初「戦記物は売れ無い」という理由で発刊を辞退した。ところが沖縄タイムスの座安専務がマッカーサーに依頼したら朝日は掌返しで出版を承諾し、初版は朝日新聞で刊行された。 マッカーサーから朝日の直接出版の指示があったので、朝日は米軍への忖度をした「まえがき」をそのまま忸怩たる思いで掲載した。
この事実は初版と第2版の発行目的が明らかに違うことを意味している
『鉄の暴風』の「取材」は沖縄タイムスの創刊にも関わった座安盛徳氏(後に琉球放送社長)が、米軍とのコネを利用して、国際通りの後の国映館(洋画専門館)の近くの旅館に「情報提供者」を集め、太田氏はそれをまとめて取材したと述べている。
当時全沖縄の情報を押さえていた米軍の協力があったからこそ、三ヶ月という短期間の取材で『鉄の暴風』を書きあげることができたという太田氏の話も納得できる。
このように太田記者の経験、取材手段そして沖縄タイムス創立の経緯や、当時の米軍の沖縄統治の施策を考えると『鉄の暴風』は、米軍が沖縄を永久占領下に置くために、日本軍が「残虐非道」であることを沖縄人に広報するため、戦記の形を借りたプロパガンダ本だということが出来る。
当時の沖縄は慶良間上陸と同時に発布された「ニミッツ布告」の強力な言論統制の下にあり、『鉄の暴風』の初版本の原稿は英語に翻訳され、米軍当局やGHQのマッカーサーにも提出され検閲を受けていた。
■『鉄の暴風』、シーツ軍司令官が出版拒否。
英語に翻訳された『鉄の暴風』の原稿は、先ず当時の沖縄の最高責任者シーツ米軍沖縄司令官の元へ出版許可のため提出された。
ところがシーツ司令官は原稿の内容に興味を示したが、何故か出版を拒否した。米軍のことを「ヒューマニズム溢れる」などと賛美し、日本軍のことを「沖縄住民に集団自決を命ずる残虐非道な日本兵」と罵声を浴びせる『鉄の暴風』は、沖縄と日本の分断を目論む米軍の意図に沿った内容であり、米軍当局が出版を推奨はしても出版拒否など考えられないことだった。
これに加えて今回、張本人の沖縄タイムスが自社の出版物で、しかも『鉄の暴風』のもう一人の執筆者・牧港篤三氏の談話として米軍と沖縄タイムスの関係について語っている記述を発見した。
沖縄タイムス発行の『沖縄の証言』(上巻)(沖縄タイムス編 1971年)が、『鉄の暴風』発刊の裏話を7頁にわたって掲載し、「米軍の“重圧”の中で」「三カ月かけて全琉から資料を集める」「書けなかった、ある一面」などの小見出しの下に、米軍の監視のもとに書かざるを得なかった執筆の内幕を書いている。
1971年といえば沖縄が返還される一年前。
まさかその30数年後に『鉄の暴風』が原因となる裁判沙汰が起きようなどとは夢想もせずに、二人の執筆者は気軽に本音を吐いていたのだろう。
関連部分を一部抜粋する。
<原稿は、翁長俊郎(元琉大教授)に翻訳を依頼し、英文の原稿を米軍司令部へ提出した。 当時の軍政長官シーツ少将が、感嘆久しくした、といううわさも伝わった。 にもかかわらず、しばらく反応はなかった。 あとでわかったのだが、米軍司令部で関係者が目をとおしたのち、「オレにもよませろ」と、ほかにも希望者が続出して許可が遅れたのだという。 米側にも公表だったわけである。>『沖縄の証言』(上巻)(303頁)
脱稿後翻訳して米軍に出版の許可を仰いでいることはこの記述で明らかである。
<「鉄の暴風」(初版)の序文には、米軍のヒューマニズムが賞賛されている。 「この動乱を通し、われわれが、おそらく終生忘れ得ないのは、米軍の高いヒューマニズムであった。 国境と民族を超えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏み出すことができた。 このことを特筆しておきたい」。 たしかに、戦場の各所で、多くの住民が米軍に救出され、米軍に暖かいイメージを抱いたとしても不思議ではない。 沖縄住民は日本に見離され、米国の被保護者に転落していたのだから。
しかし、「鉄の暴風」が米軍のヒューマニズムを強調したのは、そこに出版の許可条件を満たすための配慮もなされていた、という時代的な制約を見落としてはならないだろう。>(304頁)
太字強調部分は多くの研究者が言及していたが、沖縄タイムス自らがこれを認めた記事は珍しい。
「鉄の暴風」のラジオ放送は、1945年(昭20)12月9日からNHKで放送された、ラジオ番組「真相はこうだ」を明らかにい意識していた。
「真相はこうだ」は、NHKの独自番組のように放送されたが、実際は脚本・演出までGHQの民間情報教育局が担当した。
内容は満州事変以来の軍国主義の実態を暴露するドキュメンタリーで、アメリカの都合で故意に歪曲された部分も少なくなかった。
『鉄の暴風』の執筆にあたり、戦前からのベテラン記者である共著者の牧港篤三記者は、元々戦記には造詣が深かったが、当時可能な限りの戦記を取り寄せ執筆に備えたという。一方、元々作家希望だった太田良博はトルストイの文学作品を読んでいたというが、それが「戦争と平和」と牧港記者は言っている。
■苦しかった執筆条件
《苦しかった執筆条件
牧港篤三談(執筆者の一人ー引用者注)
戦記執筆前に日本の戦記出版類をたいてい読み、太田君もトルストイの「戦争と平和」を精読したと言うことでした》(307頁)
「鉄の暴雨風」の問題の箇所「集団自決」を執筆した太田良博氏は、沖縄タイムス入社直前まで米民政府に勤務する文学愛好家であった。
戦前からのベテラン記者であった牧港篤三氏が執筆の前に準備として目を通したのが日本の戦記物だったのに対し、文学青年の太田氏が精読したのは戦記の類ではなく、トルストイの「戦争と平和」であったという事実は『鉄の暴風』の性格を知る上で興味深いものがある。 太田は、後の作家曽野綾子との対談で、『鉄の暴風』は名前も思い出せない人物の噂話を検証見せず記した、と語っている。
牧港記者の回想は続く。
<米軍占領下の重ぐるしい時代でしたから、米軍関係のことをリアルに書けば、アメリカさんは歓迎すまい、といった、いま考えると、つまらぬ思惑があったのも事実です。 タイムリーな企画ではあったが、書く条件は苦しかった。>(307頁)
2005年に提訴された「大江岩波訴訟」「戦後民主主義」の呪縛に取り込まれ裁判長が、必死になって大江健三郎と岩波書店を守るための根拠となる『鉄の暴風』に誤った評価を与えても、執筆者の太田良博氏や、牧港篤三氏がその遺稿や談話で「『鉄の暴風』はウワサで書いた」とか「米軍重圧の思惑のもとに書いた」と吐露している以上、『鉄の暴風』に資料的価値を求める深見裁判長の判断は、逆説的意味で正しいという皮肉な結果になる。
つまり、『鉄の暴風』が書かれた昭和24年当時、米軍の広報紙の沖縄タイムスが、沖縄戦記を書くには米軍の意向に沿った噂で書くのもやむえなかった。そのような時代背景の歴史を知るために、『鉄の暴風』の資料的価値は充分にあるという逆説だ。
米軍のプロパガンダとして発刊されたと考えれば、『鉄の暴風』が終始「米軍は人道的」で「日本軍は残虐」だという論調で貫かれていることも理解できる。
■シーツ善政
ジョセフ・ロバート・シーツ(Josef Robert Sheetz、1895年11月20日 - 1992年1月28日[1])は、1939年から1941年までアメリカ陸軍指揮幕僚大学で教鞭を取り、太平洋戦争が勃発した1941年、陸軍省副参謀長に転任した。1944年には陸軍准将・第二十四軍団砲兵指揮官となり、1945年には沖縄戦の戦場に赴き、この部隊を指揮した。
終戦後は1949年10月、ウィリアム・イーグルスの後任として琉球軍司令官・琉球列島米国軍政府の軍政長官に就任した。
シーツは終戦後4年を経てなお経済・治安の混乱が続き、米軍の軍規も乱れていた沖縄において、経済復興、政治体制の確立、治安改善などの復興策に組織的に取り組んだ占領後初の軍政長官となった。
具体的には那覇市街地の首都としての再建、琉球・奄美・宮古・群島民政府の設立とその知事・議員の公選、米軍部隊の再編成と待遇改善・綱紀粛正などを行い、その施政は当時の沖縄住民によって「シーツ善政」と称えられた。
■マッカーサーとシーツ司令官
一般的に日本兵を語る時、日本兵は天皇に対する狂信的忠義を糧に徹底抗戦を続けた戦士として、その狂気じみた戦意を取り上げて諸外国の軍隊には見られない無い特異(奇異)な存在として語られる場合が多い。
ところが交戦相手である米国が見た日本兵の姿は必ずしもそうではない。防衛戦に長け、飢餓と弾薬不足でも戦意を失わず、むしろ米兵でも共感できるくらいの感性を持ち合わせていたこと、彼らも同じような人間臭さが有ったことを吐露している。
特に沖縄戦で沖縄攻撃の最前線で指揮を執った海兵隊のシーツ司令官にとって、米軍に比べて質量とも極めて貧弱な兵器で、果敢に米軍に立ち向かう日本兵は一種の驚きと同時に戦士として一種の畏敬の対象ですらあった。想像するに、シーツ司令官はぜい弱な軍備で果敢に立ち向かう日本兵をみて、「サムライ」が持つ「敵ながらアッパレ」の気概を感じたのだろう。
さて、沖縄タイムスの座安専務はシーツ司令官に出版を拒否された後上京し、GHQ最高司令官マッカーサーに面会し、『鉄の暴風』の出版を直談判、マッカーサーのお墨付きを得て出版にこぎ着ける。
そして不思議なことに座安氏ら沖縄タイムス一行が意気揚々と沖縄に帰った後、「シーツ善政」として沖縄住民に慕われたシーツ長官が病気を理由に僅か1年余で更迭され沖縄の歴史から姿を消す。マッカーサーに逆らったから、という噂もあったが真相は闇の中である
■『鉄の暴風』出生の秘密■
■米軍は解放軍■
『鉄の暴風』という言葉から受ける印象は、「沖縄対日本軍」の戦いであり、日本軍は沖縄県民を虐殺するが、米軍は日本の沖縄を解放に来た解放軍だという印象だ。
2007年10月30日付世界日報にこんな記事が掲載された。
《米、数千人動員して民間人救出
「米軍より日本軍怖い」感覚へ
沖縄戦に関する沖縄県民の手記には、しばしば「米軍よりも日本軍の方が怖かった」という感想が出てくる。言葉も通じない敵の軍人に、同じ日本人よりも親近感を覚えるということが果たしてあるのだろうか。それは、米軍が「日本の圧政に苦しみ、虐げられている状況を打開してくれた解放軍」という認識を、県民が抱くようになって初めて可能だ。(略)(世界日報 2007年10月30日)》
太田元沖縄県知事の一連の著書にはこのような記述が見られる。
≪その意味では、沖縄戦のあとに上陸してきたアメリカ軍は沖縄にとって解放軍のはずだった。≫
(大田昌秀著「沖縄の決断」朝日新聞社刊)
沖縄タイムスが極端な偏向を通り越し、敵意剥き出しの反日報道をするには理由があった。
■沖縄タイムス出生の秘密■
その訳を深く掘り下げると沖縄タイムスの出生の秘密にたどり着く。
それは昭和25年に発行された『鉄の暴風』の初版の前文にすべてが凝縮されている。
前文に「米軍の高いヒューマニズム」「米軍の人類愛」などと書かれている。揉み手をしたような、この米軍へのおべんちゃら記事が『鉄の暴風』の記事だと知ると驚く人も多いだろう。勿論、沖縄タイムス出生の秘密を暗示するこの前文はその後の重版では削除されている。
『鉄の暴風』は主として沖縄タイムス記者太田良博氏によって書かれたが、同書のもう一人の著者、牧港篤三氏によれば、初版は2万部出版され「米軍に提出されるため英訳され、占領軍司令部でも話題になった」と記している。(沖縄タイムス平成14年6月12日付け)
■米軍広報紙としての出発■
さらに沖縄タイムスの創立者の1人座安盛徳氏(故人)は昭和25年5月2日、東京のGHQを訪問し、当時の沖縄人としては珍しくマッカーサー元帥と面談もしている。
当時は日本政府の要人でさえ面会の難しかったマッカーサー元帥に沖縄タイムスが容易に面会できた事実に驚かされる。
これによって沖縄タイムスが米軍の沖縄占領政策の重要な一部門に組み込まれていたことが分かる。
マッカーサーとの面談の三ヵ月後に『鉄の暴風』は初版が出版されることになる。
■「鉄の暴風」に続く「紙の爆弾」■
当時、不足気味の新聞用紙の提供など報道に必要な備品は全て米軍によって提供された。
<沖縄戦に関する沖縄県民の手記には、しばしば「米軍よりも日本軍の方が怖かった」という感想が出てくる。言葉も通じない敵の軍人に、同じ日本人よりも親近感を覚えるということが果たしてあるのだろうか。それは、米軍が「日本の圧政に苦しみ、虐げられている状況を打開してくれた解放軍」という認識を、県民が抱くようになって初めて可能だ。>(世界日報「米軍より日本軍怖い」感覚へ)
米軍は「鉄の暴風」を吹き荒れさせた後は、
「紙の爆弾」といわれた膨大な量の宣伝ビラを島中にばら撒いて住民と日本軍の分断を図った。
この心理作戦遂行のため、情報部は沖縄での空中散布用に五百七十万枚のリーフレットを印刷。米軍上陸後にまかれたあるビラの文面を紹介しよう。
「皆さん達の家はこわされたり、畑や作物は踏み潰され又元気盛りの青年は殺され、沖縄の人は皆口に言えぬ苦労をしています。内地人は皆さん達に余計な苦労をさせます。……日本兵が沖縄の人々を殺したり住家をこわしたりしている事は皆さん達に明らかでしょう。この戦争は、皆さんたちの戦争ではありません。唯貴方達は、内地人の手先に使われているのです」(世界日報より)
全島に降り注いだ紙の爆弾の効果はてき面だった。
■沖縄と日本との分断工作■
『鉄の暴風』が書かれた戦後5年目の沖縄は通信手段や交通手段さえ現在とは比較にはならない。
バスやタクシーが未だ無いので、交通手段は勿論電話や取材用の紙さえ米軍に頼らざるを得なかった。
■不可思議な取材活動■
『鉄の暴風』著者太田氏の取材の様子を世界日報は次のように報じている。
≪さて、太田氏はこの反論連載(沖縄タイムス掲載の曽野綾子氏への反論)の中で『鉄の暴風』の取材期間が「三ヶ月、まったく突貫工事である」と書いている。≫
現役記者の鴨野氏は、取材活動でケータイは勿論PC、カセットテープを駆使し、移動手段も飛行機、電車、車、場合によってはミニバイクに乗って取材活動している。
『鉄の暴風』の取材方法については、同業者として次のように疑念を呈している。
≪記者二人で、三ヶ月の取材で書き上げた分量は四百字詰め原稿用紙で750枚前後に及ぶ膨大なものだ。 しかも離島だけではなく、本島の北から南にまでの兵隊や住民の動向を取材の視野に入れている。・・・・果たして証言内容を精査、吟味する時間をどれほど持てたのだろうか。≫
だが、読者の疑念は次の事実で氷解する。
『鉄の暴風』は証言内容の精査、吟味は不要であり、
米軍がその機動力で一か所に集めた都合の良い「証言」者から聞き取るだけで済んだからである。
何故なら『鉄の暴風』発刊の主旨は著者がいう「歴史の記録」というより、「住民と日本との分断」という米軍の意図の下で発刊を許可されていたからである。
■米軍協力で集められた「証言者」■
昭和25年、那覇市の今で言う国際通りの国映館界隈は未だ道路も舗装されておらず米軍トラックが通ると埃が朦々と立ち込める悪路であった。
埃っぽいその道路から奥まった一角に在った某旅館に「集団自決」の証言者と称する人たちが集められた。
米軍の協力の下、実際に動いて証言者を集めたのは、沖縄タイムス創立の1人座安盛徳氏であった。
『鉄の暴風』の著者が不備な交通手段や通信手段を使わなくとも済むように、座安氏は先ずその旅館に「証言者たち」を集め、取材の準備を万端整えた。
そして『鉄の暴風』の連載を企画し、その後、単行本実現に米軍情報部との強力なコネを通じて影の力を発した。
その結果、太田氏は現地取材することも無く、一か所に集められた「関係者」からの聞き取りだけで「裏付け」をとることもなく、『鉄の暴風』を著したのである。
太田氏の取材は当時としてはある意味で、比較的容易に行われ、それが後日「伝聞取材」であると批判される原因になる。
一方影の著者とも言える座安氏のやったことは、「関係者」を集めるとは言っても、電話も交通手段も不備だった昭和25年当時の沖縄で、全島から「関係者」を一か所に集めることは至難の業で米軍の機動力の支援なくしては出来ない仕事であった。

 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします