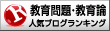⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします
読者の皆様へ
■出版社の都合で約1月発売が遅れる見込みです。 9月21日ごろ
8月15日発売を目途に皆様に献金をお願いした『沖縄「集団自決」の大ウソ』の編集作業が現在進行中です。ただ販促物のチラシ作成など、さらに最低限の出版数400冊で調整中ですが、出来れば市場に出回る出版数も800冊~1000冊と一冊でも多い方が目立ちますし、本の体裁もより目立つ体裁にしたいと考えています。
そこで再度皆様の献金ご協力お願いいたします。
■出版費用の献金のご協力願い
最低限での出版には何とか漕ぎつけましたが、増刷等で皆様の献金ご協力を伏してお願い申し上げます。
献金額の多寡は問いませんが、一口3000円以上にして頂けると幸いです。
まことに勝手なお願いですが、宜しくお願いいたします。
狼魔人日記
江崎 孝
お振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:江崎 孝
- 記号:17050
- 番号:05557981
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通預金
- 名義:江崎 孝
- 店名:708(読み ナナゼロハチ)
- 店番:708
- 口座番号:0555798
★すでに御献金賜った方には、出版本を贈呈したいと思いますので、下記メルアドに贈呈本の送り先、住所氏名をご一報いただければ幸いです。
管理人への連絡⇒ezaki0222@ybb.ne.jp
★
事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。- ニーチェ -
「捨て石にされた沖縄」否定する百田尚樹氏
阿部岳|2018年7月21日1:11PM
沖縄戦を体験した90歳の女性が亡くなった。組織的戦闘が終わったとされる6月23日の「慰霊の日」直前のこと。平和学習の語り部として高校に招かれ、駐車場で急変した。戦争体験を語るにも聞くにも、残された時間は少ない。現実が胸に突き刺さる。
体験者の声が小さくなるにつれ、「沖縄戦の教訓」への攻撃は強まっている。早い時期に狙われたのが「集団自決」の史実だった。日本軍は住民を保護対象ではなく、戦闘の足手まとい、機密を敵に漏らす危険分子とみなした。手榴弾を渡すなど、住民同士の殺し合いを強制、誘導した。
2005年、慶良間諸島の元戦隊長らが大江健三郎氏と岩波書店を提訴した。書籍で戦隊長らの「命令」に触れたことが名誉毀損だと主張した。07年にはこの訴訟を根拠の一つとして、教科書検定で「軍の関与」の記述が削除された。県民は猛反発し、復帰後最大の11万6000人が県民大会に結集するなどして押し戻した。訴訟も最高裁まで争った末、元戦隊長らの敗訴が確定した。
それでも、波状攻撃は続く。今年4月、沖縄での講演で作家の百田尚樹氏はこんなことを言っている。「決して沖縄だけを犠牲にしたわけじゃない。日本全体が犠牲になった」。広島、長崎の原爆、各地の空襲被害を例に挙げた。「沖縄だけ被害者ぶるな」という論法はネットでもよく聞かれる。
多数の民間人が殺傷された悲惨は全国に共通する。違うのは、本土の空襲目標が米軍の選択だったこと。沖縄は、日本軍が本土を守る時間稼ぎの戦場として選んだ「捨て石」だった。
その否定を試みて、百田氏は「神風特攻隊、戦艦大和が沖縄防衛のために出撃した。沖縄を見捨てるなら、そんなことはしない」とも述べた。特攻の将兵も、無謀な作戦の捨て石にされた。沖縄から見ると、日本軍指導部への怒りを共有することはあっても、感謝する理由はない。
何より、沖縄戦では日本軍が住民を壕から追い出し、食糧を奪い、スパイ視して虐殺した。「軍隊は住民を守らない。軍隊自身と権力を守る」。住民の4人に1人を失うという惨劇の末に、県民は教訓を学んだ。
自衛隊は今や、その日本軍から引き継いだDNAを隠さなくなっている。「沖縄を守るために戦った第三二軍を、現在の沖縄防衛を担うわれわれが追悼する」。05年の慰霊の日。沖縄戦の牛島満司令官らの慰霊搭を前に、沖縄の陸自トップが述べた。
牛島司令官は総司令部が陥落した後も住民多数が避難している本島南部に撤退し、犠牲者を大幅に増やした。自決前には部下に徹底抗戦を命じ、降伏の機会を奪った。その人物を追慕する集団参拝を、幹部自衛官が04年から15年連続で続けている。
奄美大島、宮古島、石垣島、与那国島。各地で自衛隊基地の新設が進む。「離島防衛のため」という大義名分を真っ向から否定する「住民を守らない」という真実は不都合で、邪魔である。だから狙われる。ここが突き崩される時、南西諸島の軍事化が完成するだけでなく、日本全体が「戦争のできる国」になるだろう。
この時代に沖縄戦の教訓をどう受け継ぐか。戦争を知らない私たちの想像力が問われている。
(あべ たかし・『沖縄タイムス』記者。2018年6月29日号)
【おまけ】
■日本軍は住民を守らなかったのか■
ウソも繰り返せば真実となり、根拠の無いスローガンも繰り返せば出版物となり、結果的には歴史として刻まれる。
連日沖縄の紙面で躍る「日本軍は住民を守らない」という左翼の主張は、「反日運動のために捏造されたスローガン」にすぎない。
では、沖縄戦の真実はどうだったか。
昭和19年の夏から大本営と沖縄配備の第32軍が、沖縄県民の安全を守るため、県や警察と協力し、県外疎開に必死の努力をしていたという歴史的事実に、沖縄メディアは全く目を閉ざしている。
戦時中といえども法律の下に行動する軍は、当時の日本の法の不備に悩まされていた。日本は過去の戦争において常に戦場は国外であり、そのために昭和19年の第32軍沖縄配備の時点で、国民を強制的に疎開させる法律を備えていなかった。
ドイツやフランスのように国境が陸続きの大陸国では、戦争といえば国境を越えて侵入する敵軍を想定する。
だが、四面を海に囲まれた海洋国家の日本では、敵の自国内侵入は海上での撃滅を想定しており、地上戦を考えた疎開に関する法律は整備されていなかった。
第32軍が沖縄に着任した昭和19年当時、戦時中であるにも関わらず当時の日本には、何と現在の平和な時代でも具備している「国民保護法」(平成16年6月18日 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)に相当する法整備がなされていなかったのである。
そのような状況で沖縄防衛を任される第32軍が沖縄着任に決まった。
沖縄着任に先立って日本軍が最も憂慮したのは、米軍の上陸により沖縄住民が戦火に巻き込まれることであった。
■県民疎開は大本営の発想■
昭和19年7月1日、大本営の後宮参謀次長は、関東軍司令部から参謀本部付きとなっていた長勇少将を特命により沖縄に派遣した。 その特命の目的は食糧不足のための兵糧の研究が表向きであったが、その他にもう一つの重要な任務を命じられていた。
同じ年の8月10日に第32軍司令官、牛島満中将が沖縄に着任するが、長少将はその一月前の7月1日に沖縄に着任し、真っ先に行ったのが住民の県外疎開調査のための県内視察であった。
既に第32軍の参謀長を拝命していた長少将は、調査結果を第32軍司令官渡辺正夫中将(牛島司令官の前任)に報告し、司令官は陸軍省に県民の県外疎開について具申し、それを受けて7月7日に県民の県外疎開の閣議が決定される。沖縄配備の第32軍は、長勇参謀長の沖縄着任(正式には昭和19年7月8日 )の一日前には、法整備の不備だった「県民の県外疎開」を着任前に閣議決定させるという素早い動きをしていたのだ。
大本営は米軍の沖縄上陸は必至と予測し、牛島満司令官着任の一ヶ月以上も前の昭和19年7月1日に長参謀長を沖縄に派遣したが、これと連動した内務省防空総本部も救護課の川嶋三郎事務官を沖縄に派遣し、県民疎開の閣議決定の下準備をさせていたのだ。(「消えた沖縄」浦崎純著・1969年)
緊急閣議決定で法的根拠は得たが、第32軍の県外疎開の実施にはさまざまな困難が伴った。今の時代で安易に想像し、軍が圧倒的権力で有無を言わせず県外疎開を命令し、実施したわけではなかった。
県民の県外疎開を管轄する政府機関は内務省防空総本部であった。当時の法律では空襲に備えて県外疎開を強制することは防空法に規定があったが、沖縄の場合のように地上戦に備えて非戦闘員を強制的に疎開させる法的権限は持っていなかったのだ。当時の沖縄の状況は新聞の勇ましい扇動報道に乗せられた各民間団体の「軍人より軍人らしい民間人」の狂気が巷にあふれ、県外疎開の必要性を説いても、それに真面目に耳を傾けるものは少数派で、県外疎開は卑怯者と後ろ指を指される有様だった。
県外疎開を民間人に直接命令する権限の無い第32軍は、民間人の安全を管轄する県に協力を求め、県は警察の持つ組織力と機動力によることが最適と考え県外疎開の担当部署を警察部と定めた。
現在のような平和な時代の後知恵で、「軍の命令は自分の親兄弟を殺害する」(軍命による「集団自決」)ほど圧倒的で不可避であったと「沖縄タイムス史観」は主張する。
だが、実際は軍隊は住民に直接命令をする権限を持たず、住民の安全を確保するための県外疎開すら県や警察機構の協力を仰がなければ実行できなかったのである。
■県外疎開は軍の発議■
沖縄タイムス、琉球新報の沖縄二紙は、「軍は住民を守らなかった」というスローガンを掲げ、沖縄戦はまるで日本軍が沖縄住民を虐殺する戦いであったかのような報道で県民を扇動するが、県民が地上戦に巻き込まれるのを最も憂慮していたのは軍であり、牛島第32軍司令官が沖縄に着任する一ヶ月前に、県民の県外疎開の閣議決定を発議し、県民の安全を真っ先に考えたのは他ならぬ、軍当局であった。少なくとも、「軍は住民の安全を守ろうとしていた」。
沖縄防衛のため戦った第32軍を代表する軍人といえば、司令官の牛島中将と参謀長の長勇少将が上げられるが、この二人は、軍人というだけで、沖縄での評価は極端に低い。長参謀長に至っては、大陸戦線で南京攻略に参加していたという理由だけで、「南京大虐殺」の実績を引っさげて「沖縄人虐殺」のために沖縄にやってきた、といわんばかりの悪評を受けている。牛島司令官も長参謀長ほどではないにしても、左翼勢力にとっては「悪逆非道な日本軍」のシンボルとして、牛島司令官の孫まで引っ張り出して日本軍を貶め、自分の祖父を罵倒するという醜いシーンまで披露している。日教組に毒された戦後教育の悪い面を、祖父を面罵する孫の姿に見出すのは残念なことである。
残された記録を検証すると、大本営は第32軍の牛島司令官が沖縄に着任する一ヶ月前には、次期参謀長予定の長参謀長を沖縄に派遣し、県民が戦火に巻き込まれないための県外疎開の研究を命じていたことがわかる。 だが、「悪逆非道の日本軍」をスローガンに掲げる沖縄紙が沖縄県民の県外疎開を真っ先に考えていた事実を報じることはない。
■県外疎開が進まなかった理由■
軍の命令が絶対であり、軍命であれば愛する親兄弟も殺すと主張するが正しいならば、住民の県外疎開など軍の命令一下で、容易に実行できそうなものである。ところが容易なはずの県外疎開には、いろんな阻害要件が次々発生して、軍と県による県外疎開の実施は思うようにうまくはいかなかった。
その第一は、沖縄の地理的要因であった。 今と違って当時の沖縄では、本土他県に行くと言うことは大変なことで、特に疎開の対象が老幼婦女子に限られていた関係上、家族と別れるくらいだったら一緒に死んだ方がマシだという風潮も県外疎開の阻害要因であった。東京から長野に汽車で疎開する学童に比べれば、沖縄の学童が船路で九州各県に疎開することは大変な決心を要する一大事であった。
次に当時の泉県知事がどういうわけか軍の指示にことごとく反抗し、県外疎開に消極的な態度を示した。「公的な立場では言えないが、個人の意見では引き揚げの必要はないと思う・・・」と発言し、県外疎開などせずに済めばこれに越したことは無いといった県内の風潮に拍車をかけていた。(浦崎純著「消えた沖縄県」)
第32軍は牛島司令官が着任の一ヶ月前から、県民の県外疎開を実施を計画していたが、軍の意思に反して疎開が無くても良いといった風潮は、泉知事や県民の大多数だけではなく、疎開を促進しようとする軍司令部の末端にもその風潮はあった。軍の指令のうまく行きわたらない地方の部隊では、第32軍が沖縄でがんばっているのにわざわざ疎開などする必要は無い、と疎開実施をぶち壊すような放言するものもいた。
遅々としてはかどらなかった疎開が一挙に盛り上がったのは昭和19年10月10日、那覇市が米軍の大空襲で壊滅的打撃を受けてからである。
何事も切羽詰まってからでないと行動を起こさない県民性は昔も今も同じことであった。
■サイパンの惨劇■
軍が沖縄県民の疎開を考え始めたのは、米軍がサイパン島に上陸し、「絶対国防圏」の一角が崩れ始めた昭和十九年六月下旬の頃である。アメリカ軍の投降勧告によって集められた日本人住民の老人及び子供の周りにガソリンがまかれ火が付けられたり、米軍の呼びかけに応じて洞窟から出てきた女性全員が裸にされトラックに積み込まれ運び去られたということは戦後いろんな証言が記録されている。
当時の沖縄県民がどの程度「サイパンの悲劇」に関する正確な情報を持っていたかはともかく、当時の沖縄には南方帰りの県人が多かったり、大本営がサイパン陥落の直前に沖縄住民の県外疎開を急遽準備し始めた事実から、沖縄県民が「サイパンの悲劇」を知っていた事は容易に想像できる。
昭和19年6月28日の陸軍省局長会報で富永恭次陸軍次官は、「小笠原ト硫黄島・沖縄・大東島・先島ノ石垣島土民ヲ引キアゲル様ニシテ居ル。問題ガアルカラ外ヘ漏レヌ様ニ」と述べ、真田第一部長は、間もなく沖縄の第32軍参謀長に着任する長勇少将に「球ノ非戦闘員ノ引揚」の研究を指示している。
またサイパンが陥落直前の七月七日の陸軍省課長会報で軍務課長は「沖縄軍司令官ヨリ国民引揚ゲノ意見具申アリ、本日ノ閣議デ認可スルナラン」と報告、翌八日の陸軍省局長会報では、軍務局長が「球兵団地区ノ住民ハ、希望ニ依リ地区毎ニ、引揚ヲ世話スル事ニナル」と述べている。
沖縄県、陸軍省、内務省などの間で疎開計画を協議した結果、疎開人数は県内の60歳以上と15歳未満の人口(約29万人)の三分の一にあたる十万人、疎開先は宮崎、大分、熊本、佐賀の九州四県と台湾に決まった。
サイパン陥落の後、米潜水艦による疎開船「対馬丸」の撃沈(8月22日)もあったが、同年10月10日の那覇大空襲によって疎開機運は一気に高まり、昭和20年3月上旬までに、延べ187隻の疎開船で、沖縄本島の約6万人が九州、宮古・八重山の約2万人が台湾に疎開した。
米軍の沖縄上陸の可能性が高くなった19年12月以降は、第32軍と県、警察、学校の間で、残った住民の県内疎が計画され、3月中旬までに、沖縄本島中南部の住民約3万人が北部の国頭郡に疎開した。3月24日、米軍の艦砲射撃が始まった後も、上陸した米軍が沖縄本島を南北に分断、疎開の道が閉ざされた4月3日までの間、県北部へ向けて殺到した中南部の住民約5万人が県北部へ疎開した。
本格的な地上戦が始まる前、県外外の疎開をした沖縄県民は16万人に至った。当初は軍中央部の要請で政府が県外疎開を決定し、19年末からは、主として現地の32軍と沖縄県の間で県内疎開が実施された。
現在、昭和19年7月7日の閣議決定の記録は確認できないが、同じ日付の陸軍省課長が、「7月7日 課長会報 軍務(課長二宮義清大佐)沖縄軍司令官より国民引揚げの具申あり。本日の閣議で認可するならん」と述べていることから、沖縄県民の県外疎開が7月7日に閣議決定されたことと、それが軍の発議で行われたことは歴史的事実である。(大塚文郎大佐ー陸軍省医事課長ー「備忘録」、「戦さ世の県庁」孫引き)
■沖縄戦の本質■
沖縄戦といえば軍の側から見た戦略的な「戦史もの」、そして住民の側から見た「証言もの」と、多数の出版物があるが、軍と住民の間に立って「軍への協力と住民の安全確保」という二律背反の命題に努力した地方行政側の「戦記」は極めて少ない。
<戦争を遂行するために、「戦争」から国民ー非戦闘員を護るために、どのように準備をなし、どのような行動をとるべきか。 平時を前提として制定されている地方制度に何らかの特例を設けるべきか、非常の措置を行うためにどのような組織・権限ーそして特別規定が必要であるか。 すべてこのような問題に直面し、実際に回答を出さざるを得ないもの、それが沖縄県であり、沖縄県で遂行された「戦争」であった。>
これは沖縄復帰当時の公使・日本政府沖縄事務所長・岸昌氏が荒井紀雄著「戦さ世の県庁」の序文で沖縄戦の本質を語った文の抜粋である。沖縄戦当時、警察部長(現在の県警本部長)として、島田叡県知事とコンビを組んで、県民の安全確保に努力した荒井退造氏の長男の紀雄氏が、父退造氏が軍と住民の間に立つ文官として如何に沖縄戦を生き、そして死んだかを、多くの資料・証言を基に記録したのが「戦さ世の県庁」である。 戦火により多くの県政関係の資料が消失・散逸した中で同書は現在望みうる最高の記録である。
■軍司令官vs県知事■
現在の偏向した沖縄紙の論調でいえば、沖縄戦とは米軍との戦いというより、「悪逆非道な日本軍」が一方的に沖縄住民を殺戮していくといった「日本軍対沖縄」という構図になる。 そのイメージでいえば、戦時中、軍と対立し、何かといえば軍の言うことに反対していた県知事がいたといえば、きっと英雄的な勇気ある県知事が連想され、今でも県民の尊敬を受けていると思う人も多いだろう。
だが、実際はこの県知事、沖縄県知事の中でも最も評判の悪い知事であった。東京帝国大学出の内務官僚泉守紀氏が第22代官選沖縄県知事の辞令を受けたのは、昭和18年7月1日のことであった。 丁度同じ日付で荒井退造氏も沖縄県警察部長の辞令を受けている。
このように昭和18年の沖縄の夏は、のどかな町の風景とは裏腹に、県庁幹部が一新され、来るべき沖縄戦を予知してか県庁内外に何時にない緊張が走っていた。そんな空気の中、泉親知事は辞令より約一月送れて7月26日に赴任するが、沖縄防衛の第32軍(初代司令官は渡辺正夫中将)が昭和19年3月に沖縄に着任すると、泉知事は軍との対立を深め、修復不可能なものとなっていく。(野里洋著「汚名」)
そして政府は昭和19年7月7日の閣議決定で「沖縄に戦火が及ぶ公算大」と判断、沖縄県から60歳以上と15歳未満の老幼婦女子と学童を本土及び台湾へ疎開させることを決定、沖縄県に通達した。
疎開目標は「本土へ8万、台湾へ2万の計10万」と決定されたが、泉知事は公然とこれに反対したと言われているが、その理由は解明されていない。
もともと明治以来の官僚国家のわが国では、軍官僚と警察官僚は犬猿の仲であった。 東大出の優秀な内務官僚を自認する泉知事は警察畑を主として歩いてきており、軍の指示は受けないという内務官僚としてのプライドがあったのだろうか。
日本の官僚機構は縦割り構造だといわれる。 最近の官僚の不祥事を見てもその悪い面が前面に出て、「省益あって国益なし」という言葉が官僚を批判するマスコミの常套句として紙面を賑わす。
戦前の、武器を装備する官僚の代表の軍官僚と警察官僚(内務官僚)の意地の張り合いで有名な事件に、昭和11年に交通信号をめぐって起きたゴーストップ事件がある。泉知事の軍に対する反抗的姿勢が軍官僚と内務官僚の対立が原因かどうかはともかく、当初は県民の疎開機運は知事の軍への非協力的態度により一向に盛り上がらなかった。
当時の沖縄県の状況を、戒厳令に近い「合囲地境」の状態であったので軍の命令は圧倒的で、従って県や市町村の命令も軍の命令であるという意見は、泉知事の第32軍へ徹底した反抗で軍が県民疎開の実施に苦慮している状況をみても、それが机上で作り上げた空論であることが明らかである。
県民の疎開については、第32軍は法的には直接住民に命令を出せないので県の、特に警察機構の協力が必須であったが、泉県知事のかたくなな反抗に困り果てた結果、昭和19年年1月31日には軍司令官統裁の参謀会議で「沖縄県に戒厳令を布告、行政権を軍司令官が掌握し、知事を指揮下に入れる」検討を行ったが、実際には戒厳令も合意地境も発令されなかった。
■県外疎開に水をかける「街の情報屋」■
第32軍は沖縄県民の県外疎開を真剣に考えていたが、その一方その頃の沖縄県民の県外疎開に対する無関心振りを、当時の那覇警察署僚警部で戦後琉球政府立法議員議長を務めた山川泰邦氏は自著『秘録沖縄戦史』(沖縄グラフ社)で次のように述べている。
<だが県民は、襲いかかってくる戦波をひしひしと感じながらも、誰も必勝を疑わず、その上無責任な街の情報屋は、「まさか、沖縄に上陸するようなことはあるまい」と勝手な気炎を吐いたため、これが疎開の実施に水をぶっかけるような結果になった。それに、当時海上は潜水艦が出没して、既に2回にわたり集団疎開船が撃沈され、多数の犠牲者を出したために、「どうせ死ぬなら、海の上で死ぬより、郷里で死んだ方がよい」と疎開の声に耳をかたむけようとしないばかりか、はては疎開を命令で強制された場合のことを心配する始末だった。>
勇ましい情報を垂れ流し、県民疎開の実施に水をかけていた「街の情報屋」が誰であったかを山川氏は特定していないが、当時の新聞報道やその他の史料から推測すると、県民疎開を発案した軍やそれの実施に軍から協力依頼されていた行政側ではないことは間違いなく、決起大会等でも、中には演壇の上で抜刀し檄を飛ばしていた「軍人より軍人らしい民間人」の姿がここでも思い浮かぶ。 戦後、琉球政府時代になって活躍した著名人の中にも平良辰雄氏、や当間重剛氏のように、当時は民間団体の責任者として県民を扇動していたという。そのような雰囲気では県外疎開などは県外逃亡と看做され軍の思惑とは裏腹に県民の県外疎開に水をかけていたのだろう。
昭和19年12月に第32軍が「南西諸島警備要項」を作成し「敵の上陸に備えて60歳以上と15歳未満の老幼婦女子と国民学校以下の児童を昭和20年2月までに本島北部に疎開させる」と言う計画を作成したが、泉知事は「山岳地帯で、耕地もない北部へ県民を追いやれば、戦争が始まる前に飢餓状態が起きる」と反対した。
確かに当時の食糧事情は厳しいものがあったが、軍民混在を避けたい軍の意向と泉知事の意見のどちらが正しかったかは、北部に疎開した県民が比較的戦火の被害が少なかった事実を見ても明らかであろう。
軍が県民疎開にこだわった理由は、7月に起きたサイパンの悲劇を教訓に、主目的は軍の作戦を円滑にする為であるが、何とか住民を避難させて、結果的に住民の犠牲を最小限にとどめようと考えた結果であったが、泉知事にことごとく妨害された訳である。 泉知事は一ヵ月後の翌年1月には出張と称して本土に渡り、二度と沖縄に戻ることはなかった。
その後任として島田叡氏が次期知事に着任するのである。
泉知事の後任の島田知事が泉知事とは対照的に軍と緊密に協力し県外や県内北部への疎開など県民の安全確保に全力をそそいだ。 後の沖縄県の調べでは県外疎開は1944年7月から翌年3月まで延べ187隻の疎開船が学童疎開5586名を含む6万2千名(疎開者数を8万とする史料もある)を疎開させ、これに合わせて沖縄本島北部への県内疎開は約15万と推定されている。
翌年3月の米軍上陸前という重要な時期に県内外の疎開が円滑に行かなかったのが、後の沖縄戦での「軍民混在」という住民巻き添えの悲劇に至った伏線になっている。 軍を悪と看做す現代の感覚でいえば、軍と県の対立といえば聞こえがよいが、島田県知事の前任の泉知事はむしろその年に沖縄に駐屯した32軍は思ったより冷静で、次のような判断をしていたとの記録が残っている。
<かの物量を誇る米軍に対しては精神面だけでは到底勝算を得られないのであり、離島である沖縄は敵の本格的攻撃にあっては孤立し、・・・>(馬淵新治著「住民処理の状況」)
県外疎開に関する閣議決定の一ヶ月後、牛島満中将が32軍の新任司令官として沖縄に着任することになる。「軍は住民を守らなかった」という左翼勢力のスローガンからは想像も出来ないが、昭和19年の夏に沖縄に着任した第32軍の司令官と参謀長は、沖縄が戦地になることを予見し、且つ「県外疎開」の法律の不備を憂慮して、大本営の発議によっり着任前に「閣議決定」に持ち込むという早業を行った上で、後顧の憂いを極力小さくして沖縄に着任したのである。
日本軍の命令でマラリア蔓延地に強制避難 八重山で3600人病死の悲劇 住民が36人の証言集発刊
【八重山】八重山戦争マラリアを語り継ぐ会(潮平正道会長)は15日、証言集「命の輝きを求めて-マラリアを生き抜いた人々の証言」を発刊した。ことしは結成10周年で、証言をまとめたのは初めて。戦時中、石垣島を中心にマラリアに侵されて家族を失うなどつらい体験をした36人から聞き取り、手記を含めて38編をつづっている。
第32軍が沖縄に着任する以前から、大本営は、沖縄住民が戦禍にさらされるのを防ぐため閣議決定により県外疎開を決めていた。 だが県外疎開、実際は思うようにはかどらず、県内のより安全と思われる場所への県内疎開を余儀なくされた。
ただ当時の法体系でも軍が直接住民に疎開命令を出すことは出来ず、第32軍は「南西諸島警備要領」を作成し県知事に協力を要請し、知事は警察の組織力でこれに協力した。
沖縄本島では、島田知事と荒井県警部長が住民疎開に尽力したが、共に殉職し県民の恩人として今でも慕われている。
だが県知事や警察の疎開指導が届かなかった離島地域ではやむなく直接軍が疎開の指導をせざるを得なかった。
同じ疎開でも県が指導した場合は命の恩人と感謝され、軍が直接指導した疎開は「強制疎開」などと、住民を殺戮させるために疎開させたような書き方をするのが沖縄紙の特徴である。
八重山で疎開を指導した山下軍曹は戦後67年経っても、八重山マラリアで住民を虐殺した悪鬼として罵倒され続けている。
だが山下軍曹も島田県知事も、故郷に家族を残し使命を帯び決死の覚悟で沖縄に赴任した善良な父であり、夫であり兄だった。 彼らは住民を安全地帯に疎開させるという思いは同じで、唯一の違いといえば、軍服を着ていたかどうかの違いに過ぎない。
八重山住民を「日本刀で脅し、マラリアの汚染地域に強制的に疎開させた」と喧伝されている山下軍曹が、1981年にひっそりと島を訪れた時、八重山住民は「・・・戦前の軍国主義の亡霊を呼びもどすように来島したことについて、全住民は満身の怒りをこめて抗議する」と抗議書を突きつけたという。
その後山下軍曹は2度八重山を訪れ、その度に罵倒され追い返されたという。
なぜ山下虎雄軍曹は何度も島を訪れたのか。
山下軍曹が罵倒されるのを覚悟で3度も八重山地区を訪れたのは、自分が指導した疎開で不幸なことに多くのマラリアの犠牲者が出たことに対する贖罪の気持ちの表れではなかったのか。
山下軍曹にとって不幸だったのは、それこそ幸か不幸か、八重山地区は本島のような米軍による「鉄の暴風」に曝されることがなかったことである。
山下軍曹が八重山住民の虐殺を企む「悪鬼」ではなかった。
たまたま不幸にも八重山地区に着任したばかりに、疎開を自ら指導せざるを得なかった善良な日本人だった。
これは戦後3度も八重山地区を訪問した事実から窺い知ることができる。
その一方で同じ疎開でも、島田県知事、荒井県警部長に対する沖縄紙の記述は、彼らが軍人でないという違いだけで比較的まともである。
以下は大本営の密使 沖縄戦秘話3に加筆したものである。
☆
沖縄は地元出版の盛んな地域である。
沖縄戦に関する軍側から見た記録や住民側の記録が多数出版されて、地元の本屋の店頭を飾っているが、軍と住民の間に立って県民の安全確保のため奔走した県行政側から見た記録は極めて少ない。
県民の安全確保のため県内外の疎開を実行するため島田知事とコンビを組んで命懸けで尽力した荒井退造警察部長は「県民の恩人」として、島田知事と共に遺骨も無いまま、摩文仁の「島守の塔」に合祀されている。
万年筆県に寄贈へ 那覇市真地の「県庁壕」で発見(2008.7.27)
 「万年筆を多くの人に見てもらうことが義務」と語る荒井紀雄さん=東京都日野市
「万年筆を多くの人に見てもらうことが義務」と語る荒井紀雄さん=東京都日野市 「県庁壕」で発見された万年筆
「県庁壕」で発見された万年筆
【東京】沖縄戦中、県民の県外、北部疎開に尽くした荒井退造・県警察部長の遺品とみられる万年筆が、近く遺族から県に寄贈されることになった。万年筆は昨年12月、那覇市真地の通称・県庁壕(シッポウジヌガマ)で見つかり、6月に東京の遺族に届けられた。
長男の荒井紀雄さん(75)=東京都=は「この万年筆が父の物だと断定できるわけではないが、大変な犠牲を生んだ沖縄の惨禍の『証言者』だ。多くの人々に見てもらえることが、私の義務だと思う」と話している。
万年筆を見つけたのは「県庁壕」の発掘・調査を続けている知念賢亀さんと繁多川公民館「壕プロジェクト」のメンバーら。壕内の荒井部長室前の地中から掘り出した。
戦時中の県職員や遺族らでつくる「島守の会」を通じて送られてきた万年筆を調べたところ「並木製作所」(現・パイロットコーポレーション)が1932年発売の製品と類似。当時の標準品が3円から5円だったのに対し、見つかった万年筆は16円程度で売られていた。元県職員の板良敷朝基さん(「島守の会」顧問)は「部長以上の高官しか持っていない代物」と説明しているという。
昨年手術を受け、通院を続けている紀雄さんは「父は生前、『家族が私の骨を拾ってくれる』と語っていたという。骨は戻らなかったが、万年筆が息子の元へ戻ってきたと父は思っているかもしれない。私も生きていて良かった」と語っている。
「県庁壕」は、米軍が沖縄本島に上陸する直前の45年3月末から5月末までに県警察部が避難していた壕。4月から島田叡(あきら)知事も合流した。荒井部長は島田知事とともに5月末に本島南部へ移動。6月26日、知事と摩文仁の軍医部壕を出た後、消息を絶った。(小那覇安剛)
◇
■「狂気は個人にあっては稀なことである。しかし集団・民族・時代にあっては通例である」■ (ニーチェ )
この言葉は昨年、沖縄タイムスと琉球新報の沖縄二紙が「11万人集会」で県民を扇動していた頃、何度も当日記で引用させてもらった。
沖縄二紙は、狂気に満ちたキャンペーンを張って、「県民大会」に反対するものは県民にあらず、といった狂気に県民を追い込んでいた。
職場等でも異論を吐くものは、「あいつはヤマトかぶれ」だと後ろ指を指されるような異常事態だったと知人の一人は当時を振り返る。
個人的にはごく常識的な人物が、一旦なんらかのグループに属すると往々にして狂気に走る。
そしてその背後に新聞の扇動がある。
そんな例は歴史を紐解けば枚挙に暇がないほどだ。
軍情報局から日本敗戦間近の情報を得ていたにも関わらず、朝日新聞は、終戦の前日の8月14日の社説で、従来の「国民扇動」の論調を変えることが出来ずに、「敵の非道を撃つ」といった勇ましい記事を垂れ流し続けていた。
■昭和19年12月の「県民大会」■
昭和19年の12月8日、「日米戦争決起大会」(県民大会)が沖縄の各地で行われていた。
その当時の沖縄の雰囲気も、今から考えると狂気に満ちたものといえるだろう。
大詔奉戴日といわれたその日の「沖縄新報」には次のような見出しが踊っていた。
けふ大詔奉戴日 軍民一如 叡慮に応え奉らん
一人十殺の闘魂 布かう滅敵待機の陣
終戦の8ヶ月も前の記事なので、「沖縄新報」が、朝日新聞のように、敗戦間近の情報は得ていた筈はないが、見出しと記事がやたらと県民を煽っていることが見て取れる。
昭和19年12月の大詔奉戴日は、二ヶ月前の「10・10那覇大空襲」の後だけに、県庁、県食料営団、県農業会などの各民間団体が勇み立って、沖縄各地で関連行事(県民大会)を開催しているが様子が伺える。
ちなみに大詔奉戴日とは、日米開戦の日に日本各地の行政機関を中心に行われた開戦記念日のことを指し、真珠湾攻撃の翌月の1942年1月8日から、戦争の目的完遂を国民に浸透させるために、毎月8日が記念日とされた。
そして、同記事では「鬼畜米英」についても、各界のリーダーの談話を交えて、次のような大見出しを使っている。
米獣を衝く 暴戻と物量の敵を撃て
お題目で獣性偽装 野望達成で手段選ばぬ
泉県知事の談話なども記されているが、那覇市の各地で檄を飛ばしているのは軍人ではなく、民間団体の責任者である。
<挺身活動へ 翼壮団長会議
県翼賛壮年団では、各郡団長会議の結果、団の強化を図り下部組織へ浸透を促し活発な挺身活動を開始することとなり幹部並びに団員の整備、部落常会との渾然一体化などを確立することに報道網をはって志気昂揚に全力をそそぐことになり、・・・>(沖縄新報 昭和20年12月8日)
当時の決起大会に参加した人の話によると、興奮して演壇上で「抜刀して」県民を扇動していたのは軍人ではなく民間人であったという。
例えば座間味島の日本軍はこれに参加しておらず、那覇から帰島した村の三役から、那覇市での決起大会の状況を辛うじて知ることが出来たいう。
では、その頃、沖縄配備の第23軍は一体何をしていたのか。
■第32軍は県民疎開をどのように考えたか■
ウソも繰り返せば真実となり、根拠の無いスローガンも繰り返せば歴史となる。
連日沖縄の紙面で踊る、「日本軍は住民を守らない」
という左翼の主張は、昭和19年の夏から大本営と沖縄配備の第32軍が沖縄県民の安全を守るため、県や警察と協力し、県外疎開に必死の努力をしていたという歴史的事実には全く目をつぶった、「反日運動のために捏造されたスローガン」にすぎない。
戦時中といえども法律の下に行動する軍は、当時の日本の法の不備に悩まされていた。
日本は過去の戦争において常に戦場は国外であり、そのために昭和19年の第32軍沖縄配備の時点で、国民を強制的に疎開させる法律を備えていなかった。
ドイツやフランスのように国境が陸続きの大陸国では、戦争といえば国境を越えて侵入する敵軍を想定するが、四面を海に囲まれた海洋国家の日本では、敵の自国内侵入は海上での撃滅を想定しており、地上戦を考えた疎開に関する法律は整備されていなかった。
第32軍が沖縄に着任した昭和19年当時、
何と、戦時中であるにも関わらず当時の日本には、現在の平和な時代でも具備している「国民保護法」(平成16年6月18日 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)に相当する法整備がなされていなかったのである。
そのような状況で沖縄防衛を任される第32軍が沖縄着任に先立って最も憂慮したのは、米軍の上陸により沖縄住民が戦火に巻き込まれることであった。
■県民疎開は大本営の発想■
昭和19年7月1日、大本営の後宮参謀次長は、関東軍司令部から参謀本部付きとなっていた長勇少将を特命により沖縄に派遣した。 その特命の目的は食糧不足のための兵糧の研究が表向きであったが、その他にもう一つの重要な任務を命じられていた。
同じ年の8月10日に第32軍司令官、牛島満中将が沖縄に着任するが、その一月前の7月1日に沖縄に着任し、長少将が真っ先に行ったのが住民の県外疎開調査のための県内視察であった。
既に第32軍の参謀長を拝命していた長少将は、調査結果を第32軍司令官渡辺正夫中将(牛島司令官の前任)に報告し、司令官は陸軍省に県民の県外疎開について具申し、それを受けて7月7日に県民の県外疎開の閣議が決定される。
沖縄配備の第32軍は、長勇参謀長の沖縄着任(正式には昭和19年7月8日 )の一日前には、法整備の不備だった「県民の県外疎開」を着任前に閣議決定させるという素早い動きをしていたのだ。
大本営は米軍の沖縄上陸は必至と予測し、牛島満司令官着任の一ヶ月以上も前の昭和19年7月1日に長参謀長を沖縄に派遣したが、
これと連動した内務省防空総本部も救護課の川嶋三郎事務官を沖縄に派遣し、県民疎開の閣議決定の下準備をさせていたのだ。(「消えた沖縄」浦崎純著・1969年)
緊急閣議決定で法的根拠は得たが、第32軍の県外疎開の実施にはさまざまな困難が伴った。
今の時代で安易に想像し、軍が圧倒的権力で有無を言わせず県外疎開を命令し、実施したわけではなかった。
県民の県外疎開を管轄する政府機関は内務省防空総本部であった。
当時の法律では空襲に備えて県外疎開を強制することは防空法に規定があったが、
沖縄の場合のように地上戦に備えて非戦闘員を強制的に疎開させる法的権限は持っていなかったのだ。
当時の沖縄の状況は新聞の勇ましい扇動報道に乗せられた各民間団体の「軍人より軍人らしい民間人」の狂気が巷にあふれ、
県外疎開の必要性を説いても、それに真面目に耳を傾けるものは少数派で、県外疎開は卑怯者と後ろ指を指される有様だった。
県外疎開を民間人に直接命令する権限の無い第32軍は、民間人の安全を管轄する県に協力を求め、
県は警察の持つ組織力と機動力によることが最適と考え県外疎開の担当部署を警察部と定めた。
現在のような平和な時代の後知恵で、
「軍の命令は自分の親兄弟を殺害する」ほど圧倒的で不可避であったと「沖縄タイムス史観」は主張するが、
実際は軍隊は住民に直接命令をする権限を持たず、住民の安全を確保するための県外疎開にせも県や警察機構の協力を仰がなければ実行できなかったのである。
警察部長として県民の県内外の疎開に尽力し、最後は南部で戦死を遂げた荒井退造氏が、冒頭記事の荒井紀雄さん(写真)の父君である
 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします
「「「
 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします