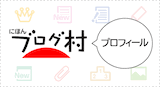昨日、東京都の新形コロナウイルス感染者は243名。
一昨日の過去最高をまたもや更新し、これは第2波どころか本山・メインディッシュなのではないかとさえ思います。

そんなタイミングで、録画していたNHK歴史秘話ヒストリア「ペスト最悪のパンデミック」を見ました。
すでに過去の病と思われている感染症・ペスト。それが14世紀のヨーロッパでは、死者がおよそ3000万人、人口の1/3が消えたといわれています。そのペストが世界を恐怖のどん底にたたき落として、最悪のパンデミックを引き起こした原因は「3密」「不要不急の移動」――いまや聞き慣れたこの2つだったそうです!
ペストの流行。正体不明の病に恐怖を覚えた人々はキリスト教の教会に集まってお祈りをしたそうです。これが「3密」です。ペスト菌の存在や感染原因などわからなかった時代ですから仕方ありません。またペストの感染地域(都市部)から逃げ出して農村へと向かう人々もあったそうです。それがまた感染の拡大を招いたそうです。これは「不要不急の移動」です。
そののち何回もペストの流行があって18世紀になると科学の進歩で検疫・患者の隔離、治療が行われるようになります。その治療にあたるペスト専門医がベネチアのカーニバルに出てきます。下の写真のようなスタイルです。このおどろおどろしい仮面のクチバシには感染を防ぐ効果があるとされたハーブや香料が詰め込んであり、いまでいうマスクやシールドにあたります。また黒いコスチュームも患者に密着しない防護服になります。このスタイルで手にした棒で診察するなど徹底していたそうです。

また衣類の洗濯・熱消毒も行われるようになったり、これらは経験や情報の蓄積によって得られたものです。またペスト菌が発見され、媒介する生き物、蚤やネズミの駆除とか消毒の効用が証明されたり、ペスト菌に打ち勝つ方法が確立されていきました。
ところが、7世紀後の現代でも「3密」「不要不急の移動」をするなと言っても、命知らずの方々がいるのですね。緊急事態宣言と営業自粛が解けた途端に・・・それから2~3週間たったら過去最高の感染者数を毎日更新してます。政府や東京都はPCR検査数が多くなったからとか面白い分析をしてますけれど、感染者のうち20代30代が過半数を占めるところから見てもやはり血の気が多い命知らずの方々が罹患されているのでしょうね。
ホストクラブ、キャバクラ、カラオケ喫茶など接待、大声を出す施設が寄与してるでしょうし、東京・埼玉・神奈川など人口密集地で多くなっています。昨日は野球やサッカーJリーグも観客を入れての試合を再開しましたから2週間後はどうなっているか非常に不安です。
PS.
今朝の新聞によりますと東京都の感染者のうちホストクラブやキャバクラの従業員や客といった夜の街関連の感染者が110人。新宿近辺のホストクラブの集団検査が6店舗で47人含まれているそうです。これらの特定業種店舗がかつての大阪のネズミと同じ媒介組織にあたるわけですから、当分営業禁止にせざるを得ないでしょう。
ただいまブログランキング アタック中です。
ワンクリック↓をお願い申し上げます。日々更新の励みになります。
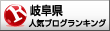
岐阜県ランキング<script src="https://blogparts.blogmura.com/js/parts_view.js" async></script>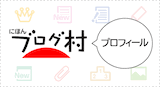
一昨日の過去最高をまたもや更新し、これは第2波どころか本山・メインディッシュなのではないかとさえ思います。

そんなタイミングで、録画していたNHK歴史秘話ヒストリア「ペスト最悪のパンデミック」を見ました。
すでに過去の病と思われている感染症・ペスト。それが14世紀のヨーロッパでは、死者がおよそ3000万人、人口の1/3が消えたといわれています。そのペストが世界を恐怖のどん底にたたき落として、最悪のパンデミックを引き起こした原因は「3密」「不要不急の移動」――いまや聞き慣れたこの2つだったそうです!
ペストの流行。正体不明の病に恐怖を覚えた人々はキリスト教の教会に集まってお祈りをしたそうです。これが「3密」です。ペスト菌の存在や感染原因などわからなかった時代ですから仕方ありません。またペストの感染地域(都市部)から逃げ出して農村へと向かう人々もあったそうです。それがまた感染の拡大を招いたそうです。これは「不要不急の移動」です。
そののち何回もペストの流行があって18世紀になると科学の進歩で検疫・患者の隔離、治療が行われるようになります。その治療にあたるペスト専門医がベネチアのカーニバルに出てきます。下の写真のようなスタイルです。このおどろおどろしい仮面のクチバシには感染を防ぐ効果があるとされたハーブや香料が詰め込んであり、いまでいうマスクやシールドにあたります。また黒いコスチュームも患者に密着しない防護服になります。このスタイルで手にした棒で診察するなど徹底していたそうです。

また衣類の洗濯・熱消毒も行われるようになったり、これらは経験や情報の蓄積によって得られたものです。またペスト菌が発見され、媒介する生き物、蚤やネズミの駆除とか消毒の効用が証明されたり、ペスト菌に打ち勝つ方法が確立されていきました。
ところが、7世紀後の現代でも「3密」「不要不急の移動」をするなと言っても、命知らずの方々がいるのですね。緊急事態宣言と営業自粛が解けた途端に・・・それから2~3週間たったら過去最高の感染者数を毎日更新してます。政府や東京都はPCR検査数が多くなったからとか面白い分析をしてますけれど、感染者のうち20代30代が過半数を占めるところから見てもやはり血の気が多い命知らずの方々が罹患されているのでしょうね。
ホストクラブ、キャバクラ、カラオケ喫茶など接待、大声を出す施設が寄与してるでしょうし、東京・埼玉・神奈川など人口密集地で多くなっています。昨日は野球やサッカーJリーグも観客を入れての試合を再開しましたから2週間後はどうなっているか非常に不安です。
PS.
今朝の新聞によりますと東京都の感染者のうちホストクラブやキャバクラの従業員や客といった夜の街関連の感染者が110人。新宿近辺のホストクラブの集団検査が6店舗で47人含まれているそうです。これらの特定業種店舗がかつての大阪のネズミと同じ媒介組織にあたるわけですから、当分営業禁止にせざるを得ないでしょう。
ただいまブログランキング アタック中です。
ワンクリック↓をお願い申し上げます。日々更新の励みになります。
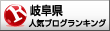
岐阜県ランキング<script src="https://blogparts.blogmura.com/js/parts_view.js" async></script>