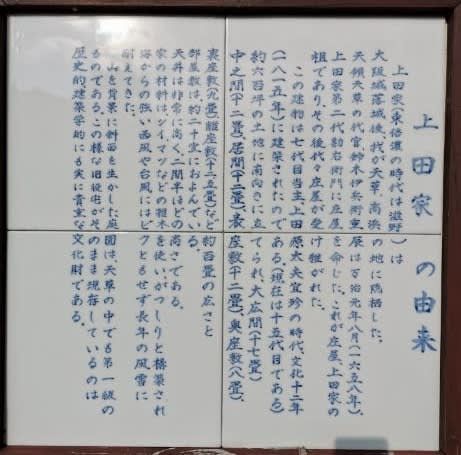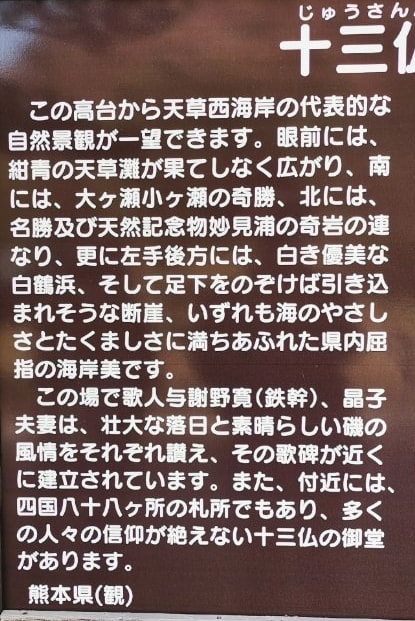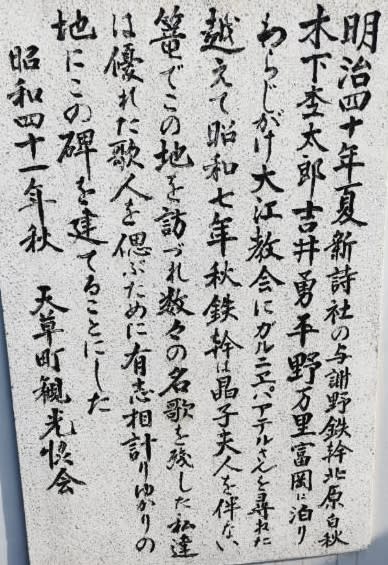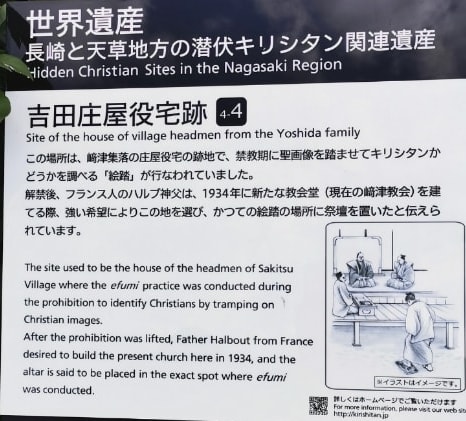いやいや面白かった。
この本も永久保存用に取り寄せようかしら??
最近「半沢直樹」の作者池井戸潤が昔勤めていた銀行の頭取に「半沢」氏が就任という話題がありましたね。この半沢氏は池井戸潤の同期だったらしく、優秀だったので小説の主人公の名前に借りたとのだとか。半沢直樹が実在したというわけではないようですが、小説の世界が現実世界と地続きになってるようで、ファンは楽しく盛り上がったことでしょう。
三菱UFJ銀頭取に半沢氏 13人抜き、常務から来春昇格―池井戸潤氏と同期 2020年12月22日21時49分(時事ドットコム)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が傘下の三菱UFJ銀行の次期頭取に、同行常務の半沢淳一氏(55)を昇格させる人事を固めたことが22日、分かった。同行で常務から頭取に就任するのは初めてで、副頭取など計13人抜きとなる。MUFGの指名・ガバナンス委員会の承認を得て、来年4月に就任する。
半沢氏は1988年に三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行し、人気ドラマ「半沢直樹」の原作者である池井戸潤氏とは同期。(後略)
さて、シャーロック・ホームズが架空の人物であるように、半七捕物帳の半七親分も岡本綺堂の創作だと思っていたのですが、どうやらそうでもないらしい。
半七親分にもモデルがいたそうです。
いや、モデルどころではない、実際に綺堂は半七親分(のモデルの人)から聞いた話を元に小説を書いたらしいのです。
明治の半七老人が赤坂に住んでるというのは創作らしいですが。おそらく綺堂が執筆した当時はゆかりの人がまだいて、個人が特定されるのがよろしくないと考えたのかもしれません。
明治の半七老人は赤坂でなく大久保に住んでいたようです。(その大久保の住まいの様子は半七老人の友人である三浦老人の住まいとして「三浦老人昔話」の方で語られています。)
綺堂も「モデルはいるのか実在の人物なのか?」と散々聞かれたらしく、自らちゃんと文章を残しています。ちょっと長いですが引用しておきます。(青空文庫から持ってきました)
半七招介状
岡本綺堂
明治二十四年四月第二日曜日、若い新聞記者が浅草公園弁天山の惣菜(岡田)へ午飯を食いにはいった。花盛りの日曜日であるから、混雑は云うまでも無い。客と客とが押し合うほどに混み合っていた。
その記者の隣りに膳をならべているのは、六十前後の、見るから元気のよい老人であった。なにしろ客が立て込んでいるので、女中が時どきにお待遠さまの挨拶をして行くだけで、注文の料理はなかなか運ばれて来こない。記者は酒を飲まない。隣りの老人は一本の徳利を前に置いているが、これも深くは飲まないとみえて、退屈しのぎに猪口をなめている形である。
花どきであるから他のお客様はみな景気がいい。酔っている男、笑っている女、賑やかを通り越して騒々しい位であるが、そのなかで酒も飲まず、しかも独りぼっちの若い記者は唯ぼんやりと坐っているのである。隣りの老人にも連れはない。注文の料理を待っているあいだに、老人は記者に話しかけた。
「どうも賑やかですね。」
「賑やかです。きょうは日曜で天気もよし、花も盛りですから。」と、記者は答えた。
「あなたは酒を飲みませんか。」
「飲みません。」
「わたくしも若いときには少し飲みましたが、年を取っては一向いっこういけません。この徳利も退屈しのぎに列べてあるだけで……。」
「ふだんはともあれ、花見の時に下戸はいけませんね。」
「そうかも知れません。」と、老人は笑った。
「だが、芝居でも御覧なさい。花見の場で酔っ払っているような奴は、大抵お腰元なんぞに嫌われる敵役で、白塗りの色男はみんな素面ですよ。あなたなんぞも二枚目だから、顔を赤くしていないんでしょう。あははははは。」
こんなことから話はほぐれて、隣り同士が心安くなった。老人がむかしの浅草の話などを始めた。老人は痩やせぎすの中背ちゅうぜいで、小粋な風采といい、流暢な江戸弁といい、紛れもない下町の人種である。その頃には、こういう老人がしばしば見受けられた。
「お住居は下町ですか。」と、記者は訊きいた。
「いえ、新宿の先で……。以前は神田に住んでいましたが、十四五年前から山の手の場末へ引っ込んでしまいまして……。馬子唄で幕を明けるようになっちゃあ、江戸っ子も型なしです。」と、老人はまた笑った。
だんだん話しているうちに、この老人は文政六年未年の生まれで、ことし六十九歳であるというのを知って、記者はその若いのに驚かされた。
「いえ、若くもありませんよ。」と、老人は云った。「なにしろ若い時分から体に無理をしているので、年を取るとがっくり弱ります。もう意気地はありません。でも、まあ仕合せに、口と足だけは達者で、杖も突かずに山の手から観音さままで御参詣に出て来られます。などと云うと、観音さまの罰が中る。御参詣は附けたりで、実はわたくしもお花見の方ですからね。」
話しながら飯を食って、ふたりは一緒にここを出ると、老人はうららかな空をみあげた。
「ああ、いい天気だ。こんな花見日和は珍らしい。わたくしはこれから向島へ廻ろうと思うのですが、御迷惑でなければ一緒にお出でになりませんか。たまには年寄りのお附合いもするものですよ。」
「はあ、お供しましょう。」
二人は吾妻橋あづまばしを渡って向島へゆくと、ここもおびただしい人出である。その混雑をくぐって、二人は話しながら歩いた。自分はたんとも食わないのであるが、若い道連れに奢ってくれる積りらしく、老人は言問団子に休んで茶を飲んだ。この老人はまったく足が達者で、記者はとうとう梅若まで連れて行かれた。
「どうです、くたびれましたか。年寄りのお供は余計にくたびれるもので、わたしも若いときに覚えがありますよ。」
長い堤を引返して、二人は元の浅草へ出ると、老人は辞退する道連れを誘って、奴うなぎの二階へあがった。蒲焼で夕飯を食ってここを出ると、広小路の春の灯は薄い靄もやのなかに沈んでいた。
「さあ、入相がボーンと来る。これからがあなたがたの世界でしょう。年寄りはここでお別れ申します。」
「いいえ、わたしも真直まっすぐに帰ります。」
老人の家は新宿のはずれである。記者の家も麹町である。同じ方角へ帰る二人は、門跡前から相乗りの人力車に乗った。車の上でも話しながら帰って、記者は半蔵門のあたりで老人に別れた。
言問では団子の馳走になり、奴では鰻の馳走になり、帰りの車代も老人に払わせたのであるから、若い記者はそのままでは済まされないと思って、次の日曜に心ばかりの手みやげを持って老人をたずねた。その家のありかは、新宿といってもやがて淀橋に近いところで、その頃はまったくの田舎であった。先日聞いておいた番地をたよりに、尋ねたずねて行き着くと、庭は相当に広いが、四間ばかりの小さな家に、老人は老婢と二人で閑静に暮らしているのであった。
「やあ、よくおいでなすった。こんな処は堀の内のお祖師さまへでも行く時のほかは、あんまり用のない所で……。」と、老人は喜んで記者を迎えてくれた。
それが縁となって、記者はしばしばこの老人の家を尋ねることになった。老人は若い記者にむかって、いろいろのむかし話を語った。老人は江戸以来、神田に久しく住んでいたが、女房に死に別れてからここに引込んだのであるという。養子が横浜で売込商のようなことをやっているので、その仕送りで気楽に暮らしているらしい。江戸時代には建具屋を商売にしていたと、自分では説明していたが、その過去に就いては多く語らなかった。
老人の友達のうちに町奉行所の捕方すなわち岡っ引の一人があったので、それからいろいろの捕物の話を聞かされたと云うのである。
「これは受け売りですよ。」
こう断わって、老人は「半七捕物帳」の材料を幾つも話して聞かせた。若い記者はいちいちそれを手帳に書き留めた。――ここまで語れば大抵判るであろうが、その記者はわたしである。但し、老人の本名は半七ではない。
老人の話が果たして受け売りか、あるいは他人に托して自己を語っているのか、おそらく後者であるらしく想像されたが、彼はあくまでも受け売りを主張していた。老人は八十二歳の長命で、明治三十七年の秋に世を去った。その当時、わたしは日露戦争の従軍新聞記者として満洲に出征していたので、帰京の後にその訃ふを知ったのは残念であった。
「半七捕物帳」の半七老人は実在の人物であるか無いかという質問に、わたしはしばしば出逢うのであるが、有るとも無いとも判然と答え得ないの右の事情に因るのである。前にも云う通り、かの老人の話が果たして受け売りであれば、半七のモデルは他にある筈である。もし彼が本人であるならば、半七は実在の人物であるとも云い得る。いずれにしても、わたしはかの老人をモデルにして半七を書いている。住所その他は私の都合で勝手に変更した。
但し「捕物帳」のストーリー全部が、かの老人の口から語られたのではない。他の人々から聞かされた話もまじっている。その話し手をいちいち紹介してはいられないから、ここでは半七のモデルとなった老人を紹介するにとどめて置く。(昭和11・8「サンデー毎日」)
面白いですね~!
半七捕物帳を読んだことがある方なら、この記者と老人のやり取りはまさに小説そのままだと気が付かれると思います。(というか、この浅草から向島への花見の話も小説の中に確かありましたよね)
私が特に面白いなぁと思うのは、半七捕物帳の第一作「お文の魂」に登場する「Kのおじさん」のことです。この「Kのおじさん」が実在の人物で16歳の綺堂に「お文の魂」を話したのなら、綺堂は16歳のときに聞いた話の人物に20代半ばで出会って親しくなっているのです。そんな偶然あるのかしら??いくら今より人口が少ないとは言っても?
で、この本ですが、
この本の著者は半七親分は実在の人物で、場所などの設定は変えてあるものの、毎回話の導入部分に出てくる明治の話も事実であったと考えています。そして、半七の一生をできるだけ正確にたどって年表もつくってます。話に出てくる街の様子から、その日の歩いた道順はどうだったかとか、「停車場」とだけ書いてあるのは何駅だとか、注釈本を作る勢いで事細かに調べつくし、推理しつくしています。
シャーロック・ホームズならシャーロキアンとかホームジアンと言われる研究者がいますが、こらはまさに「ハンシチアン」の研究成果。著者自身も戦前の神田の生まれで、思い入れも深いのでしょう。
私も半七親分の神田三河町の家のあたりを歩いてみようと、鎌倉河岸のあたりを歩いたことがあります。その頃はまだ親分が実在だなんて知らなかったので、洒落のつもりでしたが、また行ってみたいと思います。
子どものころからシャーロック・ホームズが好きな私は、ロンドンベーカー街へも行きましたが、やはり架空の人物とわかっているので221bがどこだったかとか真剣に考えようとは思いません。が、半七はちがいます。名前こそ「半七」ではなかったものの、実在の人物で、きっと子孫もどこかにいるでしょう、ひょっとすると先祖がかの有名な半七親分だとは知らずにいるのかもしれません。そんなことも想像すると、また一段と楽しくなります。
半七ブームが起きてほしいなぁ。
そして映像作品も良質なのがどんどんできてほしいです。
ホームズでいうところの「グラナダTVシリーズ」のような、原作に忠実な作品を見てみたいです。



























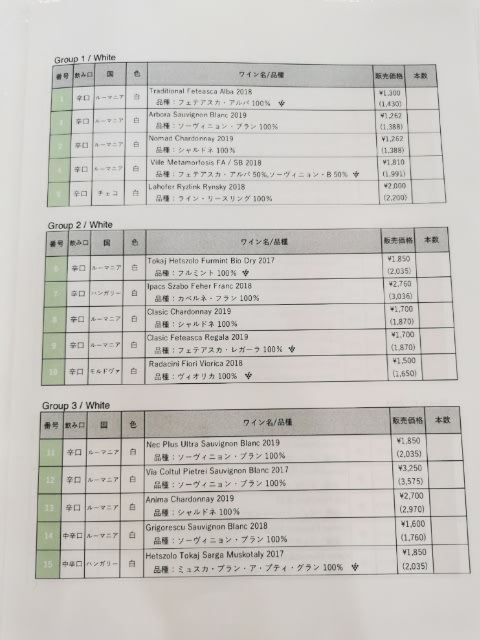
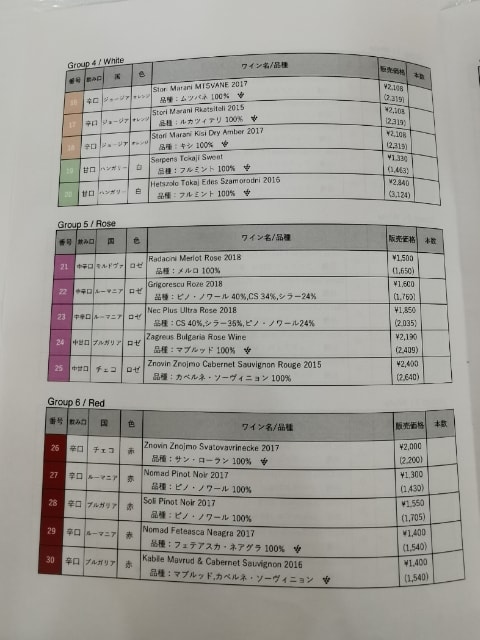
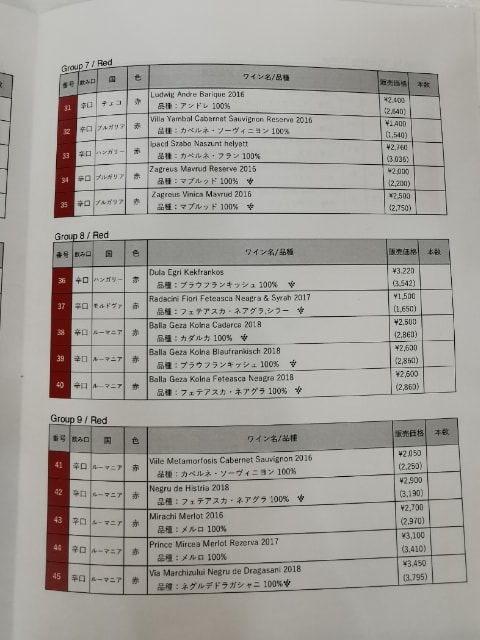
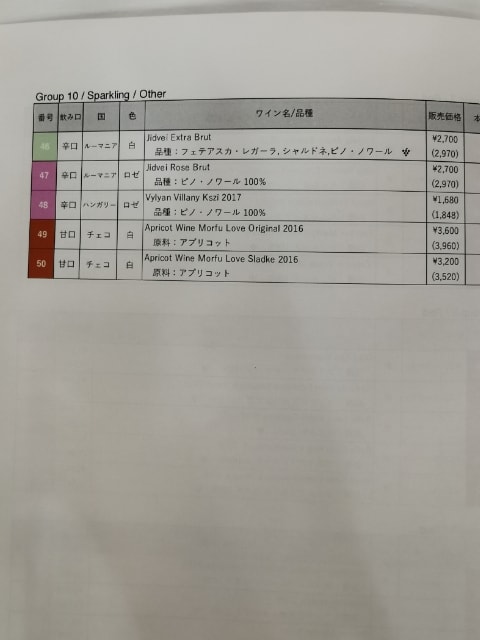















![エヴェレスト 神々の山嶺 通常版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61DK1QbDkLL._SL160_.jpg)