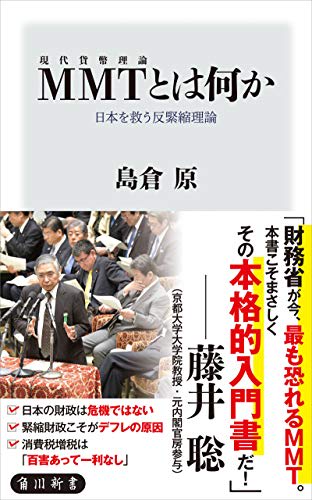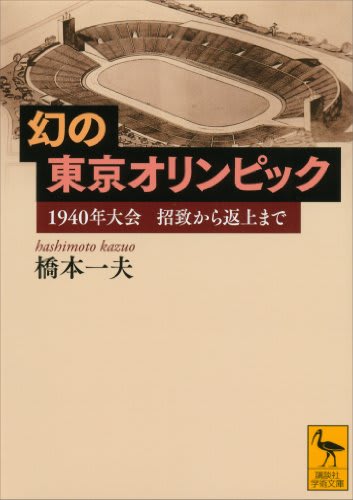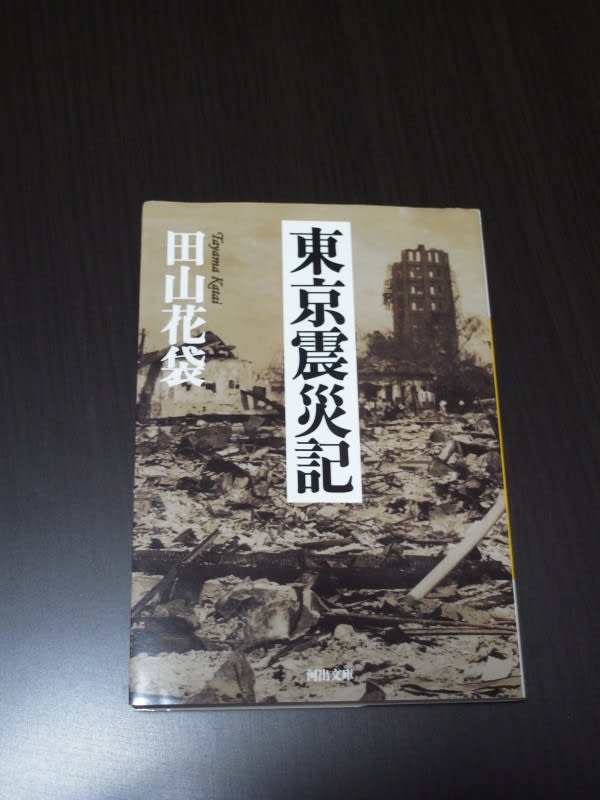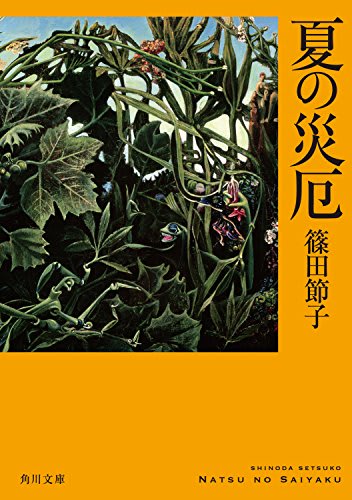夏から秋にかけて、再読をはじめた本がふたつある。ひとつは「独ソ戦」で、ここに書いた。
もうひとつは村上春樹の「1Q84」だ。
どちらも、今年の世相が再読のきっかけとなっているところが似ている。
この本は7年前に一度感想を書いている。
さらにその4年前にも、なにか書こうとして中途半端になってしまったらしい。
独ソ戦が今日的世相に照らして、何がきっかけかはすぐわかるとおもうが、「1Q84」は何かというと、この小説の主人公(青豆、女性)が宗教二世である、という点だ。家族全員が入信しており、兄はのちにその教団に勤務するようになる。小学校の行事に出られなかったり、給食の時にお祈りを唱えたり(することを強要された)したため、学校内で孤立する。最終的に彼女は家族と縁を切り、物語が始まるころにはスポーツジムのインストラクターをしている。
もう一人の主人公、天吾に宗教的な背景はない。彼はNHKの集金人である父のもと、男手ひとりで育てられた。父は仕事熱心だがやや偏屈なところがあり、休日には息子を連れまわして払いの悪い家などを集金して回っていた。
当然子供たちからは特殊な目で見られるが、天吾は体格もよく、成績もよかったためいじめの対象にはならなかった。
この二人は小学校の同級生であり、お互いの特殊な環境からか、どこかで惹かれ合うものを持っていたのだろう。ある日、のちに二人とも相手を想うときに必ず思い出す、印象的な出来事が起きる。
そのあとすぐ、二人は離れ離れになる。
物語が始まる時点で天吾は、予備校の数学の講師をしながら小説を書いている。そして、ふとしたきっかけで文学賞に応募した女子高生とかかわることになる。
この女子高生、ふかえりもまた、宗教二世である。父は教団のトップを務めている。
そして、ふかえりも家族と、その家族の属する組織から逃れてきた。
ここまで書くと、この物語は(読んでない人から見ると)宗教二世がその桎梏から逃れる物語か、と思うかもしれないが、もちろん単純にそういう建付けにはなってはいない。
村上春樹はここでいくつかの違ったセクターが、本来保護されるべき幼子たちを不可避的に押さえつけ、苦しめている姿を描き出している。
いわゆる新興の、厳格な教義を持つ宗教団体、全共闘世代が作り上げたコミューン(宗教的色彩を帯びているが、どちらかというとヒッピー文化の変形したものという要素が強いように思える)、そしてゆがんだ権威主義。
さいごのゆがんだ権威主義は、本来は父と子の関係性を示すものだが、村上氏はなぜかその権威のおおもとを’NHK’に据えて、これを親子間の関係から拡大させている。集金人の亡霊(のようなもの)は、大人になった天吾(ふかえり)、青豆、それを追う牛河を脅しつける。
だしに使われたNHKもいい迷惑だと思うが。。村上氏はNHKが、たぶんお好きなようで(その点は例のワン・イシューの政党とはちがう)、「ねじまき鳥」でも常にNHKを大音量で見ている本田さんとか、しばしば出てくるFMのクラシック番組(本作の冒頭でもタクシーの車内でヤナーチェクが流れていた)は間違いなくNHK FMの番組だ。
家庭を訪問して受信料を徴収するのはNHKしかない(Netflixの集金人というのはいない)から、集金人のシーンはNHKとなるのも道理なのかもしれないが、明らかに自民党員のはずの綿谷昇(「ねじまき鳥」の)の所属政党は保守党となっていたよなあ、とか、思ったりするん、だがなあ。実名で出すか。。
話を戻すと、本作の主人公たちはそうした強い権利からの桎梏から、形の上ではすでに逃れることに成功している。そこから逃れること自体は、村上氏にとっては主題たりえないらしい。ただ、少なくとも青豆、たぶん天吾も、心のどこかではその傷を克服しきれていないように思える。
物語的にはいちおう、第3部の最後にはハッピーエンド的な展開にはなるのだけど、どうもすっきりしない感じは残るのだよな。。
2,3よけいなこといいます・。
ときどきここでも書いているけど、僕は天吾はどうも苦手だ。
この人は村上作品には珍しく、自分の存在にあまり疑念を持つようなものの考え方はしない。それは良いのだが、周りの人に対する反応がとても鈍い(意図的な描写なのだと思うが)。
年上の人妻と付き合っていたが(ほぼ性的な面においてのみ)、あるときその関係が失われる。この女性の夫から天吾に、直接電話がかかってくる。夫は女性に何が起きたのか、はっきりとは言わない。天吾は、何が起きたのか繰り返し確認しようとして夫に遮られる。そのあとも天吾は、自分と女性の関係性以外のことには思いを巡らせることはない。女性の夫がいかに傷ついているのか、自分の行為が彼女の周辺にどういう影響を与えていたのか、そういう認識が見られない。
その鈍さは、彼を取り巻く女性、ふかえり、安達クミ(父の入院していた病院の看護師)、青豆との関係性においても変わらないように思える。小学校の先生もそうか。ただ、女性たちから見ると、その鈍さはあまり気にならないらしい。
この人は予備校の講師かつ作家(志望)だし、身寄りもないので、そうした人間関係でもまれることはなかったのだろう。それでもたぶん、もししばらく一緒に仕事をすることになったら、僕は嫌な奴だと思うようになりそうだ。
牛河という人が出てくる。切れ者のもと弁護士で、教団に乞われて青豆の足跡を追っている。頭脳は鋭いが外見は極めて醜く、彼も社会に強い疎外感を持っている。自然と社会の底辺をさまようような仕事をせざるを得なくなった、という設定だ。
これも前に書いたが、同名の牛河として「ねじまき鳥」に出てくる人物と、外見や役割は似ているが境遇(の設定)は少し違う。ねじまき鳥の牛河はある意味自然な底辺者だが、1Q84の牛河はインテリだ。その結果かどうか、描写に彼の外見の醜さが繰り返し描かれていて、そこがどうも引っかかる。
天吾を追う牛河は、天吾の小学校時代の教師に2名会う。村上氏はここでも二人の教師(どちらも年配の女性)の外見、美醜に言及している。
この、外見の美醜に関する奇妙なこだわり(醜さ=悪とまで言い切りはしないが、背後にそういう思想が感じられること)と、料理に関する描写(たぶん村上氏自身にこだわりがあるー喫茶店を経営してらしたからーせいか、時に奇妙に一面的で、料理があまりおいしそうに思えない)、お酒に関する描写(酒が弱い人の気持ちがわからないのか、登場人物がやたらと飲みまくる)は、村上春樹氏の作品の、なんというか引っかかるところだ。
ファンはそれをひっくるめて村上作品として受け入れているんだとは思うけど、ちょっとね、覚めるんですよね。やたらとあれしまくる、っていうのは、巷間言われているし、それは本人も認めている(「村上さんのところ」)けど、上記の点はあまり指摘をみないので、いちおう。















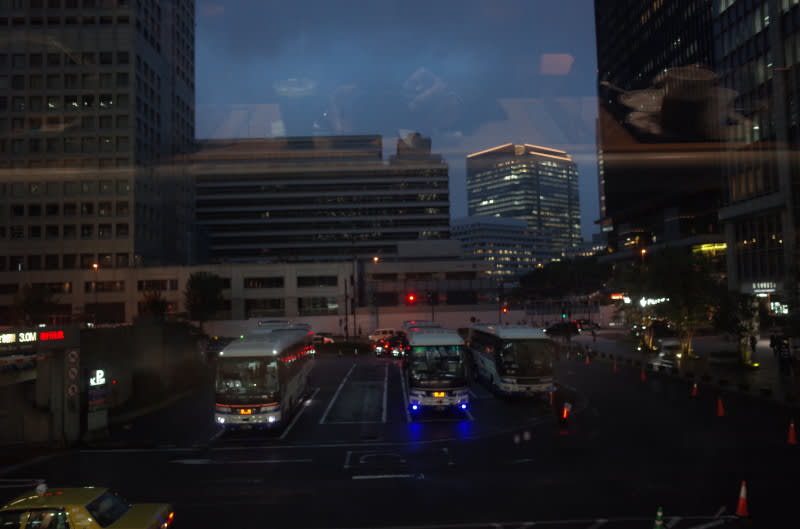
 きょうは選挙で、テレビも夜はずっとそれをやっているようですから、こちらは少し静かにどくしょのおはなしを。
きょうは選挙で、テレビも夜はずっとそれをやっているようですから、こちらは少し静かにどくしょのおはなしを。