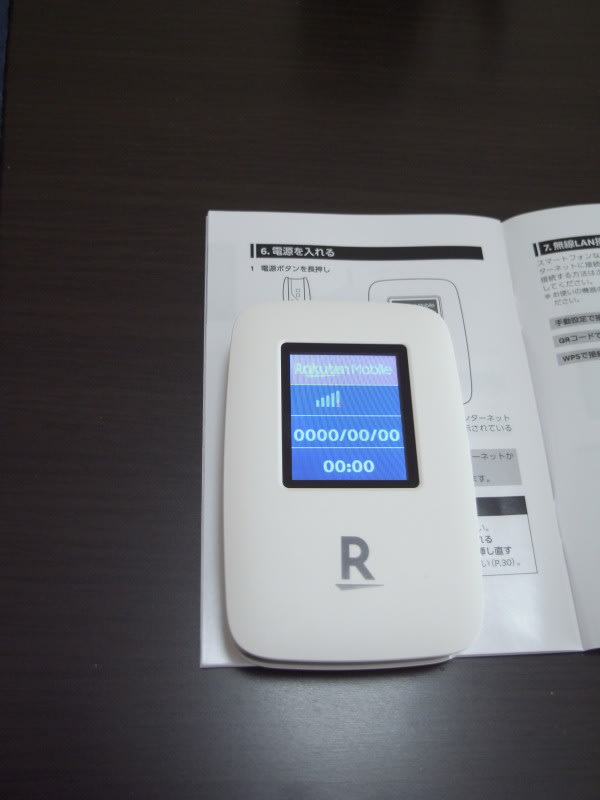渡辺恒雄 新潮新書2020
著者自身が言及しているが、もともとはトランプ政権4年間のことを概観する内容で書かれたものを、世界全体(秩序)まで視点を広げてまとめられたものである。なので、基本的にはアメリカ政治、特に前政権(第45代大統領)に関する考察が中心といってよい。
その第45代大統領が2016年に選挙に勝ったことを、予想できなかった反省から本書は執筆されたのだという。
これ(トランプ現象)は米国内だけではなく現在の世界で起きている、大きな変化の一つであり、その変化は冷戦やベトナム戦争の時代に揺れ動いていたアメリカ社会よりも、むしろイギリスが第二次大戦を経て新興国アメリカに派遣を譲ったときのようなダイナミズムに近い、としている。
本書のあとがきを見ると2020年11月とあるので、ちょうど選挙が終わり、しかしトランプ大統領が敗北を認めていない、という時点であったようだ。そのあと12月に選挙人による投票があり、更にその一月後には議会乱入の事件が起きた。そのまた一月後、元大統領の2回目の弾劾裁判が行われた。
弾劾裁判が早期に決着したように、どうもアメリカ社会(あるいは世界全体もか)は過去の4年間のことを早く忘れようとしているようにも思える。あれほど毎日ニュースを騒がせていた大統領とその支持者たちの姿も、今は見ることはない。ネットでは時折でてくるが、SNSのニュースサイトに掲げられるコメントの風潮も変化した。
しかし、忘れてしまって良いわけではないし、起きてしまったことを取り消すこともできない。もう10年か15年ぐらいしたら、だれか力量のあるジャーナリストが1000ページぐらいの大著をまとめてくれそうな気がする。が、本書も今の時点でのまとめとしては非常に良く書けていると思う。
前政権についてはかなり批判的だ。とりわけ外交上の政策失敗については厳しく追及している。中東問題と、それをめぐる欧州との隙間風、ベネズエラ政変をめぐる失敗、米中新冷戦、ロシアとの核軍縮の行き詰まり、北朝鮮、シリア、イラン、リビア、パレスチナ(イスラエル)、枚挙にいとまがない。
外交上の失敗は、ある意味大統領の職務としては避けられないものなのかもしれない。
しかし、在任期間中に行った数多くの権力乱用や問題行動、言動は常軌を逸している。
- 2017年5月、トランプ大統領はジェームズ・コミ―FBI長官を解任した。一部の憶測では16年の大統領選におけるロシア介入(ロシアゲート疑惑。ロシア諜報機関がトランプ氏が有利になるように水面下で選挙に介入した)についてのFBI操作を止めさせるため、大統領が圧力をかけたが、長官が拒否したためだとしている。
退任後出版した著書の中でコミ―氏は、トランプ大統領が頻繁にコミ―氏を食事に誘い、自身への忠誠心を確認してきたという。
コミ―氏は自身が検察官時代に扱ったニューヨークのマフィアのの事件で得た経験から、トランプ氏の論理はマフィアと同じだ、と断じている。 - 他方、偽証の罪で起訴されたマイケル・フリン補佐官は、トランプ氏の度重なる圧力により起訴が取り下げられた。これには流石に批判が相次いだが、最終的に大統領選挙後の11月25日になって、トランプ大統領はフリン氏に恩赦を与えた。
- 白人警察官が黒人被疑者を死亡させた事件に端を発した抗議行動に対し、トランプ氏は平和的なデモ参加者を排除させて教会の前で記念撮影を行った。マティス元国防長官は「ドナルド・トランプは私が人生で見た中で初めての、アメリカ国民を一つにしようとしない大統領だ。そのふりすら見せない。代わりに我々を分断させようとしている」と激しく非難した。
抗議活動は一部で暴動に発展したが、これに対し連邦軍の出動を示唆した大統領に対し、マーク・エスパー国防長官は拒否の姿勢を示し、エスパー長官は解任された。
自分の敵か味方かを峻別したがり、味方には徹底的な忠誠心を求める一方、敵には容赦ない攻撃を仕掛ける。こうした論理をマフィアと同じだと論じたコミ―氏の言葉が印象的だった。
ただ、トランプ氏の人物評としてはこれだけでは不十分に思えることも確かだ。外部から見たら狂信的としか言いようのない「支持者」たちが自費でワシントンまで駆けつけて、挙句の果てに議会に乱入までする、という事態を十分説明はできない。
本書ではアメリカにおけるポピュリズムの歴史について言及し、更に反知性主義についても触れている。
よく、戦前の日本は根拠に乏しい精神論を振りかざし、物理的合理性を欠いていたが、アメリカは合理性を重んじ、科学的なアプローチで戦争を戦った、と語られてきた。
もちろん一面ではそれは真実なのだが、他方、一部のアメリカ人の間では極端に聖書に拘る人たちがいる(福音主義者)ことも事実だ。進化論論争などが典型だ。その意味ではアメリカはとてもおかしな国なのだ(個人的な意見としては、人間はだれしもどこかしら変なのだ。日本だけおかしいということもないし、何もかも公平で理想的な国や国民というのもいない)。
それはともかく、本書の指摘「欧州では啓蒙主義の時代に、信仰と科学に折り合いをつけたが、聖書を文字通り信じようとする福音主義者のピューリタンは、自分たちの進行を追求するために欧州からアメリカ大陸に移住した。(”地球温暖化は「たわごと」”)」という言葉は印象に残った。
調査によると今のアメリカで多少なりとも現実に基づいた判断をしている人は3分の1にとどまり、3分の2は「天使や悪魔がこの世界で活躍している」と信じている(本書より)、のだそう。
以下は個人の見解だ。アメリカ人にはヘンなところがあるが、日本人も普通にヘンだったし、いまもそうかもしれない。戦前のドイツは理想的な憲法を作りながら、ヒトラーの台頭を妨げられなかった。繰り返しになるが、人というのはそんなにいつも正しいことをするわけではないのだ。
ヒトラーは(基本的には)暴力ではなく合法的な政治活動で政権を掌握した。貴族でもテクノクラートでもなかった彼に、疑念を抱く人も多かったが、多くの人は一度彼と会って語りあうと、すっかり魅了されてしまったのだという。
ある種の人間にはそういうものが備わっている。
我々は日常的にオーラとか、カリスマとかいうけれど、本当にそういうものを備え持っている人は滅多にいない。トランプ氏にはたしかにそれがあったのだろう。もちろんヒトラーとトランプ氏を同列に並べるのは適切ではない。しかしとにかく(議事堂は襲撃されてしまったけど)、致命的な道を歩む前にアメリカは方向転換を図ることができた、といえるのかもしれない。