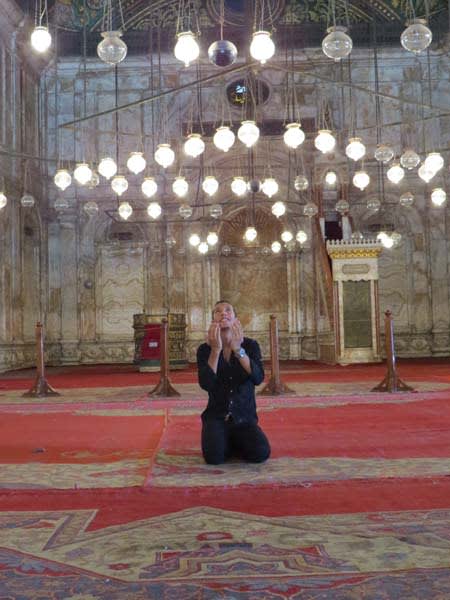九月の歌ですが、まずは 貫之さま
 から^^v
から^^vながつきのつごもりの日、大井にてよめる 紀貫之
夕月夜小倉の山に鳴く鹿の 声の内にや秋は暮るらむ
古今和歌集 312
これさだのみこの家の歌合せのうた 読人知らず
奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の 声聞く時ぞ秋はかなしき
古今和歌集 215
十月中旬
奈良公園には仲良し鹿さんがいっぱいいました。

毛繕いしてもらっているのかな?

仲がいいな☆

鹿曰く
「ねぇ。恥ずかしいから、こっち見ないでくれない?」
「ほんと、人間って、やぁね! 写真撮らないでくださらないこと?」
あらま! かんにんどすえ

あらま! かんにんどすえの後は、
アラマタ!カンニンドスエ

こんな写真で、ほんまに かんにんしとくれやす


ただいま牡鹿はキーンきーんと鳴いてパートナーを捜しています。
あちらでも、こちらでも、18K?どすえ。



みなさま、おつきあい下さいまして、ありがとうございます。
感謝感謝デス(*^-^*)

散歩中、美男をみた

といっても、植物の美男葛
ツルに愛くるしい実
まだ真っ赤に染まっていない美しい実は、一般的には「サネカズラ」というそうだ。
秋も深まれば、真っ赤な色に頬を染めるのだろう…
「サネカズラ」が「美男葛(ビナンカズラ)」という別名を持つ理由は、昔つるから粘液をとって整髪料に使ったためたとか。

古歌にもしばしば「さねかづら」「さなかづら」として詠まれ、「さ寝」の掛詞として使われる。
名にし負はば 逢坂山のさねかづら 人に知られで くるよしもがな
(藤原定方、百人一首25/後撰和歌集)

藤原定方
藤原 定方(ふじわら の さだかた、貞観15年(873年) - 承平2年8月4日(932年9月11日))は、平安時代前期から中期にかけての公家・歌人。内大臣藤原高藤の次男。醍醐天皇の外叔父。官位は従二位・右大臣、贈従一位。三条右大臣と号す。
和歌・管絃をよくし、紀貫之

 凡河内躬恒の後援者であった。
凡河内躬恒の後援者であった。『古今和歌集』(1首)以下の勅撰和歌集に13首入集。家集に『三条右大臣集』がある。
古今和歌集
秋ならで あふことかたき 女郎花 天の河原に おひぬものゆゑ
小倉百人一首
25番 名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな(「後撰和歌集」恋三701)

データーはウィキペディアより引用させて頂きました。
単位というものは、まこと難しいものでございます。
下(林英夫監修『基礎 古文書のよみかた』)を参考にいたしまして、古い資料に出てまいりました斗(と)の前の文字が石(こく)と判明いたしました。

八百八拾壱石八斗七分…
弐百七拾三石七斗三分三尺
斗(と)の前は石(こく) のようです。
加えて
古い文字で記された【ト】の縦長は【分】という文字です。
斗(と)の前は石(こく)
とのまえはこく
殿前は酷
殿前は酷
あぁれぇ~ はずかしぃ はずかしわぃのぅ~
かのお方は、【トの』】にあられまするぞ!【分】をわきまえよ。
あいのぅ。ううううう~
…朝からすみませんです

と、謝る乱鳥

林英夫監修『基礎 古文書のよみかた』参考▼
度(尺度・里程)
丈(じょう)・尺(しゃく)・寸(すん)・分(ぶ)・厘(りん) 十進法
中世以降、曲尺(かねざし)が基準(呉服尺・鯨尺・享保尺・文木(文尺)などもある)
明治八(1875)年に曲尺一尺=30.303センチ
里程
里(り)・町(ちょう)・間(けん)
一間は曲尺の六尺が基本となります。

量(容積)
量
石(こく)・斗(と)・升(しょう)・合(ごう)・勺(しゃく 尺)・才(さい)・弗(ふつ) 十進法
中世では、荘園領主や寺社ごとに個々の量制が用いらる。
豊臣秀吉により 京桝に統一される。

衡(重さ)
古代の令制以前から斤(きん)・両(りょう)・分(ぶ)・銖(しゅ)の制がある。
近世でも茶や生糸などに用いられた。
一斤を茶では四百匁、生糸では百六十匁とする。
重さを計る単位
貫(かん)・匁(もんめ)・分(ふん)・厘(りん)

面積
町(ちょう)・反(段)(たん)・畝(せ)・歩(分)(ぶ)
太閤検地以降は一反=三百歩。一
歩は一坪もいい、曲尺の六尺×六尺

度(長さ・里程)
1丈(じょう)=10尺(しゃく) 1尺=10寸(すん) 1寸=10分(ぶ) 1分=10厘(りん)
曲尺(かねざし)1尺=30.303cm 鯨尺(くじらじゃく)1尺=37.8cm
1里(り)=36町(ちょう)=3927.2688m 1町=60間(けん)=109.0908m 1間=曲尺6尺=1.818m

量(容積)
1石(こく)=10斗(と) 1斗=10升(しょう) 1升=10合(ごう) 1合=10勺(しゃく) 1勺=10才(さい) 1才=10弗(ふつ)
寛文9年(1669)以降 1升=1.80391リットル
「夕」は「勺」(「しゃく」「せき」)と読む。

衡(斤両銖及び重さ)
1斤(きん)=16両(りょう) 1両=4分(ぶ) 1分=6銖(しゅ)
明治8年(1875)以降 1銖=1.6g
1貫(かん)=1000匁(もんめ)=3.75kg 1匁=10分(ぶ) 1分=10厘(りん)

面積(広さ)
1町(ちょう)=10反(たん)(段)*1町=1ha 1反=10畝(せ)*1反=10a 1畝=30歩(ぶ)(分)
(写真は 歌川国貞)
22日から
この絵と 七代目 中村芝翫丈 が気になって仕方が無い。
なぜでしょう?なぜかしら?
それは…(泣)
七代目 中村芝翫丈から考えて
橋之助さんは ご子息で、七之助さんは お孫さん
お二方共にそれぞれ個性があり無くてはならない役者さん
このお二人の名前を早口言葉で言うと結構難しい。
七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助…
試しに【七之助橋之助】の十編唱えてみて。
天ぷら食べても、わたくしには無理。
難なく言える方は、お知らせ下さい。
今年も あと 99日
充実の【瞬間】をつなぎ合わせて、来年につなげたい☆
22日から
この絵と 七代目 中村芝翫丈 が気になって仕方が無い。
なぜでしょう?なぜかしら?
それは…(泣)
七代目 中村芝翫丈から考えて
橋之助さんは ご子息で、七之助さんは お孫さん
お二方共にそれぞれ個性があり無くてはならない役者さん
このお二人の名前を早口言葉で言うと結構難しい。
七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助七之助橋之助…
試しに【七之助橋之助】の十編唱えてみて。
天ぷら食べても、わたくしには無理。
難なく言える方は、お知らせ下さい。
今年も あと 99日
充実の【瞬間】をつなぎ合わせて、来年につなげたい☆
如何様
だから、【如何様】だってば!
それを…
いったい、だぁれ?
回答に【如阿様】って書いたのは…
だって、如来さまと阿弥陀さまだって思ったんだもの
それに,お寺の話だったんだもん!
この前、【如】って調べてたじゃない?
【如法】 (にょほう) のとこでさぁ~
【如】【如】【如】
ウーン
【如】がわかってんだからさぁ、辞書で調べなよ。
ウーン
ほうら!
『古文書 解読字典』(林秀夫)&『くずし字用例辞典』(児玉幸太 編)に【如何】っていぱい載ってるじゃん
如何
如何様
いかよう!!だけど
あはは
いかさま
いかさかさま
さかさま
あべこべ
あべこうぼう

やったー! 大好き☆
安部公房

と
内心
自分へ問いかけ、ひとりごとが続く☆
如法 (にょほう)
古○書にはよくある「一札如件」(いっさつくだんのごとし)
一週間前には読み終えていたが、わからない箇所はどちらにしてもわからない。
チンプンカンプンな所は一定で、辞書などで調べるとどうにかこうにか少しはわかった箇所が増えたものの、一週間かけたほどでは無く.空しい努力に終わる。
残念無念(泣)
仕方が無いので原稿用紙に詞をおこしてみたが、たったの一枚余だった…(なんだか,複雑…)
本「一札如件」は
決まり文句の一つのように 最後には
一札 仍而 如件(いっさつ よって くだんのごとし)
如件 は
如
レ
件
この
如
が、気にかかる。
【如】とは
[常用漢字] [音]ジョ(漢) ニョ(呉) [訓]ごとし しく もし
〈ジョ〉
1 そのとおり。…のごとく。「如上」
2 状態を表す語に添えて調子を助ける語。「晏如(あんじょ)・欠如・突如・躍如・鞠躬如(きっきゅうじょ)」
〈ニョ〉そのとおり。そのまま。…のごとく。「如実・如法・如来・如是我聞(にょぜがもん)/一如・真如・不如意」
[名のり]いく・すけ・なお・もと・ゆき・よし
[難読]如何(いかが)・如何(どう)・如何(いか)なる・如何(いか)に・如月(きさらぎ)・不如(しかず)・莫如(しくはなし)・不如帰(ほととぎす)
デジタル大辞泉引用
今回の「一札如件」の中には 「如法」が出てきた。
【如法】 (にょ‐ほう)[名・形動]とは
1 仏語。仏の教法にかなっていること。
2 文字どおりであること。また、そのさま。「―の闇」
3 穏やかであること。柔和であること。また、そのさま。「―なる気もまる額、にこやかに」〈浄・今宮の心中〉
デジタル大辞泉引用
さらに 三省堂 大辞林では
(1)〔仏〕 仏の教えどおりである・こと(さま)。
「功徳も御祈りも―に行はせ給ひし/大鏡(頼忠)」
(2)柔和なこと。温厚篤実なこと。また、そのさま。
「その身の―なるに任せて/御伽草子・羅生門」
(3)(副詞的に用いて)もちろん。もとより。
「―夜半のことなれば、内侍も女官もまゐりあはずして/平家 11」
三省堂 大辞林引用
にょほうにょほう(わらい)
なんてことは間違っても書きませんぞ!
なんだかわかったようなわからないような
むずかしいものだなぁ~と 穏やかなわたくし
誠に
堅相守如法ニ為相勤可申候
なので ごじゃりまする(*^_^*)
平常心是道 びょうじょうしんこれどう
南泉 因みに趙州問う、
如何なるか是れ道。
泉云く、平常心是れ道。
州云く、環って趣向すべきや否や。
泉云く、向かわんと擬すれば即ち乖く。
州云く、擬せずんば争でか是れ道なるを知らん。
泉云く、道は知にも属せず、
知は是れ妄覚、
不知は是れ無記、
若し真に不擬の道に達せば、
猶大虚の廓然として洞豁なるが如し、
豈(あに)に強いて是非す可けんや。
州云く、言下に頓悟す。
豈とは (大辞泉より)
1 あとに推量を表す語を伴って、反語表現を作る。どうして…か。
「価なき宝といふとも一坏(ひとつき)の濁れる酒に―まさめやも」〈万・三四五〉
2 あとに打消しの語を伴って、強い否定の気持ちを表す。決して…ない。
「夏蚕(なつむし)の(ひむし)の衣二重着て隠み宿(やだ)りは―良くもあらず」〈仁徳紀・歌謡〉
豈とは (日本国語大辞典より)
1〔副〕反語表現に用いる。どうして。何として。推量の助動詞「む」に助詞「や」を添えた形をあとに伴う場合。まれに「や」のつかない例もある。*万葉〔8C後〕三・三四五「価無き宝といふとも一坏(ひとつき) ...
2 あに =図(はか)らん(や)[=図(はか)りきや]-日本国語大辞典
(反語の副詞「あに」に、動詞「はかる」、助動詞「む」、助詞「や」が連なったものが呼応し、それが一つの言いまわしとして固定したもの)次に来る文で表現される事態が予想外の時に使う。(「…とは」「…と」「 ...
がい‐てい【豈弟・悌】-日本国語大辞典
3 〔名〕人柄のおだやかなこと。また、やわらぎ楽しむこと。*古事記〔712〕序「乃ち、牛を放ち馬を息(いこ)へ、悌して華夏に帰り」*伊呂波字類抄〔鎌倉〕「悌 カイテイ」*常山文集〔1718〕七律「我元 ...
(写真は「翁」 2012年1月 京都八坂神社にて)
雲絶照天地 無風地不動
万歳楽吉日 青葉満心潤
鳴滝水満々 翁舞滝変酒
2013年5月4日 先負
【先負】(せんぷ)とは
六曜の一。急用・争い事・公事などを避け、静かに待つのがよいとされる日。
午前は凶、午後は吉。
先負日。せんまけ。さきまけ。
雲絶照天地 無風地不動
万歳楽吉日 青葉満心潤
鳴滝水満々 翁舞滝変酒
2013年5月4日 先負
【先負】(せんぷ)とは
六曜の一。急用・争い事・公事などを避け、静かに待つのがよいとされる日。
午前は凶、午後は吉。
先負日。せんまけ。さきまけ。
多くのご来場のみなさま
いつもごひいきいただき、誠にありがとうございます☆
今年に入り散歩や読書や芝居や美術館関係の記録更新を怠っております、
なのに毎日今も300人以上の方々にお越しいただき、更新できない今でも多い日は400人を越えることもあります。
また、gooコメントやメールでご心配いただいているみなさまにも、心より御礼申し上げます。
ありがとうございます☆
ご心配いただいた方の中には、家族のアクシデントや病気や旅行等と言っていただいた物が多かったです。
ですが、わたくしもわたくしの家族も元気でおります。
ちょっとした人生の風邪のようなものです。
庭の梅はとうにおわり、葉。トキワマンサクも満開です。
そのうち できるだけ早く記録ブログを再開いたします。
その折は、みなさま、暖かく見守っていただければと感じます。
今日は時間ができましたので、出かけることにします。
今日の記録も近日中にしたいと考えています。
みなさん、どうぞよろしくお願いします^^
何があっても、
世の中のみなさまに感謝する心を忘れないで生きて行きましょうっと!
みなさんもわたくしも
楽しい時間をつなぎあわせて、満足を味わえる時間を過ごしましょうね(*^_^*)
今日も楽しみましょう!^^!
『外郎売』
出演:尾上松緑 河原崎権十郎 坂東亀三郎 坂東亀寿 尾上松也 中村梅枝 中村萬太郎 尾上右近 片岡亀蔵 市村萬次郎 市川團蔵 坂東三津五郎
2011年
40分
カラー
お正月にふさわしい曽我狂言、早口の言いたてが見どころ聴きどころ。 遠くに富士を望む大磯の遊廓。工藤祐経が小林朝比奈やその妹舞鶴たちを従え廓で休息していると、小田原名物の外郎売に身をやつした曽我五郎がやって来る。祐経に評判の早口の言い立てを所望された五郎は、妙薬である外郎の故事来歴や効能を立て板に水の如く披露しながら、祐経への敵討ちの機を狙っているが、兄の十郎に時節を待てとたしなめられる。親を思う心を察した祐経は、狩場での再会を約束するのだった。 松緑の曽我五郎に、権十郎の朝比奈、萬次郎の舞鶴、松也の曽我十郎、三津五郎の工藤祐経ほかの出演でお届けする。 (2011年/平成23年11月・新橋演舞場)
『名作歌舞伎全集』(東京創元社)で早口言葉を言ってみたが、なかなか難しくって…
おまけに仕草までつけると、頭は真っ白となりまする☆
拙者 親方と申すは
お立合いの中(うち)にご存知のお方もござりましょうが
お江戸を発(た)ってニ十里上方
相州小田原一色町をお過ぎなされて
青物町を登りへおいでなさるれば
欄干橋虎屋藤右衛門(らんかんばし とらや とうえもん)
只今は剃髪致して円斎(えんさい)と名乗りまする。
元朝(がんちょう)より大晦日(おおつごもり)まで
お手に入れまするこの薬は
昔、珍(ちん)の国の唐人(とうじん)
外郎(ういろう)という人
わが朝(ちょう)へ来たり
帝(みかど)へ参内(さんだい)の折から
この薬を深く籠(こ)め置き
用ゆる時は一粒(いちりゅう)ずつ
冠(かんむり)の隙間より取り出(いだ)す。
依(よ)ってその名を帝(みかど)より
透頂香(とうちんこう)と賜る)。
即ち文字(もんじ)には
「頂(いただ)き・透(す)く・香(にお)い」
と書いて、とうちんこうと申す。
只今はこの薬
殊の外(ことのほか)
世上(せじょう)に弘(ひろ)まり
方々(ほうぼう)に似看板(にせかんばん)を出(いだ)し
イヤ
小田原の
灰俵の
さん俵の
炭俵の
といろいろに申せども
平仮名をもって「ういろう」と記(しる)せしは
親方円斎ばかり
もしやお立合いの中(うち)に
熱海か搭(とう)の沢へ
湯冶にお出(おいで)なさるか
又は伊勢御参宮(ごさんぐう)の折りからは
必ず門違い(かどちがい)なされまするな。
お登りならば右の方(かた)
お下りなれば左側
八方(はっぽう)が八つ棟(やつむね)
表が三つ棟(みつむね)
玉堂造り(ぎょくどうづくり)
破風(はふ)には
菊に桐の薹(とう)の御紋を
御赦免(ごしゃめん)あって系図正しき薬でござる。
いや最前(さいぜん)より
家名の自慢ばかり申しても
ご存知ない方には
正身(しょうしん)の胡椒の丸呑み
白河夜船(しらかわよふね)。
さらば一粒(いちりゅう)食べかけて
その気味合いをお目にかけましょう。
先(ま)ずこの薬をかように一粒(いちりゅう)
舌の上にのせまして
腹内(ふくない)へ納めますると
イヤ
どうも言えぬは
胃・心・肺・肝(い・しん・はい・かん)がすこやかになって
薫風(くんぷう)喉(のんど)より来たり。
口中(こうちゅう)微涼(びりょう)を生ずるが如し。
魚鳥(ぎょちょう)・茸(きのこ)・麺類の食い合わせ
その外(ほか)万病(まんびょう)速効ある事
神(かみ)の如(ごと)し。
さてこの薬
第一の奇妙には
舌のまわることが
銭独楽(ぜにごま)がはだしで逃げる。
ひょっと舌がまわり出すと
矢も盾もたまらぬじゃ。

wao! 葉っぱが…
でっけいかなでっけいかな
?
ちゃう
ちゃうちやう
絶景かな絶景かな
こちらが「五三の桐」でごじゃりまする。
南禅寺山門 (12景)
ぜっけいかな、ぜっけぇいかな。
春の宵はあたい千両とは、
ぁ ちいせぇ、ちいせえぇ