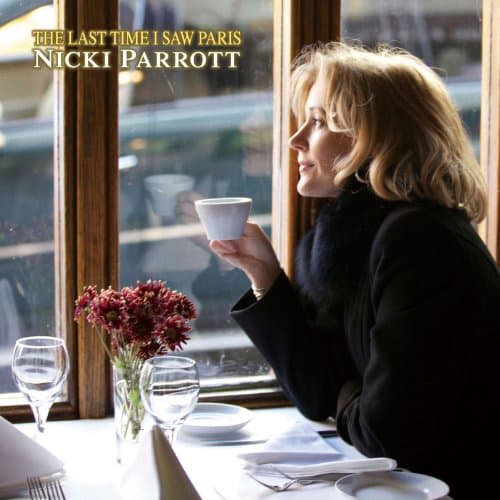アクアデザインアマノが考案した苔玉です。オリジナルは高額なので手作りした。

一般的な水草にはないメリットがたくさんあります。最大の特長は取り扱いがカンタンなこと。
水草を植える手間さえ必要なく底床に置くだけです。水中に置いても簡単に水草早々になります。
現在筆者の部屋には3個の侘び草が生息しています。
詳しくは、http://www.adana.co.jp/jp/contents/products/wabikusa/index.html

有茎草やシダ、コケや特定の種類に捉われずに自由に色々な種類を 混ぜた苔玉です。
手入れ要らずで簡単に楽しめるようなので 早速自作しました。

今日は侘び草から小さな花が咲きました。 意外と水の減りは早いようです。
毎日の水を追加しなければなりません。鉢を深い鉢に変えればいいのですが・・・・・

意外と簡単にアクアリウムが楽しめそうです。

早速LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. にワイドコンバージョンレンズ
を付けて撮影。電動沈胴機構でコンパクト感が良いですよ!ライカみたいです!

次々と花目がついています。5mm程の小さな可愛い花です。
侘び草って買うと意外と高いんですよ(笑)
筆者も水草眺め先日アンプLINNに変更し未だ音楽視聴を試さなとLINNのポテンシャルがわかりませんので、
以前にも紹介したカフェ・ツィマーマンCafé Zimmermannをじっくり聴いてみます。

18世紀、ライプツィヒの聖カタリナ通りにある ゴットフリート・ツィマーマンのコーヒー・ハウスでは、
毎週コレギウム・ムジクムのコンサートが開かれていました。聴衆と演奏家とを結ぶ、
この開放的で親しみやすい精神に触発されて、 1998年にパブロ・ヴァレッティと
セリーヌ・フリッシュは アンサンブル・カフェ・ツィマーマンを結成。
カフェ・ツィマーマンによる「さまざまな楽器のための協奏曲集」
(現在、第四集まで刊行中)がそれである。 カフェ・ツィマーマンとは、
バロック・ヴァイオリン奏者パブロ・バレッティと
チェンバロ奏者セリーヌ・ブリッシュが主宰する気鋭のアンサンブルで、
その名の由来は、 バッハが「コレギウム・ムジクム」という
コンサート・シリーズを開催していたライプツィヒ の コーヒーハウスの店名にある。

さらに、「さまざまな楽器のための協奏曲集」というシリーズ名は、
「ブランデンブルク協奏曲」 献呈譜の表紙に仏語で書かれた
「Six Concerts Avec plusieurs Instruments」
(さまざまな楽器のための6つの協奏曲集)に由来しておるそうです。
凄く説得力のある言い回しですね・・・・・・・言われれば確かに さまざまな楽器・・・・
J.S. Bach, III Koncert Brandenburski BWV 1048 : Allegro (I). Café Zimmermann - Katedra Gnieźnieńska
今回筆者が特に注目したのは セリーヌ・フリッシュ(Celine Frisch)(チェンバロ)
の奏でる『ゴルトベルク変奏曲』の基本の低声部を使った14のカノンと、
第30変奏のQuod libetクォドリベットのもととなった2曲が入っている。
カノンの方はともかく、クォドリベットのもととなった2曲
あとで気がつくがこのゴルトベルク変奏曲には秘密がある曰く付きのアルバムなのである

Quod libet(ラテン語で「好きなように」の意) は音楽形式で、
15世紀のルネッサンス時代に はじまりました。
複数の人がそれぞれ違う歌を同時に 歌う遊びでしたが、
器楽曲ではバッハの ゴールドベルグ変奏曲の終曲などがquodlibetと いわれています。
Johann Sebastian Bach, 'Aria' Goldberg Variations
以前カフェ・ツィマーマンをアップした時と今回は音色と音の厚みがでて実に快く聞こえます。
此のアンプはやはり英国の音なんです。と言うより音楽を良く知った音なんです。
しかし、今回色々の曲を聞くうちに分かったことは、ピンマイクで録った音は前のアンプが音は澄んでいた。
昔から思うが、実に音は繊細であり、微妙です。昔、五味先生が茄子(KT88)を変えるだけで、音が違う、
此の茄子はピアノに良くこれはヴァイオリンにといったいた事が良く理解出来ます。

益々、此の系統(バロック音楽)の曲を聴くことが多くなるでしょう。
300年の時を超えて…やはりカフェ・ツィマーマンCafé Zimmermannのバッハが凄い!