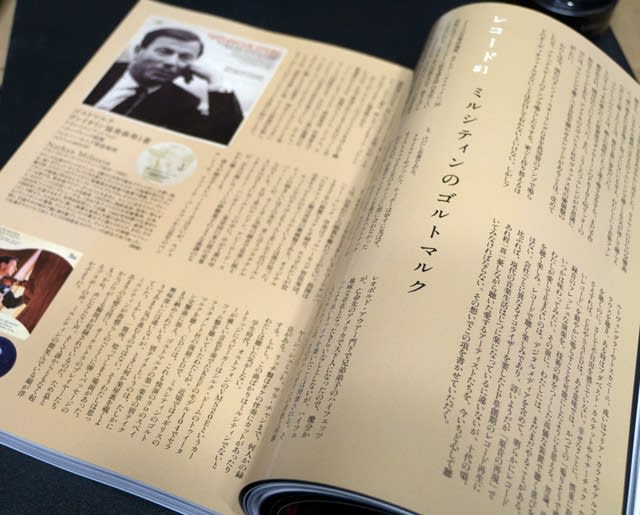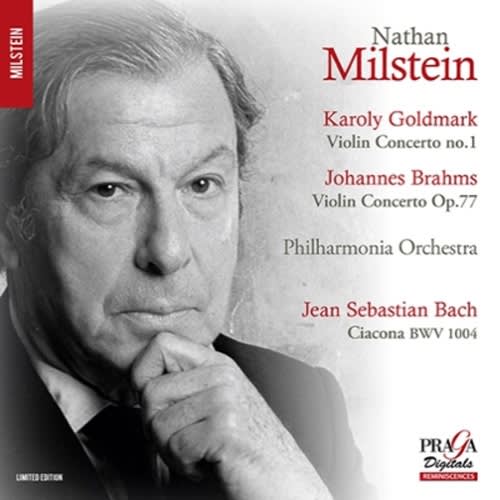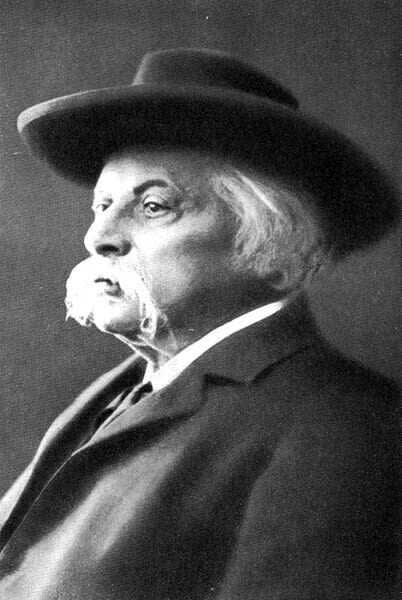我家の庭にヒヤシンスが咲き始めた、 この時期は色々な花が咲何か嬉しくなる。

春の優しい風が運んで来るようである。

最近修理から帰り鳴らし運転を始めた我家のオールドタンノイⅢLZ音はまだまだである、
それと筆者の居間も手狭なので少し広く使えるように片つけ出したが捗りません。
最近バッハ以外の音楽を聞き出したがやはり落ち着くのはバッハになります。

ジャン=ギアン・ケラスJean-Guihen QUEYRAS(チェロ) 1967年モントリオール生まれ。
リヨン国立高等音楽院、フライブルク音楽大学、ジュリアード音楽院でチェロを学ぶ。
レパートリーはバロックから現代まで多岐にわたり、ウィーン楽友協会、コンセルトヘボウ、
シャンゼリゼ劇場、ウィグモアホール、 カーネギーホール等、
欧米の権威あるコンサートホールの多くでリサイタルを行っている。
筆者も好きなメルニコフ(ピアノ)とのベートーヴェン「チェロとピアノのための作品全集」、
メルニコフならびにファウスト(ヴァイオリン)とのベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第6番、第7番」等のCDをリリース
(ハルモニア・ムンディ/キングインターナショナル)、数々の賞を受賞している。

演奏楽器は1696年ジョフレド・カッパ製(メセナ・ミュジカル・ソシエテ・ジェネラルより貸与)。
今回はバッハの無伴奏チェロを聴いてみる。
Jean-Guihen Queyras: Bach Cello Suite 2 - Allemande
モダン楽器による、ピリオド奏法(古楽器の奏法)を取り入れた演奏。
無伴奏チェロ組曲の「顔」ともいえる、第1番プレリュードは楽譜通りの正攻法で、素晴らしいの一言。
ピリオド奏法ながら、全体的にとても楽しく、面白く聴くことができた。
筆者の好きなカザルスと比べるとテンポは少し速めですが春風が通り抜ける爽やかさが感じられる。
ピリオド奏法に抵抗がなければ、初めてこの曲集を手にする人にもお勧めできるだろう。

我家のオールドタンノイⅢLZも本調子とは言わないが、其処鳴る感じです。
色々不満も多いのですが、ヴァイオリンよりむしろチェロの音のが相性がいいのか?
此のⅢLZってラッパは最近思うのはオールドなシステム?カラード、オルトフォン、
オールドな真空管 幾ら懐古主義者だと言われてもやはり、

もう一度は火屋を眺めながらながら聴いてみたい。 オールドタンノイを真空管アンプで楽しむ・・・・・
真空管アンプは大きく重い。 重量の大半は電源トランスと出力トランス。
でも此のアンプはオールドタンノイオールドファンからもかなり賞賛されているようです。
これはキット屋の製品で、電力増幅管に300Bを用いたシングルアンプ(2004年製)
300BはWEではなくエレクトロ・ハーモニックス製。
価格的にも頑張れば?何ととか貧困老人でも手がつどくのかも知らない??
メーカーによれば、’96年発売のアドバンスM-501の改良機となっています。
等によって鳴らさないと真価が発揮しないのでは?と考える。一度試聴したい。
そのような事が頭の中を駆け回る、しかし其れには仕事をして稼がないと実現しないのだが
相わからずサボタージュしてしまう貧困老人のようだ、元来怠け者の筆者です。
そこで筆者も好きなバッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバを聴く

リュシル・ブーランジェ(Lucile Boulanger) 5歳でクリスティーヌPlubeauとヴィオラダガンバを開始します。
「脚のヴィオラ」を意味する楽器ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ。
見た目はチェロのようですが、異なる種族の楽器であり、通常6本の弦が張られています。(チェロは4本)
美しく流れてゆく旋律に身を任せ、当時の楽器(バッハの時代のものを復元しています)
の素晴らしい音色を楽しみましょう。

5歳から古楽器を始めたという2人の名手による演奏です。
リュシル・ブーランジェほか『バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ』
BACH - Sonate en sol mineur BWV 1029 "Allegro" Lucile Boulanger Arnaud de Pasquale Enregistrement
精巧な演奏と強烈な演奏意欲を感じる。 録音の良さもあるが、
何よりもバッハの音楽をこれだけ生き生きと精細に再生しうる演奏はめったにない。
ヴィオラ・ダ・ガンバの音色と表現能力は現代楽器にも劣らぬ魅力があることを再認識。

チェンバロのリアリゼーションの卓越さにも驚く。満喫の一点。
【曲目】
J.S.バッハ: 1. ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV1023(ヴィオラ・ダ・ガンバを使った演奏)
2. ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ ト長調 BWV1027
3. チェンバロのためのトッカータ ハ短調 BWV911
4. ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ ニ長調 BWV1028
5. ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ ト短調 BWV1029
【演奏】 リュシル・ブーランジェ(ヴィオラ・ダ・ガンバ/ティールケ・モデル)
アルノー・ド・パスクアル(チェンバロ/J-H.ジルバーマン・モデル)
新しい演奏者も次々に現れ益々楽しみが増えますね!リュシル・ブーランジェも新しい演奏者です。