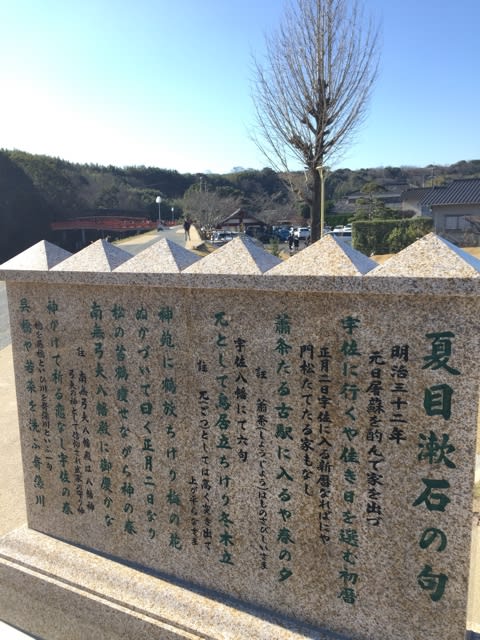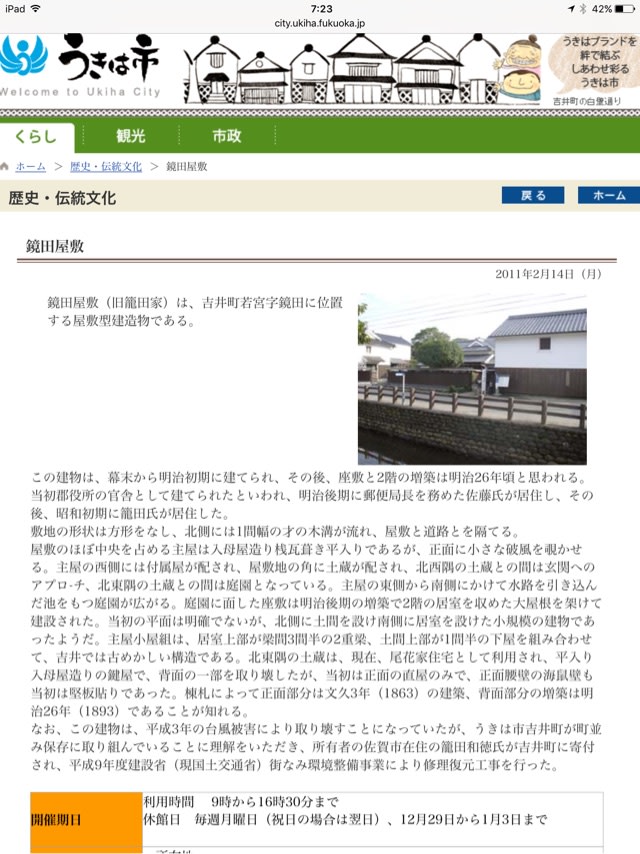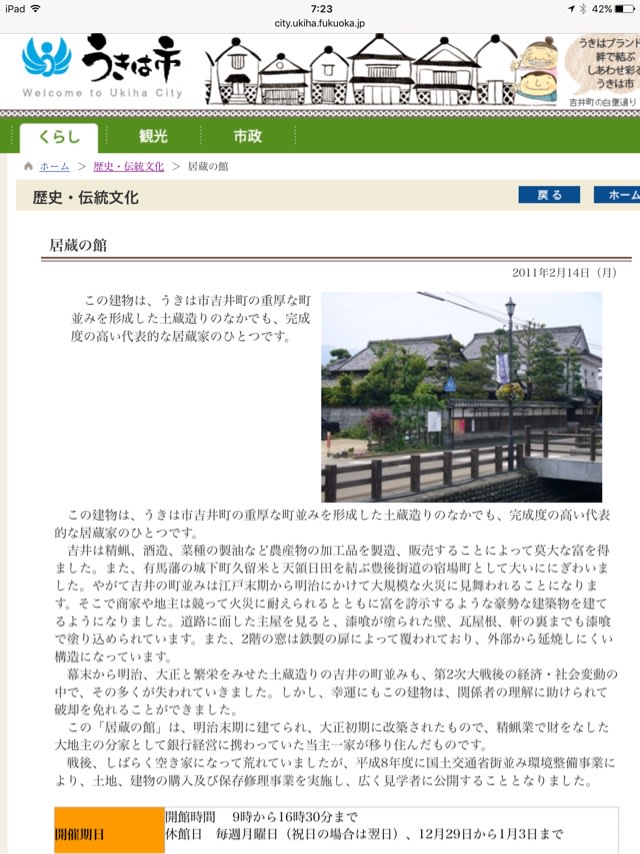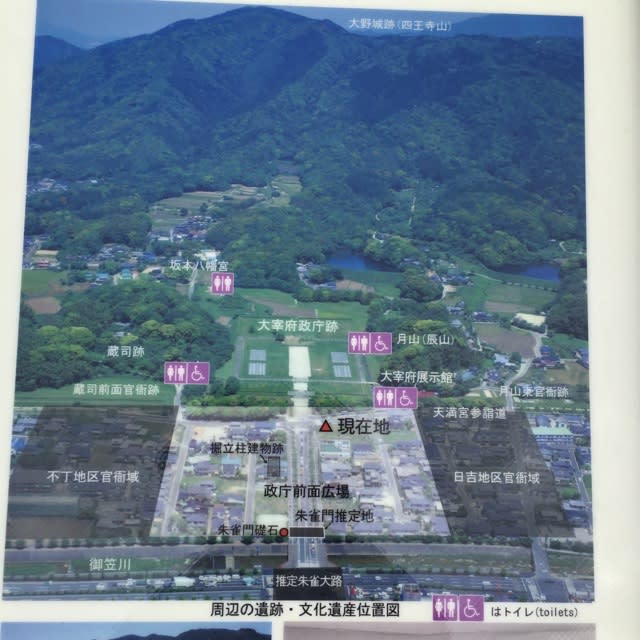湯布院でどっと疲れて…
最終観光は別府鉄輪温泉の海地獄でした。




でもその前に、なぜか昭和の観光土産物会館へ連れて行かれました。
ツアーのお約束なのかな。
大分県から1000円のクーポン貰ったからね。
わずか30分の滞在時間だというのに、
そこには入らずに向かった先はスーパー。
夜のお弁当とか仕入れました。
近隣といえどその往復でさらにドッと疲労蓄積。
そしてやっと海地獄へ。


2020年元旦にも訪れてます。
あの時同様、掃除行き届いてました。
2回目でもぜんぜん嫌じゃなかった。
湯布院との違いはなんだろう。
ざーっと別府のこと調べてて、
海地獄の5代目代表、千壽智明社長のnoteブログに辿り着きました。
「地域の魅力を多くの人と共有し、ファンになって頂く」
その思いを受け止め拡散しておきましょう。
温泉が誕生する奇跡を知りました。
別府の温泉は、別府市と由布市の境にある鶴見岳・伽藍岳という活火山を「熱源」とする。
この時に海地獄ができたと推定される。
九州を北東-南西に縦断する別府-島原地溝帯にあり、
雨水が地下に染み込み地下に水が溜まりやすく「水量豊富」
別府が日本一の湯量を誇るのは、これら3つがであった奇跡。
海地獄の経営者はさらに一歩前へ。
昨年12月に地獄温泉ミュージアムを開館させました。

帰りのバス集合時間までの時間潰しで立ち寄りました。
地獄温泉ミュージアム併設のカフェでお茶休憩。
かぼすソルティドッグ風炭酸水、超美味しかった。
もう歩きたくなくて。
この日は入場料1500円ケチりました。
今回調べてみて思ったことに、
体力まだある時に時間許せば覗いてみたい。
新たな試み頑張って欲しいですもん。