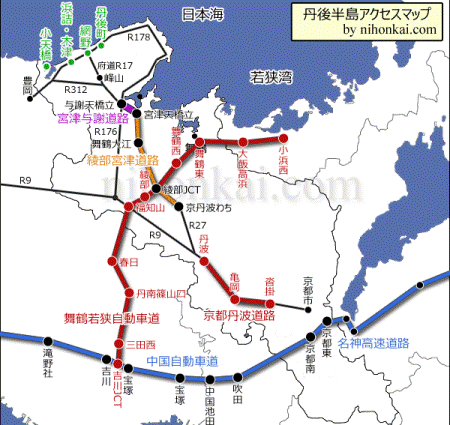お水取りは法会の中の一つの行にすぎず、意外とその全貌は知られていない。
もちろん私は全く知らなかった(これまで興味もなかった)。
ちなみに東大寺は華厳宗の総本山です。
華厳宗がどういったものかもよく存じませんが、
お水取りは今回調べてびっくりするほどすごい法会でした。
大仏開眼の開眼師、菩提僊那はインド僧で、
実忠もペルシャ人またはインド人ではないかと言われています。
「お水取り」の行は、類似の行事が中国や朝鮮にはないそうです。
若狭から奈良まで水を送るという発想は、イラン地方のカナートというインフラが起源という説もあります。
二月堂の修二会について、検索すればいろんなサイトで詳しく述べられていますが、
せっかく調べたので、かいつまんで記録しておきます。
修二会(しゅにえ)の正しい名称は、
十一面悔過(けか)の法会といいます。
元々は旧暦の2月1日から行われたので「二月に修する法会」が「修二会」に。
752年から一度も絶えることなく毎年続けられ、今年2011年でたぶん1260回。
十一面悔過の、悔過とは懺悔。
雨乞いや病気平癒のための呪的な法会であった悔過会は
正月には、旧年の罪障を仏に懺悔し、新年の除災招福・豊穣安穏を祈願する法会となる。
この天下泰平・五穀豊穣・万民快楽を願って懺悔を勤める行は、
他に南都の名刹である薬師寺・興福寺・法隆寺はじめ全国あちこちで執り行われます。
ただこの東大寺が最も著名にして最も厳密な悔過会であり続けています。
修二会が創始されたはずの大仏開眼の年には、現二月堂が建つ所に建物はなく井戸一つだけがあったそうです。
聖武天皇は749年に譲位され太上帝となり、
光明皇后は皇太后になられ、その紫微中台に「十一面観音悔過所」があった。
そこで最初期の「十一面観音悔過行」が行なわれたようで、
悔過には光明皇太后の公私に渡る情念が深く塗り込められていたのです。
修二会の行では、本行に先立ち「
大中臣祓」が行われ、
連行衆は各人が御幣を持ちそのつど自らを祓い清める、神仏習合です。
悔過作法は「
五体投地」と聞くと驚く。
これってチベットとかの映像でみたことある。
平衆が交代で勤める時導師を中心に、旧年の罪障を悔過懺悔するが、
「一称一礼」という声明ごとに「五体投地」で体を投げ出す礼拝を行なうそうだ。
呪禁作法は、「咒師」が内陣に何重にも結界をはり悪魔悪霊の侵入を防ぐ。
それを担うのは、注連縄(〆め縄)なんだそうだ。

準備された注連縄

二月堂周辺にはられた結界の注連縄
大導師が新年の安穏豊楽を祈り、「神名帳」や「過去帳」の読誦を行なう。
二月堂鎮守の三社(興成社、飯道社、遠敷社)の守護神ばかりではなく、
日本全国から一万四千余所の神々が勧請されて「
神名帳」読誦は毎夜行われます。
華厳宗の総本山・二月堂修二会の行は、仏教法会でありながら奇妙な作法がいっぱい。
最も有名なものが「
若水汲み」は日本の正月行事「お水取り」です。
「
達陀」妙法というのは、読み方も「だったん」なんて韃靼人みたいです。
「咒師」の鈴と叫びを合図に、火天役が達陀松明を所狭しと振り回し、内陣を火の海とする。
実際、火事となり二月堂を焼失したこともあるそうです
これに応えて、水天役が香水を振りまく

この達陀妙法は十四日の結願まで続けられ、「火と水の祭り」と言われる所以です。


1日6回の行を14日間くり返し、上七日(前半7日間)の本尊は十一面観音
下七日(後半7日間)での本尊も十一面観音だが「小観音」と通称される別本尊で、どちらも秘仏です。
小観音は、補陀落山から難波津に流れ着いた仏といわれ、
常世から寄り来る神(マレビト)としての仏。
以上の上下各七日の中に、
「過去帳」の読誦、「走り」行堂と「香水」まき、「若水汲み」(お水取り)、「達陀」(だったん)妙法などがあります。
「
過去帳」とは、東大寺の有縁者が聖武天皇や源頼朝から無名の下々まで、
現在の今上天皇や現首相まで含まれる方々のお名前を読み上げられます。
ここで怖いエピソードが残されています。
鎌倉時代の修二会の最中、集慶という僧侶が過去帳を読み上げていると、
眼の前に青い衣の女性が音も無く現れて、
「私の名を読み落とした」
困った集慶はとっさに「青衣(しょうえ)の女人」と読み上げると、満足げに消えていった。
女人結界の内陣に女人が現れるわけがないのです。
しかしそれ以降、過去帳には「
青衣の女人」の名が記され、
現在でも声を落として低く読み上げられるのだそうです。