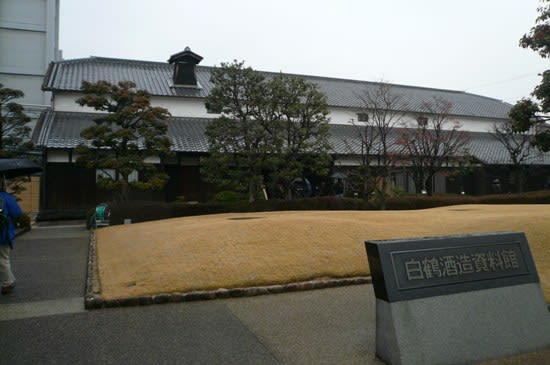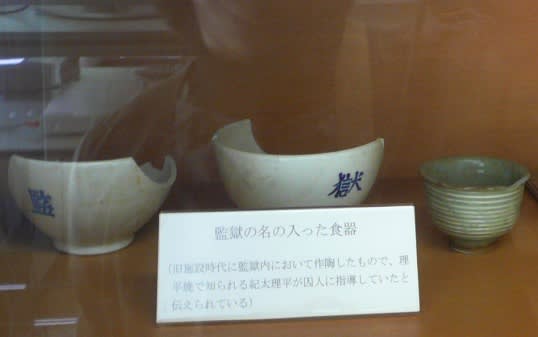金剛山には錬成会があることが、おそらく他の山と異なる点ではないでしょうか。
TVなどで金剛山へ何百回、何千回も登られてる方の映像をご覧になられてるかも。

広場に1000回以上のお名前が貼り出されています。
10000回以上もお一人おられました。
1日1回でも27年はかかるということになる。
金剛錬成会は、金剛山葛木神社の崇敬団体として1963年に発足され現在に至ります。
主に回数登山を中心に活動しており、現在の会員数は4000人を越えてるとか。
登山回数を記録するカードがあり、心身鍛錬と自然との調和を目的に登頂されたら、金剛山登拝回数捺印所でスタンプ押してもらえます。

毎年5月3日のさくら祭りに百回以上の登拝者が表彰されるそうです。
山頂には転法輪寺(てんぽうりんじ)というお寺があります。


大人になってからで3回め登山にして、やっとこのお寺の存在に気づいたのでした。
不動明王の前の護摩壇をきれいにされてたお寺の方に
踏んだらあきませんよと注意されました。
そして7月7日に是非お参りにおいでなさいと。

この寺の本堂へと続く階段はきれいに掃き清められ、雪は残ってなくて足を滑らすということがない。
お掃除が行き届いていて、さすが修験の中心地だなと大変印象に残りました。
家に帰り、7月7日に何があるんだろうと調べてみました。
転法輪寺で検索すると、日本のあちこちに同じ名前のお寺があることが判明。
なんとインドのサルナートにも初転法輪寺があり、
映し出された画像を見てると、2006年1月にインドのサルナートへ行った時見た景色か??
インドまで行きながらお参りした寺の名前を覚えていないのだった。
初転法輪(しょてんぽうりん)とは、釈迦が初めて仏教の教義(法輪)を人びとに説いた出来事を指すようです。
まず最初にお釈迦さまはかつての五人の比丘に教えを説こうとされ、これが伝道活動の開始となります。
これを初転法輪と呼びます。
「輪」というのは古代インドで使われた武器で、輪の回りに刃物がついています。
もちろんお釈迦さまは武器を手にされたわけではなく平和の「輪」の法輪を回転させたという意味です。
で、金剛山の転法輪寺は、山岳宗教の開祖 役の行者が開かれました。
毎年7月7日は「れんげ祭」
なんで、夏にれんげやねん と思ったら蓮華だった。
吉野の金峯山寺の蓮華会(れんげえ)は毎年7月7日 ということでわかりました。
そしてこの日は、役の行者のご命日でした。
葛木一言主ノ神を祀る葛木神社と法起菩薩を本尊とする転法輪寺との珍しい神仏習合のまつりの日です。
7月7日忘れずに、いつかそのうち…

今でこそ金剛山(こんごうさん)と言われていますが、
古くは葛城山(かつらぎやま)または高天山(たかまやま)と言われていたそうです。
ちなみに葛木神社の現在の住所は、奈良県御所市高天476
古事記・日本書紀、内容はそれぞれ若干異なっていますが、
雄略天皇と一言主神(ひとことぬしのかみ)との逸話は、この葛城山が舞台となっています。

天智天皇4年(665年)役の小角(えんのおづぬ)16才の時、
この山に登られ霊気を感得し長い修行の後、
頂上に法起菩薩を御本尊とする金剛山転法輪寺を建立されました。
役の小角は金剛山の奈良側の山麓になる御所市出身で、
ご自身の祖神である一言主神を祀る葛木神社を鎮守としてあわせ祀られ神仏混淆の霊峰とされました。

以後、真言密教の霊場として信仰を集め、
転法輪寺のお寺の山号である『金剛山』が略称の様に使われ葛城山脈中の最高峰を指す名称になったとも言われています。
時代はすすみ後醍醐天皇の時代、楠正成が転法輪寺の山伏勢力を利用しわずか500の兵で知略を使った結果、関東5万の大群を寄せ付けなかった。
千早城の要塞としても関わりの深いものがあったと言われています。
近世までは葛城修験の中心地として栄えていたのが、明治維新を迎え神仏分離令によって廃寺に。
そして昭和10年まずは葛城神社が復興され、
昭和25年役行者1250年忌に再興事業が始まり昭和37年(1962)にようやく転法輪寺も復興。
このときに金剛山葛木神社宮司であった葛城貢氏が、登山者の会「金剛錬成会」を発足させたようです。