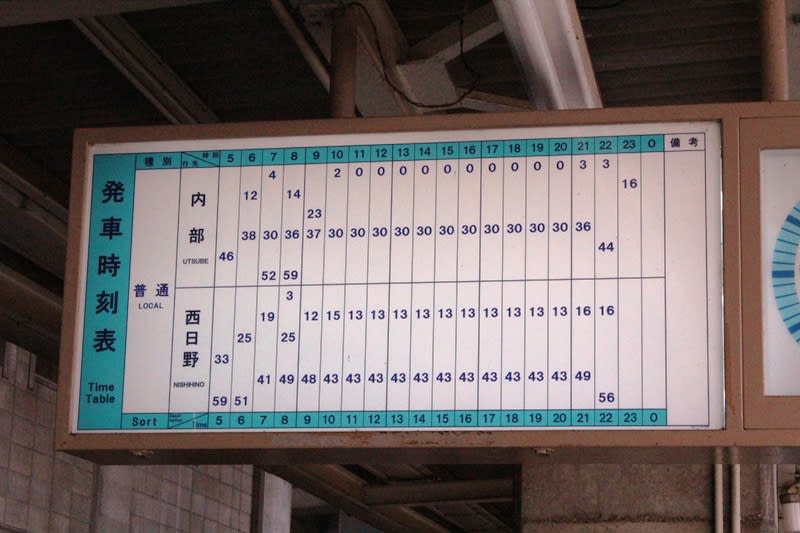このところ、新聞報道で消費税の軽減税率が取り上げられています。自民党は導入に慎重ですが、公明党が積極的です。今日の朝日新聞朝刊3面14版のに掲載されている「軽減税率なお平行線 自公、導入時期で対立」という記事によると、公明党は2014年4月から軽減税率を導入するように主張しています。これに対し、自民党は、基本的に軽減税率を導入しないという方向のようです(2015年10月からの導入という意見もあるようですが)。
今年の7月に行われる予定の参議院議員選挙への対策をはじめとして、それぞれの政党の思惑はあるものと思いますし、両党で具体的にどのような議論が行われたのかということまではわからないのですが、私は、昨年の1月3日付で記した「大晦日に青葉台で買った本から、消費税の正当性を訴える本を取り上げてみました。」でも記した通り、軽減税率の導入には反対の立場をとります。
但し、昨年の記事から見解を改めました(訂正に近いものとなります)。そこでは「日本の場合はインボイス方式でないために軽減税率を導入すると面倒な話になる、ということもあるのですが、それは大した問題ではありません」と書いたのですが、これは誤りでした。「大した問題」であり、消費税の仕組み、付加価値税の構造という根本的な問題に関わる深刻な問題なのです。
税制に限らないことなのですが、軽減税率についても、実に単純な議論が横行しています。当たり前の事実を忘れているのです。そのためにずさんな比較となり、拙速となり、失敗につながるのです。
日本の租税法学などでは常識的な事柄ですが、日本の消費税は付加価値税の中でも他の国に例がない構造です(Alan Schenk and Oliver Oldman, Value Added Tax, A Comparative Approach. Cambridge University Press, 2007という本でも、日本のみのものとして取り上げられています)。
何が独特なのかというと、付加価値税の肝である仕入税額控除のやり方にあります。日本の仕入税額控除はアカウント方式または帳簿方式などと言われているのですが、この方法を採用し続ける限り、軽減税率などできません。少なくとも、まともに施行されえません。仮に軽減税率を導入すれば、必ず、納税・徴税の現場で大混乱を招き、納税義務者である事業者や税理士業界などにしわ寄せが及びます。このような部分にまで目を向けない議論は、政策論としては失格でしょう。
軽減税率を導入するというのであれば、まずはアカウント方式を完全に廃止し、EU諸国としてほとんどの付加価値税導入国では当たり前となっているインボイス方式に切り替える必要があります。そこから始めなければなりません。軽減税率を採用する場合にインボイス方式を採るのは世界の常識(いや、常識以前)の話なのです。
実は、1980年代、日本で消費税の導入に関する侃々諤々の議論が行われた時に、インボイス方式の採用も念頭に置かれていました。しかし、納税義務者となる事業者の猛烈な反対により、アカウント方式になったのでした。理由は、要するに面倒だからというものです。たしかに面倒なのですが、他の国々では行われていることですから、そもそも、日本の事業者は消費税の納税義務者となりうる能力など持ち合わせていない、ということを世界に証明したようなものです。目先のことを優先して問題を先送りし、解決の困難性を増大させる結果に終わるという、日本にありがちな傾向がよく現れています。
アカウント方式では、基本的に売り上げも仕入れも事業者の帳簿のみで判断します。しかし、これでは仕入れの額、仕入れにかかる税額、売り上げの額、売り上げにかかる税額などがわからない場合がありますし、消費税が適正に転嫁されているのかどうかについて、どうしても不正確になります。そもそも、売り上げの額や仕入れの額を消費税込みで処理しているのか抜きで処理しているのかという問題もありますし、帳簿に記載があるのに証拠書類がないという問題もあります。
そのため、現在ではアカウント方式によりながらも、仕入税額控除を受けるためには帳簿、請求書、領収書などを「保存」しておかなければならないことが、消費税法第30条第7項に定められています。しかも、ここにいう「保存」は文字通りの意味に留まらず、税務調査の際にこれらを税務職員に提示することを含むというのが実務の扱いであり、最高裁判例(最一小判平成16年12月16日民集58巻9号2458頁)でもあります(http://kraft.cside3.jp/steuerrecht32-2.html も御覧ください)。この扱いについては「保存」の拡張解釈であるなどという批判があるのですが、考えようによってはアカウント方式を採用しているからこそ生ずる問題であると言えるでしょう。
もう一つ、アカウント方式を採用しているために生ずる厄介な問題が、免税事業者の存在です。売り上げ額が或る一定の金額を下回ると免税事業者になり、消費税を納める義務を負いません。その代わり、仕入れにかかる税額を控除できません。詳しいことはhttp://kraft.cside3.jp/steuerrecht32-2.htmlや租税法学の教科書などを参照していただきたいのですが、流通過程(取引過程)に免税事業者が入ると、その免税事業者は勿論、他の事業者についても仕入税額控除ができなくなります。もっとも、外から見ただけでは免税事業者か否かということなどわからないことが多いでしょうから、ここで別の変な話が発生する可能性もあります。
インボイス方式は、インボイス(仕送状などと訳されます)や請求書に税額が記載されていることを要求します。インボイスは事業者から事業者へ、取引の度に渡されることになります。インボイスがない、または税額が書かれていないインボイスがある、というような場合には、仕入税額控除が認められません。そのため、免税事業者が取引から排除されるということになり、これが日本では大きな問題となりえますが、取引そのもの、仕入れの額、売り上げの額、それぞれにかかる税額に関する明確な証拠書類が最初から存在しますので、後々の計算が楽でしょう。保存、提示の問題も、アカウント方式に比べれば煩雑性は少ないはずです(制度の前提となっているため)。結局は、最終的に消費税を負担させられる消費者にとっても、インボイス方式のほうが利益となるはずです。
軽減税率を採用するということは、消費税に複数の税率を持ち込むということです。従って、納税義務者の申告が行われやすいように制度を組み立てなければなりません。それは、単に、申告書に税額を書き込むということではなく、様々な計算など全体が簡明な制度でなければならないということです。或る意味で、携帯電話などで日本が陥っている「ガラパゴス」状態(あまり良い言葉とは思えませんが)である消費税を、世界の常識に適うものに変更しなければ、そもそも軽減税率など採用できません。インボイス方式に全面的に移行して、その次にようやく適用例などの問題を検討することができます。
繰り返しますが、誰にしわ寄せが及ぶのかを考えていただきたいものです。納税義務者はもとより、税務を実際に担当する者が混乱するのです。それでは悪い税制ということになります。
消費税については、他にも簡易課税制度(消費税法第37条)など、再検討しなければならない問題が多いはずです。単に税率の問題で終わるのでは不十分です。