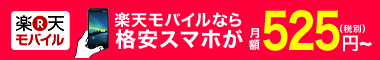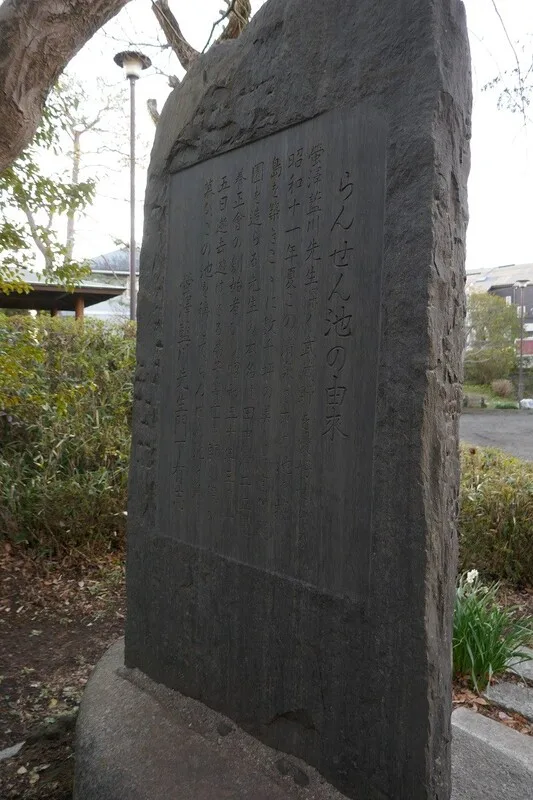こちら田舎の家では、日の出が東京よりだいぶ早いような気がしていたのですが、実際は2分ぐらいしか違わないようです。ただ、高台だし、空も広く開けているので更に早く感じるのかもしれません。

池まで散歩にでると、もうそろそろ帰ったのかなと思っていたオオバンが、まだたくさんいました。

何だか、気温も上がってきたし、いい天気ですが、明日からまた雨が降るみたいで、お決まりのウエザーニュースは、関東内陸部では積雪の可能性なんて脅かしていました。内陸部にはスキー場を擁しているところもあるんだから、「積雪ぐらい普通だろう!!」ってつっ込みたくなります。

第二ハリハル砦。10段ぐらい登ってみたら、降りるのに怖くて苦労しました。やっぱり挑戦は無理かも。

図鑑 カワヅザクラ
河津桜(カワヅザクラ) は、静岡県の河津町で発見された早咲きの桜。沖縄などを中心に咲くカンヒザクラ系と早咲きオオシマザクラ系の自然交配種と考えられており、例年2月上旬になると花が咲き始める。開花時期が早く、また見頃が長く続くのも特徴。

河津桜と思っていたこの花は、
図鑑 カンヒザクラ
原産地は中国南部と台湾。台湾と中国南部に分布する。台湾では主に「山櫻花」と呼ばれ、海抜500-2200mの山地に自生
花は中輪の一重咲きで、釣り鐘状の下向きに閉じたような半開きの形で咲き、濃い紫紅色の花弁を付けるのが最大の特徴

このごろ、結構多く見かける花。
図鑑 立金花(リュウキンカ)
その名のとおり茎が立ち上がって黄金色の花を付けることに由来。 北海道では谷地に自生し、フキの葉に似ていることから「ヤチブキ」とも呼ばれる。
その葉、茎は食用となり、お浸しにすると少し苦味があるものの美味。

図鑑 グランドモナーク
房咲き水仙〈イギリス王立園芸協会の分類ではタゼッタ水仙〉の一種で園芸品種。日本水仙より少し花が大きく、日本水仙に比べ花弁の先が細く尖っているのが特徴。色は日本水仙に比べて、中央の副花冠の黄色がやや薄く、花びらはやや黄色いクリーム色

アオサギ が集まっています。営巣かと思ったら、営巣は高い木の枝にするそうですので、ただ単に、そこに好物の魚がいっぱいいただけなのかもしれません。

調布で散歩しているとき、そこかしこでクリスマスローズを見かけたので、田舎の家の庭でも咲いているかなと思ってたら、やっぱり元気に咲いていました。

クリスマスローズとは、クリスマスローズの原種であるヘレボルス・ニゲルを指した名前で、ちょうどクリスマスの頃に咲くバラのような花、というのが名前の由来。

2月下旬から咲き出し、早春から春に咲くのはヘレボルス・オリエンタリスという系統。日本ではオリエンタリスも含んでクリスマスローズと呼んでいるから季節がずれているんですね。
庭の水仙も立派なのが咲いていました。球根の花はほって置いても何とか頑張ってくれます。

馬酔木(あせび)も咲きだしました。