
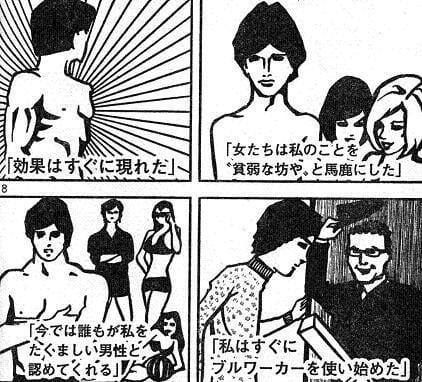


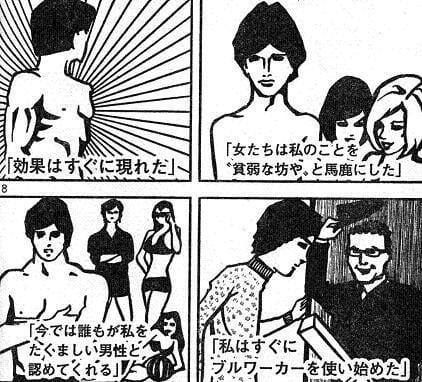

かつて、十二世本因坊丈和という碁打ちがいました。江戸時代後期に唯一「名人」の地位に上がった人です。当時名人になることは、大変な名誉と権勢を手に入れることが出来、しかもその地位は終身安泰!江戸時代の碁打ち達は、この名人を目指して死闘を演じたのですが、その地位につけるのは、勿論技量抜群の最強者だけでした。
ところが、この丈和は、同業者をペテンにかけたり、幕府の有力者に裏工作をしたり、ダーティな権謀術数を弄して、結局全く勝負をしないで名人になってしまったのです!

しかも1度名人になってしまえば、将軍指南役ということで、軽々しく他門の打ち手と戦ったり出来ないし、公式対局も免除されたから、永久に誰とも勝負しなくても良いのです。
しかし、何とか勝負の場に引きずり出して、名人の実力などないことを証明してみせたい他の家元が種々画策し、さる老中のたっての希望ということで、非公式な対局ではあるが、ついに丈和を勝負の場に引きずり出すことに成功しました。
相対するのは、進境著しい若手ナンバーワンの赤星因徹七段。もとより必勝を期していたし、周囲も丈和に敗れることはないと確信していました。
ところが、丈和は強かった。しかも圧倒的に強かったのです。この時の対局は「天保吐血の碁」として有名で、序盤劣勢に陥った名人丈和が、現代にまで語り継がれる3つの妙手を連発し、その後も最善手、最強手の連続で相手を圧倒、赤星因徹七段は吐血して、そのまま世を去ったと伝えられています。
因徹七段の必勝を不動明王に祈願していたという、ある寺の住職は「丈和の技量は、神仏をもってしてもいかんともしがたい」と述懐したとされますが、これほど強かった丈和が、なぜ勝負から逃げ回っていたのか謎とされています。
しかし、彼が勝負を避け続けたことは、まさしく彼が勝負師だったからに他なりません。どんなに強くても、勝負に絶対はない。体調の良し悪し、運不運、一瞬の判断ミス、ほんの些細な事が明暗を分ける。まして命がけの勝負ともなれば、肉体も精神も著しく消耗する。それが勝負です。日々勝負の世界に生きる者に、長生きなどは望むべくもない。
その勝負の過酷さ、凄まじさを知っていたからこそ、丈和は勝負を忌避してきたのですが、それが避けられないと悟るや、全身全霊を打ち込んで戦った。深夜1人で局の検討に没頭し、失禁したことにも気が付かなかった程だったと言いますが、この集中力によって歴史に残る妙手を放ち、名局をものにしたのです。
最後の最後に詰めが甘いと言われる人が世の中には多い。勝負ということを現代の人は忘れ去ったからです。勝負とは勝つか負けるか、つまり生きるか死ぬかの1回きり。後がない戦いの事ですが、現代の人々はゲームよろしく負けてもすぐにリセット出来ると信じている。ましてスポーツを見ても、相手を倒すというより、ポイントを奪い合うゲームとなってしまいました。だから、勝負の何たるかを知らず、真剣に打ち込むことを忘れているのです。
将棋の「王手」とは、文字通り勝敗を決する時に言う言葉で、チェスでは「チェック・メイト」という言葉がこれに当たります。しかし、この言葉には「大失敗」という意味もあるのです。将棋でもチェスでも、安直な王手は味消しの悪手となる場合があるし、それどころか、腰の浮いたところを相手に反撃されて、たちどころに敗勢に陥るという危険もはらんでいます。
因みに、将棋なら王将、チェスならキングがどうやっても逃げられない、絶体絶命の状態、つまり「詰み」のことは、チェック・メイトではなく、「ステール・メイト」(stale mate)と呼びます。
今日はザ・ビートルズに関する、東京での思い出。
ビートルズの最新作『LOVE』のリリースに先がけ、2006年11月19日に『LOVE・発売前夜祭』と題したイベントが、ビートルズがその40年前の来日時に宿泊したキャピトル東急(旧ヒルトン東京ホテル)の「真珠の間」で行われました(「真珠の間」は、ビートルズが記者会見を行ったゆかりの場所)。
イベントのスペシャル・ゲストとして、ビートルズのプロデューサーだったジョージ・マーティンの息子で、父とともに『LOVE』の共同プロデューサーに名を連ねたジャイルズ・マーティンが迎えられるというビッグ・サプライズも当日はありました。

会場は、幸運にも今回のイベント参加に当選したビートルズ・ファンで埋めつくされ、大きな拍手・歓声のなか、ジャイルズ・マーティンが壇上に登場。『LOVE』の制作過程や聴きどころ、「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」のことなどを語ってくれました。

続いてサイケデリックでカラフルな会場と化した「白真珠の間」へと場所を移し、5.1chサラウンドのスペシャル・バージョンの試聴イベントがスタート。5本のスピーカーにふりわけられたサウンド・エフェクトの楽しさを、満喫できるすばらしい内容でした。とくに「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」は、まるでレコーディング・スタジオにいるかのように錯覚するほどの音響効果。11月いっぱいで改築工事のため取り壊されるキャピトル東急ホテルの、まさに最後を飾るのにふさわしい“愛”に満ちあふれた一夜は、盛況のなか幕を閉じました。

東京の人は冷たいイメージがあると関西の人間は言いますが、それは話し方が上からの物言いに聞えることに原因があると思います。関東は上から文化で、関西は下から文化なのです。東京は首都であるという宿命なのか、上から下へと流れて行く文化。歌舞伎にしろ能にしろ、驚くことに、落語も漫才も文化の香りをまといます。関西では「師匠」と呼ばれても、東京では「先生」と呼ばれています。
関西では大衆芸能が庶民の間に文化として浸透しています。井戸端会議のおばさん達の話し方も、商店街での買い物の駆け引きも、関西漫才のようなボケとツッコミの掛け合いで成立しているのです。

東京が権力が作り上げた街なら、大阪は関ヶ原以降、庶民が作り上げた街。権力のあるところには階級がある。そこで育てば上昇志向が発達する。裏を返せば、見栄も張るし、常に力の限りを尽くそうとする。自分に10の力があると思ったら、最初から10の力を見せつける。
ところが、関西の人間は10の力があっても、最初は6か7くらいの力しか見せません。あとは状況に合わせて小出しにして力を見せる。教えてくれる人があれば、素直に耳を傾ける。そんな関西人のやり方で東京の人に接すると、こいつは何も知らない奴だと理不尽な扱いを受けるようになった経験があります。
飲食店も大きな違いがあるように思えます。東京は、店構えも料理の盛り付けも豪華。店員の態度も必要以上に高級感を演出するところが多い。しかし、その味は見かけ倒しが多い。大阪は入り口はチンケでも味よし、人よし、値段よしの三拍子が揃う。東京は外見を大事にし、大阪は中身で勝負のような差を感じてしまうのです。
東京人は関西人の泥臭くて、まとわりつくような言葉を嫌い、関西人は東京のいかにも軽薄でキザな言葉に不快感を覚えると罵る。どちらの言葉にもいい味わいがあるし、文化も面白い。
それにしても、これほど文化の違いが正反対というのが、1番面白いことだと思います。日本で1番北の北海道と南の沖縄を比べても、仲が悪いと言われる県同士を比べても、ここまでハッキリした対比にはなりません。お互いに大都会であるから、「将軍のお膝元」と「天下の台所」だからこそ、「こっちが1番」という対抗意識を持つのかも。
しかし、お互いにいい所を認め、改めて行く心の広さ。これからはそれが求められる時代です。日本人同士でお互いを、文化の差を認められないようでは、日本人もいつか、海外のいろいろな国のように、人々が分断されてしまうかも知れません。