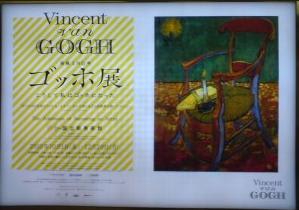 昨日、六本木の国立新美術館で開催中の『没後120年 ゴッホ展 こうして私はゴッホになった』に行って来た。
昨日、六本木の国立新美術館で開催中の『没後120年 ゴッホ展 こうして私はゴッホになった』に行って来た。
ひと月以上前に新聞店から招待券を貰っていたのだが、私がずっと体調がすぐれなかった為に延び延びになっていた。昨日も咳がまだ出る状態だったが、会期末に近づくにつれ混雑が酷くなることを予想して、思い切って行ってみた。今年は前半のオルセー展を、これまた股関節の故障で見逃してしまったので、少しくらい無理をしないと殆ど見ず終いで1年が終わってしまいそうなのが何とも悔しかったのだ(咳は最小限に留めたつもりだが、会場でご一緒した方々、お許しを)。
ゴッホは大好きな画家のひとりだ。その作品は何度見ても飽くことがない。見る度に新たな感動がある。発見がある。国内外で何度、彼の作品との出会いを、或いは再会を喜んだか知れない。 私とゴッホとの出会いは小学校5年生の時まで遡る。図画工作の時間に、鑑賞文の対象作品に選んだのが、彼の《アルルの跳ね橋》だったのだ。確か、学年雑誌に掲載されていた。明るい陽光の下で跳ね橋を中心に描かれる、外国の長閑な風景。一枚の絵を(雑誌に掲載された写真ながら)隅から隅までじっくりと見入って、作品の世界に深く思いを馳せたのは、この作品が初めてだった。
私とゴッホとの出会いは小学校5年生の時まで遡る。図画工作の時間に、鑑賞文の対象作品に選んだのが、彼の《アルルの跳ね橋》だったのだ。確か、学年雑誌に掲載されていた。明るい陽光の下で跳ね橋を中心に描かれる、外国の長閑な風景。一枚の絵を(雑誌に掲載された写真ながら)隅から隅までじっくりと見入って、作品の世界に深く思いを馳せたのは、この作品が初めてだった。 また、「自分の履いている靴を描く」と言う授業で作例として挙げられた作品も、ゴッホの《古靴》(1886)と言う作品だった。持ち主の人となりまで見えて来るような履き崩した靴の描写は、子供の目にも衝撃的だった。私の中で「物を描く時には、ここまで描き込まなくてはならない」と言う基準にもなった絵である。よく見ると、両方共左足用の靴に見える。一説には、ゴッホと弟テオの靴を描いたのではと言われている。
また、「自分の履いている靴を描く」と言う授業で作例として挙げられた作品も、ゴッホの《古靴》(1886)と言う作品だった。持ち主の人となりまで見えて来るような履き崩した靴の描写は、子供の目にも衝撃的だった。私の中で「物を描く時には、ここまで描き込まなくてはならない」と言う基準にもなった絵である。よく見ると、両方共左足用の靴に見える。一説には、ゴッホと弟テオの靴を描いたのではと言われている。 私が国立西洋美術館で初めて見た企画展もゴッホ展である。と言うより、地方出身の私には、これが本格的な美術館で初めて見た大規模な展覧会だった。その時に買ったカタログは今も宝物だ。その後、新婚旅行先のパリでも、オルセー美術館で開催されていたゴッホ展を見た。展覧会の開催の時期を選んで旅行に行ったわけではなかったが、現地で開催を知って、フリータイムには迷わずそのゴッホ展へ行った。その時に買った展覧会ポスターは今も額装してダイニングの壁に掛けてある。
私が国立西洋美術館で初めて見た企画展もゴッホ展である。と言うより、地方出身の私には、これが本格的な美術館で初めて見た大規模な展覧会だった。その時に買ったカタログは今も宝物だ。その後、新婚旅行先のパリでも、オルセー美術館で開催されていたゴッホ展を見た。展覧会の開催の時期を選んで旅行に行ったわけではなかったが、現地で開催を知って、フリータイムには迷わずそのゴッホ展へ行った。その時に買った展覧会ポスターは今も額装してダイニングの壁に掛けてある。
今回の展覧会は、ゴッホの母国であるオランダの、ゴッホ・コレクションの中核を成す2つの美術館、「ヴァン・ゴッホ美術館」と「クレラー・ミュラー美術館」からの出品が核となっている。実は両美術館へは、20年近く前に訪れている。前者はアムステルダム市内に、後者はアムステルダムから列車で1時間ほどの街の広大な国立公園の中にある。
特に後者は最寄り駅から車(自転車で行けないこともないかな?)でないと行けないような奥まった場所にあり、少なくとも私が訪ねた当時は個人で行くにはアクセスが良くなかった。それでもその時行けたのは、夏季に期間限定(2週間)で、列車のチケットと駅からのバスの送迎と公園内のレストランでパスタランチがセットになったものが、アムステルダム中央駅で販売されていたからだ。今は世界的に人気も高まっているので、そういったサービスチケットが常時販売されているかもしれないので、興味のある人は調べてみたら良いと思う。 過去の展覧会の観客動員記録が示すように、世界でも日本人ほどゴッホ好きな国民はいないと言われている。素朴で親しみ易い題材(聖書、神話、歴史等の予備知識なんて要らない)、解説不要な饒舌な色彩(特に渡仏後の明瞭で多彩な色彩のハーモニーが、見る者の心に語りかけて来る)、浮世絵に学んだと言う和テイストな構図(西洋の伝統的絵画技法から逸脱した大胆な構図がシュール、且つ、日本人には親しみ易く、何となく誇らしくもある
過去の展覧会の観客動員記録が示すように、世界でも日本人ほどゴッホ好きな国民はいないと言われている。素朴で親しみ易い題材(聖書、神話、歴史等の予備知識なんて要らない)、解説不要な饒舌な色彩(特に渡仏後の明瞭で多彩な色彩のハーモニーが、見る者の心に語りかけて来る)、浮世絵に学んだと言う和テイストな構図(西洋の伝統的絵画技法から逸脱した大胆な構図がシュール、且つ、日本人には親しみ易く、何となく誇らしくもある![]() )など、日本の一部の美術ファンならずとも魅了される要素を幾つも兼ね備えたのが、ゴッホ作品の魅力なのだろう。
)など、日本の一部の美術ファンならずとも魅了される要素を幾つも兼ね備えたのが、ゴッホ作品の魅力なのだろう。
今回は残念ながら思い出の《アルルの跳ね橋》も《古靴》も出展されていない。しかし、ゴッホのオランダ時代の初期の作品から、フランス時代の晩年の作までを万遍なく揃え、並々ならぬ情熱を持って画家としての10年間を駆け抜けたゴッホの、かけがえのない遺産を目にすることができる展覧会となっている。
《サン=レミの療養院の庭》(1889、クレラー・ミュラー美術館蔵) 今回のお気に入りの1枚!
今回のお気に入りの1枚!
美術館の照明に照らされて、なぜかひと際キラキラと輝き、画中の多彩な色がさんざめいていた《サン=レミの療養院の庭》(左画像)。PCのモニターで、その素晴らしい色彩の競演を再現することは到底不可能。種々の庭木の葉を巧みに描き分けた筆触の妙は、実物の絵の具の厚みを見てこそ堪能できるもの。とにかく本物を目にしたら、目が釘付けになるような美しさだった。この絵に魅了されたのはどうも私だけではないようで、会場の作品の前で暫く佇む人が少なくなかったし、ショップでも絵はがきを買い求める人が多かった。
ここで改めて考えるのは、作品を美術館で見ることの意味だ。夫の選んだ1枚は《草むらの中の幹》だが、草むらの中で堂々と立つ二又に分かれた幹は茶、赤、黄、青、白と様々な色で彩られている。夫はそこが気に入ったらしく「画家の眼って変わっているんだよ。一般の人間には見えないもの、色が見えるらしい」と笑った。 その言葉に私はハッとした。正にそうなのだ。私達は、画家の眼を通して、この世界を見ているのだ。それは見慣れたはずの世界の、自分では想像もつかない新しい姿とも言える。そして、画家自身がその独特の眼で見た世界を、精魂込めて画布上で再現した作品は、その実物を肉眼で直接見てこそ、その本領を理解できるのだと思う。実際、肉眼ではくっきりと色分けできる幹の木肌が、今回アップロードした画像(右上)では不鮮明で、夫の感動は第三者に伝わりづらい状況だ。
その言葉に私はハッとした。正にそうなのだ。私達は、画家の眼を通して、この世界を見ているのだ。それは見慣れたはずの世界の、自分では想像もつかない新しい姿とも言える。そして、画家自身がその独特の眼で見た世界を、精魂込めて画布上で再現した作品は、その実物を肉眼で直接見てこそ、その本領を理解できるのだと思う。実際、肉眼ではくっきりと色分けできる幹の木肌が、今回アップロードした画像(右上)では不鮮明で、夫の感動は第三者に伝わりづらい状況だ。
そうした実物とのギャップは印刷画像でも顕著だ。例えば、ルオーの厚く塗り重ねた絵の具の質感や、そのボリュームがもたらす迫力は、実物を目の前にしてこそ感じられるもので、そこで初めて、なぜ彼がそこまでして絵の具を厚く塗り重ねたのかが、鑑賞者には納得できるものなのではないだろうか?表面がつるんとした画集では、ルオー作品の何十分の一の魅力も伝えることはできまい。
会期も後半に入って、休日のゴッホ展の会場内は作品の前に人波が2重3重にできる混雑ぶりだったが、そんな中で小学生の姿もチラホラと見られた。案の定、大人達の高い壁に阻まれて、せっかくの素晴らしい作品も、子供達には見づらい状況だった。こういう時は、彼らが視界を遮ることは殆どないのだから、大人は大人らしい懐の深さを見せて、子供達を作品の前に立たせてあげて欲しいと思う。
さらに言わせて貰えば、ゴッホの絵は子供達にこそ見て貰いたい。子供達には、エネルギーのほとばしるゴッホの作品から彼が絵に傾けた情熱を、夢中になれることに出会えた彼の人生から生きることの素晴らしさを、是非、感じ取って欲しいと私は思っている。その為には、新宿の損保ジャパン東郷青児美術館のように、休館日に子供達だけの鑑賞日を設けるのもひとつの方法だろう(その際は、学校の校外学習としての位置づけで、引率教師の管理の下、ボランティア等の助けを借りて見学して貰う)。混雑必至の企画展では今後、そういった美術館側の配慮も必要なのではないか?
生前、僅か1枚しか売れなかったゴッホの作品。ゴッホは失意のうちにこの世を去ったのかもしれないが、彼の作品が大量にまとまって遺族(弟テオの妻)の元に残されたが故に、それらは個人蔵として散逸することも、個人宅に秘匿されることも殆どなく、クレラー・ミュラー美術館創設者夫妻をはじめとする、”画家ゴッホの発見者”の尽力もあって、今日では美術館で日々多くの人々の目に触れられ、感動を与えている。彼の人生に思いを馳せながら、彼が多くの作品を遺してくれたことに感謝しながら、ひとつひとつの作品を見てみるのも、良いのかも知れない。
会期は12月20日(月)まで。火曜日定休。
◆国立新美術館 ゴッホ展公式サイト
以下のリンク記事は、ゴッホやクレラー・ミュラー美術館、及びオランダにまつわるエピソードを綴ったもの。興味があれば。
◆「オランダと私」(はなこのアンテナ@ココログ)
もし時間があれば、改めて《アルルの寝室》や2枚の自画像についても言及してみたい。
最新の画像[もっと見る]
-
 ノロウィルスの流行で思うこと
2時間前
ノロウィルスの流行で思うこと
2時間前
-
 今朝2025年2月20日(木)の富士山🗻
1週間前
今朝2025年2月20日(木)の富士山🗻
1週間前
-
 映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
-
 映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
-
 映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
-
 映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
-
 映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
映画『アプレンティス〜ドナルド・トランプの創り方』
2週間前
-
 今日は虫干し☺️
3週間前
今日は虫干し☺️
3週間前
-
 今日は虫干し☺️
3週間前
今日は虫干し☺️
3週間前
-
 Q地球🌏は誰のもの?A誰のものでもない
3週間前
Q地球🌏は誰のもの?A誰のものでもない
3週間前















