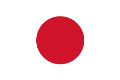
2006年1月1日の新聞に日本経団連の御手洗富士夫会長の今後10年間のヴィジョン「希望の国、日本」に関する記事が載っていた。経団連の「希望の国」は安倍・自公政権の「美しい国」への応援歌であろう。
ひところ「交通安全宣言の町」という看板をよく見かけたが、これは交通安全のためのマナーがよく守られている町です、と言う意味ではなく、逆に、交通事故の絶えない町ですよ、という表明であった。「美しい国」も「希望の国」も、どうやら日本がそのような国ではないことの表明なのだろう。「この国には何でもある。ただ希望だけがない」という、村上龍の『希望の国のエクソダス』が書かれたのは、もうかなり前のことだ。
「希望の国」は経団連のホームページで前文が読める。その文章の「おわりに」には次のように書かれている。
「異邦を訪れた際、子どもたちの目を見れば、その国が分かるという人がいる。これからのびていく国の子どもたちの瞳は澄み輝き、たとえ貧しくても誇りと自信に溢れているという。日本の子どもたちの瞳に輝きが欠けているならば、これを取り戻すことは、われわれ世代の最も重い課題である」
ま、この程度の観察力、事実掌握力、分析力、知性で書かれた文書である。一読を薦めるつもりはない。新聞によると、話は産業力の強化に尽きるが、企業経営とは関係のない①企業や官庁が旗日だけでなく日常的に日の丸を掲げ、君が代を斉唱する②愛国心・公徳心の涵養③共同体重視の価値観、などを提唱した。さらに、憲法を改正して「戦力不保持」を見直し、自衛隊の保持を明確化すると提言した。
朝日新聞の記者はさすがに御手洗ヴィジョンにうんざりしたようで「安倍政権とともに愛国心や日の丸、君が代を前面に押し出すことで為政者と経営者への批判を封じ、『お上』に従順な国民、社員に仕立てあげようとしている印象がぬぐえない」と実にまっとうな感想を、解説に書いていた。
比較政治学と国際関係論をしばらく生業にした筆者は、スハルト政権下の権威主義政治の分析をしたことがある。インドネシアには「パンチャシラ」という名の建国5原則があって、スハルト政権下ではスハルト大統領がそのパンチャシラの解釈権を独占していた。
スハルト政権は1978年からパンチャシラ道徳向上運動(Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, P4)と称する官製運動を始めた。パンチャシラ道徳向上運動はまず公務員を対象にまり、社会の指導者、ジャーナリスト、イスラム教師、主婦、大学生、若者へと徐々に拡大された。この研修は数日間にわたり、市民には歓迎されなかった。彼らはP4を"pergi pagi, pulang petang" (朝出て夕方帰る)ともじり、コースの内容の退屈さを冷やかした。後に「フォルム・クアディラン」という週刊誌が、1990年代の中ごろになって、スハルト政権の閣僚のどのくらいがP4を受講しているのか調べた。当時の閣僚39人中、有力閣僚でのちにスハルト氏の後をついで大統領になったブハルッディン・ハビビ研究技術相をふくむ閣僚10人もがP4コースを修了していないことを暴露した。このことからわかるように、官製道徳普及運動はよき指導者やよき統治者を育成することが目的でなく、統治しやすいよき民を育てるのが目的である。
妻以外の女性と国家公務員住宅に入居していた政府税調会長が辞任したが、その税調で決まったことといえば、企業向けの減税メニュー。減価償却制度の拡充、内部留保金への課税見直し、ベンチャー企業への投資を優遇する税制など。一方、今年から所得・住民税の定率減税が全廃され、例えば、年収700万円の夫婦・子ども2人の家庭で約41,000円の負担増になるといわれている。
世の中には強いものと弱いものがいる。弱い者に対して援助や保護の手を差し伸べるためには、まず国家財政が豊かでなくてはならない。国家が豊かになるためには、強い者がしっかり稼いでくれるような環境づくりが必要だ。企業活動が活発になり生産力が増大すれば、その分税収入がふえる。そういうわけで、自由競争で一時的に格差は増大するが、最終的には格差縮小へと向かう。
まあ、以上のような論理をいともたやすく呑んでくれる国民や社員にしてしまいたい、ということであろう。
性悪な輩ほど性善説の普及に熱心だ。
(花崎泰雄 2006.1.3)
ひところ「交通安全宣言の町」という看板をよく見かけたが、これは交通安全のためのマナーがよく守られている町です、と言う意味ではなく、逆に、交通事故の絶えない町ですよ、という表明であった。「美しい国」も「希望の国」も、どうやら日本がそのような国ではないことの表明なのだろう。「この国には何でもある。ただ希望だけがない」という、村上龍の『希望の国のエクソダス』が書かれたのは、もうかなり前のことだ。
「希望の国」は経団連のホームページで前文が読める。その文章の「おわりに」には次のように書かれている。
「異邦を訪れた際、子どもたちの目を見れば、その国が分かるという人がいる。これからのびていく国の子どもたちの瞳は澄み輝き、たとえ貧しくても誇りと自信に溢れているという。日本の子どもたちの瞳に輝きが欠けているならば、これを取り戻すことは、われわれ世代の最も重い課題である」
ま、この程度の観察力、事実掌握力、分析力、知性で書かれた文書である。一読を薦めるつもりはない。新聞によると、話は産業力の強化に尽きるが、企業経営とは関係のない①企業や官庁が旗日だけでなく日常的に日の丸を掲げ、君が代を斉唱する②愛国心・公徳心の涵養③共同体重視の価値観、などを提唱した。さらに、憲法を改正して「戦力不保持」を見直し、自衛隊の保持を明確化すると提言した。
朝日新聞の記者はさすがに御手洗ヴィジョンにうんざりしたようで「安倍政権とともに愛国心や日の丸、君が代を前面に押し出すことで為政者と経営者への批判を封じ、『お上』に従順な国民、社員に仕立てあげようとしている印象がぬぐえない」と実にまっとうな感想を、解説に書いていた。
比較政治学と国際関係論をしばらく生業にした筆者は、スハルト政権下の権威主義政治の分析をしたことがある。インドネシアには「パンチャシラ」という名の建国5原則があって、スハルト政権下ではスハルト大統領がそのパンチャシラの解釈権を独占していた。
スハルト政権は1978年からパンチャシラ道徳向上運動(Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, P4)と称する官製運動を始めた。パンチャシラ道徳向上運動はまず公務員を対象にまり、社会の指導者、ジャーナリスト、イスラム教師、主婦、大学生、若者へと徐々に拡大された。この研修は数日間にわたり、市民には歓迎されなかった。彼らはP4を"pergi pagi, pulang petang" (朝出て夕方帰る)ともじり、コースの内容の退屈さを冷やかした。後に「フォルム・クアディラン」という週刊誌が、1990年代の中ごろになって、スハルト政権の閣僚のどのくらいがP4を受講しているのか調べた。当時の閣僚39人中、有力閣僚でのちにスハルト氏の後をついで大統領になったブハルッディン・ハビビ研究技術相をふくむ閣僚10人もがP4コースを修了していないことを暴露した。このことからわかるように、官製道徳普及運動はよき指導者やよき統治者を育成することが目的でなく、統治しやすいよき民を育てるのが目的である。
妻以外の女性と国家公務員住宅に入居していた政府税調会長が辞任したが、その税調で決まったことといえば、企業向けの減税メニュー。減価償却制度の拡充、内部留保金への課税見直し、ベンチャー企業への投資を優遇する税制など。一方、今年から所得・住民税の定率減税が全廃され、例えば、年収700万円の夫婦・子ども2人の家庭で約41,000円の負担増になるといわれている。
世の中には強いものと弱いものがいる。弱い者に対して援助や保護の手を差し伸べるためには、まず国家財政が豊かでなくてはならない。国家が豊かになるためには、強い者がしっかり稼いでくれるような環境づくりが必要だ。企業活動が活発になり生産力が増大すれば、その分税収入がふえる。そういうわけで、自由競争で一時的に格差は増大するが、最終的には格差縮小へと向かう。
まあ、以上のような論理をいともたやすく呑んでくれる国民や社員にしてしまいたい、ということであろう。
性悪な輩ほど性善説の普及に熱心だ。
(花崎泰雄 2006.1.3)











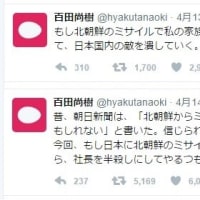

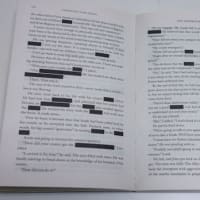
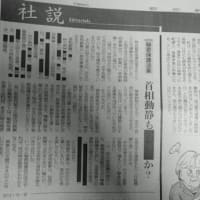










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます