タイが雨季の終わりの水害に見舞われた。チャオプラヤ川流域のアユタヤの工業団地にある日系企業が、直接の浸水被害や部品調達難などで操業停止追い込まれたと、日本の新聞各紙が伝えた。日本の新聞だからトヨタ、 ホンダ、三菱などの自動車メーカーのほか、ニコン、パナソニック、食品・飲料の日本ハム、味の素、ヤクルト、ファミリーマートなどの操業停止・閉店を詳しく伝えている。
バンコク・ポスト紙によると、今回の水害で900以上の工場が操業し、20万人の労働者が影響を受けたたそうだ。だが、例によってそうした全体像は、日系企業の被害ばかりに焦点をあてた日本の報道でははしょられていてなかなかわかりにくい。
チャオプラヤ川の下流にある首都バンコクにも水害の危機が迫っている。外国資本は、この水害をどう乗り切るか、首相になったばかりのインラック・シナワットの手腕を注視している、と大げさな物言いをする外国メディアもある。
雨季のバンコクはしばしば水害に見舞われてきた。運河を掘ってチャオプラヤ川から水を引き込んで水運のネットワークをはりめぐらせていたバンコクはかつて東洋のベニスと称された。ベニスと同じようによく水浸しになった。
ベトナム戦争のころ、米はタイ東北部にB52の基地を作ることを認めてもらい、ベトナムじゅうたん爆撃の基地にした。タイは見返りに米国から提供された資金援助でバンコクの運河を埋め立てて道路にした。そして、日本がその道路を走らせる自動車をタイ人に売った。何十年も前の冗談とも本当ともつかない伝聞である。
バンコクの平地とチャオプラヤ川の水面は高低差があまりなく、川が増水する雨季には、水が市内にあふれ出ていた。チャオプラヤ川のほとりにある、かの5つ星ホテル、マンダリン・オリエンタル・バンコクの前の通りも水浸しになり、宿泊客がボートでホテルに出入りした。
日本の急流が作り出すような急性の水害が洪水(flood)で、緩やかなチャオプラヤの水位が徐々に上昇してやがて陸地を浸してゆくような水害は溢水(inundation)という。タイの水害は溢水で、この溢水のゆるやかな速度にあわせて“浮稲”がその背をのばすことができた。日本のようなあっという間の洪水だったら、さしもの浮稲も水中に没するだろう。
さて、タイ王国大使館の広報サイトによると、世界で一番広い浮稲の田んぼをもっているのはバングラデシュだ。バングラデシュも水害で有名な国だ。2番目がインド。タイは3番目になる。そのあと、ベトナム、ミャンマーと続く。
今回水害に見舞われたバンコク北方のアユタヤはバンコク王朝の前のアユタヤ王朝の都があったところだ。アユタヤ王朝の前の王朝はアユタヤ北方のスコータイ王朝である。スコータイ王朝の有名なラムカムヘン大王の碑に「ナイナームミープラー、ナイナーミーカーオ(水に魚あり、 田に稲あり)と彫られている。タイの豊かさを讃えたとされる有名な言葉で、たいていのタイ語の入門書に引用される。
農業国タイの豊かさを支えたのはチャオプラヤ川流域のデルタ地帯だ。雨季のチャオプラヤの溢水が稲を育てた。
今回のアユタヤの水害は20年にいちどあるかないかの規模のものだとされる。雨の降り方もさりながら、チャオプラヤの溢水がこれほどの大騒ぎになったのは、タイが工業国へと確かな変身をとげていることの証でもある。
(2011.10.15 花崎泰雄)











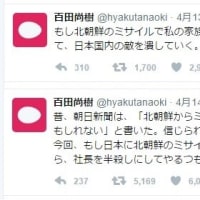

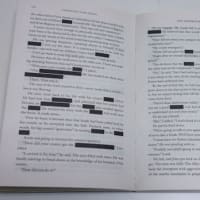
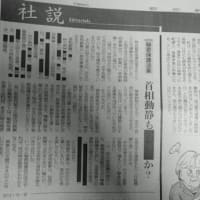










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます