ニューヨークのウォール街で始まった失業や格差に抗議する若者たちの小さなデモが、次第に膨れ上がった。ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト、ニコラス・クリストフによると、若者たちがOccupy Wall Street運動を繰り広げるさなか、付近のピザ屋がOccupy Specialとなづけたピザパイを売り出した(2011年10月1日)などと、初めのうちはお祭り見物気分だった。マイケル・ムーア、ジョセフ・スティグリッツ、ジョージ・ソロスらが激励・声援、同情的なコメントを述べた。やがてデモはボストンなど全米のいくつかの都市に広がり、オバマ大統領が「国民の不満の表れ」と発言するにいたり、政治問題になった。日本の新聞も「金融街デモを『反市場』に広げないために」(日本経済新聞10月8日社説)や「ウォール街デモ――『99%』を政治の力に」(朝日新聞10月9日付社説)などと、本気で取り上げる姿勢を見せ始めた。
若者の雇用を促進させるためにフランス政府が、従業員20人以上の企業が26歳未満の従業員を採用する場合、試用期間の2年以内であれば理由を告げずに自由に解雇することを認める「初期雇用契約」を打ち出したさい、労働組合や若者はこれに反対して大規模なストライキとデモを繰り広げ、政府に法案を撤回させた。2006年のことだった。フランスでは無期限雇用契約が一般的で、このため雇用に慎重になっている企業が多く、これが若者の失業拡大の一因になっているとして、企業側の雇用促進をねらった法案だった。だが、働く側は雇用促進より無期限雇用の慣行が崩されることの方を重要視した。
2010年にはイギリスやイタリアで学費値上げ反対のデモがあった。赤字財政に苦しむ政府の大学補助金の削減と学費値上げの動きに反対する学生が街頭に出た。筆者はこの時イタリア旅行中で、ベニスのサンタルチア駅発車の列車がデモで止められ、立ち往生してしまった。日本、アメリカ、韓国に比べれば、これらの国の高等教育費の個人負担は極めて低い。
そうした若者の抗議が、今度は米国で広がっているわけだ。銀行は政府によって救済されるが、われわれは救済されない。日経新聞の社説によると「米国では、上位1%の人たちが国民全体の所得総額の20%を占める。全体の失業率は9.1%だが、25歳未満の失業率は17.7%。欧州でも英国の若年失業率は20.9%、スペインは46.2%に達する」そうだ。米国のインターネット新聞『ハフィントン・ポスト』(2011年5月13日)によると、2011年に大学を卒業する学生は平均で27,200ドルの学生ローンを借金として抱えて社会に出てゆくそうだ。そのうえ、就職難などが理由で卒業後親元に帰る学生も前代未聞の85%に達する見込みという調査会社の数字も出されている。CNNはこうした親元に帰る学生をBoomerang Kids あるいはBoomerangerとよんでいた。
日本政府の『子ども・若者白書』(2011年版)によると、2010年の日本の完全失業率は5.1%だが、これを年齢層でみると25-29歳では7.1%、20-24歳では9.1%、15-19歳では9.8%になる。日本の場合、安定的な終身雇用の機会は学校卒業の時がほとんどだから、この若年層の失業率は見かけよりきつい。同白書によると、15-24歳のいわゆる非正規雇用率は30.4%になる。
日本の若者が街頭で異議をとなえないのは、日本社会の不公正の現状がまだ受忍限度内にとどまっているためなのか、日本国民の受忍能力が他国民に比べて高いためなのか――議論のあるところだろう。
日本では政府のガバナンス(統治能力)は低く、国民のガバナビリティー(統治容易性=注)は高い。ありていに言えば、唯々諾々とお上の決定に従うという従順さがこの国の人々の特徴である。とはいえ、発火点が存在しないわけではないだろう。人間は年を重ねると物事の見方が悲観的になるようで、国債漬けの日本がギリシャ化するのも、虐待されつつも政治的ひきこもりを続けている若者が久しぶりに街頭に出て、オキュパイが売られるのも時間の問題のように、筆者には思える。
<注>日本では英語国と異なって、以前はgovernabilityがgovernanceの意味で使われていた。その例を国会審議から紹介する。「さて、最後に三木総理、議会運営において、ロッキード究明において、経済運営において、日本の民主主義は死に瀕しています。苦し紛れに、あなたは、野党の担政能力が欠けているなどということを口実にされます。しかし、今日の政治の乱れは、目の前の参議院の保革伯仲が物語るように、すでに一党支配の条件を失った自民党が、それにもかかわらず強権をもってこれを推し進めようとするところにあるのであります。ガバナビリティーの喪失とは、一総理の統治能力の欠如などではなく、言葉の正しき意味において自民党全体の当事者能力の欠如であります。議会の子としての三木さんは、生きたり、死んだり、また生きたり、そうした有為転変ではなく、まさに死力を尽くして、いま民主主義の蘇生のために立つべきであります。(1976年9月28日、参院本会議 上田哲質問)
(花崎泰雄 2011.10.9)











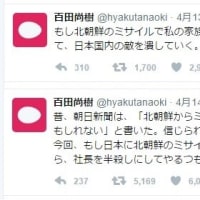

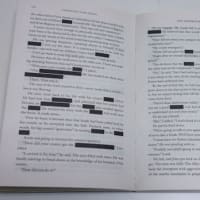
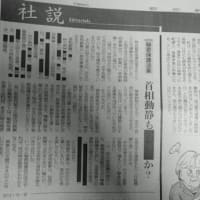










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます