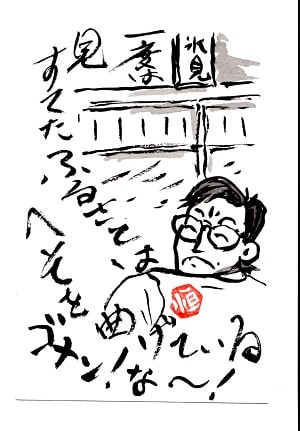京都から新快速で姫路まで。姫路からバスに乗り四十数分揺られれば、誠の故郷に着く。まずは実家へ直行して、五年に渡った東京暮らしのストレスを癒すのが先決だった。仕事は、そのあとでゆっくりと探すつもりでいた。
誠は東京に出る前、現在はSホテルチェーンの新姫路Sホテルに変身している、当時の姫路Lホテルのレストランに勤めていた。誠が東京行きを前倒しで踏み切ったのは、Lホテルの思いがけない倒産だった。
倒産で職場を誠と同様に追われる羽目になった、その頃のチーフや同僚は神戸や播磨近辺に四散して働いている。彼らのツテを頼れば、就職など、そう悩む必要もあるまい。
実家にたどり着いたのは二時過ぎだった。バス停から十二,三分は歩いた。下着や着替えを詰め込んだボストンバッグを抱えてだから、結構大変である。秋口に差し掛かった時候のおかげで、汗をかかずに済んだのは幸運だった。
中途半端な時間になったせいもあり、家には誰もいなかった。
東京を離れる直前に、東京駅から長距離電話で、帰郷することを連絡しておいたが、忙しく働いている母や兄夫婦の誰かに、誠を迎えるべくワザワザ在宅しておいてくれと望むのは、身勝手過ぎた。父は誠が高校生の折に、交通事故で亡くなっている。働き手がひとり欠けた状況は、誠が考える以上に大変なのだ。無理はいえない。
鍵のかかった玄関と睨めっこである。多分に期待していた家族と感激の再開も何もあったものじゃなかった。それでもホッとするものがあった。故郷は格別だ。我が家は、やはり最高だ。
家族の誰かが帰ってくるすれば、早くても四時ごろになるだろう。遅くなれば六時を過ぎる可能性もある。しかし、誠は焦らず待つ態勢にあった
Uターンして県道まで出れば、左手五十メートル先に喫茶店が一軒あることはあるが、もう一度逆戻りするのは億劫だった。それに誠は、懐かしさを醸し出す我が家の前を離れる気力は、微塵もなかった。
誠は玄関脇へ無造作に放り出してあるダンボールの箱を潰すと、それを敷物代わりに尻を下した。新宿歌舞伎町界隈で飲み過ぎて終電に間に合わなくなったとき、地下鉄の入り口付近で、同じようにして夜を過ごしたのを思い出す。誠のアパートは、小田急沿線にあったのである。
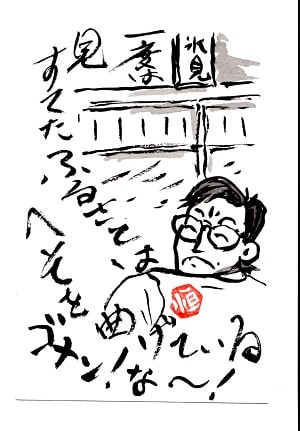
誠は東京に出る前、現在はSホテルチェーンの新姫路Sホテルに変身している、当時の姫路Lホテルのレストランに勤めていた。誠が東京行きを前倒しで踏み切ったのは、Lホテルの思いがけない倒産だった。
倒産で職場を誠と同様に追われる羽目になった、その頃のチーフや同僚は神戸や播磨近辺に四散して働いている。彼らのツテを頼れば、就職など、そう悩む必要もあるまい。
実家にたどり着いたのは二時過ぎだった。バス停から十二,三分は歩いた。下着や着替えを詰め込んだボストンバッグを抱えてだから、結構大変である。秋口に差し掛かった時候のおかげで、汗をかかずに済んだのは幸運だった。
中途半端な時間になったせいもあり、家には誰もいなかった。
東京を離れる直前に、東京駅から長距離電話で、帰郷することを連絡しておいたが、忙しく働いている母や兄夫婦の誰かに、誠を迎えるべくワザワザ在宅しておいてくれと望むのは、身勝手過ぎた。父は誠が高校生の折に、交通事故で亡くなっている。働き手がひとり欠けた状況は、誠が考える以上に大変なのだ。無理はいえない。
鍵のかかった玄関と睨めっこである。多分に期待していた家族と感激の再開も何もあったものじゃなかった。それでもホッとするものがあった。故郷は格別だ。我が家は、やはり最高だ。
家族の誰かが帰ってくるすれば、早くても四時ごろになるだろう。遅くなれば六時を過ぎる可能性もある。しかし、誠は焦らず待つ態勢にあった
Uターンして県道まで出れば、左手五十メートル先に喫茶店が一軒あることはあるが、もう一度逆戻りするのは億劫だった。それに誠は、懐かしさを醸し出す我が家の前を離れる気力は、微塵もなかった。
誠は玄関脇へ無造作に放り出してあるダンボールの箱を潰すと、それを敷物代わりに尻を下した。新宿歌舞伎町界隈で飲み過ぎて終電に間に合わなくなったとき、地下鉄の入り口付近で、同じようにして夜を過ごしたのを思い出す。誠のアパートは、小田急沿線にあったのである。