原口総務大臣は、障害者を「チャレンジド」と言うように省内にも
徹底させているそうだ。
しかし、一昨日の推進会議で「障害者」の表記について、いくつか
の意見があったが、「チャレンジド」は不評だった。
なぜか。チャレンジというのは障害、社会の障壁にチャレンジする
ことを指している。チャレンジするのを支援する、理解すると言う
ような意味合いがあるようだ。しかし、チャレンジすべきは社会の
方ではないか、障害者が障害を持つが故になぜ普通の人はしなくて
も良い「チャレンジ」をしなくてはならないのかという疑問がある。
障害者と言う言葉もあえて使う障害者もいる。社会によって障害を
持たされた人(Disabled person)という意味で、本来その人
には障害があるとは考えない、社会モデルとして理解しているとい
うことだ。
しかし、障害者問題は言葉の表記や語感だけで解決する問題ではな
いので、施策の転換を議論するうちに国民の中に合意が形成される
だろう。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「チャレンジド」という言葉、これは神様から生まれながらにして
挑戦をする課題をもらった人たち、生まれたときに様々な課題に挑
戦する人たち、この人たち を納税者に。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kyoryoku/aisatsu.htm
徹底させているそうだ。
しかし、一昨日の推進会議で「障害者」の表記について、いくつか
の意見があったが、「チャレンジド」は不評だった。
なぜか。チャレンジというのは障害、社会の障壁にチャレンジする
ことを指している。チャレンジするのを支援する、理解すると言う
ような意味合いがあるようだ。しかし、チャレンジすべきは社会の
方ではないか、障害者が障害を持つが故になぜ普通の人はしなくて
も良い「チャレンジ」をしなくてはならないのかという疑問がある。
障害者と言う言葉もあえて使う障害者もいる。社会によって障害を
持たされた人(Disabled person)という意味で、本来その人
には障害があるとは考えない、社会モデルとして理解しているとい
うことだ。
しかし、障害者問題は言葉の表記や語感だけで解決する問題ではな
いので、施策の転換を議論するうちに国民の中に合意が形成される
だろう。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「チャレンジド」という言葉、これは神様から生まれながらにして
挑戦をする課題をもらった人たち、生まれたときに様々な課題に挑
戦する人たち、この人たち を納税者に。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kyoryoku/aisatsu.htm










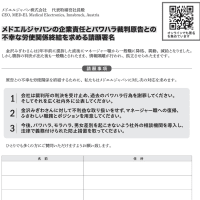

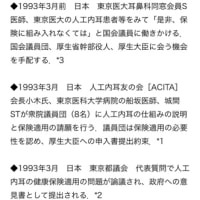






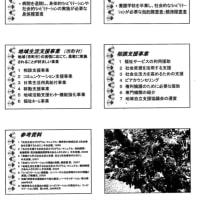

♪ことを指している。チャレンジするのを支援する、理解すると言う
♪ような意味合いがあるようだ。しかし、チャレンジすべきは社会の
♪方ではないか、障害者が障害を持つが故になぜ普通の人はしなくて
♪も良い「チャレンジ」をしなくてはならないのかという疑問がある。
これは、単純に量の問題ですね。障がいのある者(甲)は、社会(乙)よりも量的に少ない者、つまりマイノリティです。
マイノリティである甲が何もしなくても乙に不都合はないが、乙が何もしないと甲に不都合である、という関係にあるから、不都合な者=甲がチャレンジすることになります。
少なくとも、障壁ができてしまったのは、その障壁が甲に不都合であっても、乙に不都合がなかったせいです。
では、このままでよいのか、となると、別の問題になります。
おっしゃるように乙が(または乙も)チャレンジするべきではないか、となると、乙がチャレンジしなければならない理由を明らかにしないと。
理由はある、と思いますが、コンセンサスを得られているかどうか。得られていないから、依然として乙によるチャレンジが(ほとんど)行われていないのですね。
聴覚障害者の場合、耳が聞こえないけど音楽をつくる、聞こえないけど、声優をやるというような意味合いに聞こえてしまいます。
上記のようなチャレンジは周りの理解、支援が
ないと超えられないですよね。
そういう意味で原口総務大臣の捕らえ方は
一歩先に行ってしまってますよね。
目の前の課題が解決されないと言わない言葉
のような気がしますね。
周りの理解があって初めてチャレンジできるからチャレンジドといえる
ということと
障害者をチャレンジドと呼ぼうということとは
また別の話で、書いたのは単なるイメージの話です。
よろしくお願いいたします。