
先日のNHKのテレビで人工内耳を装用した子供たちの問題を取り上げているのをちらと見たが、ちょっと違和感を感じた。
テレビではどうして人工内耳と手話、ろうと人工内耳を対比させるのかということだ。
いま、人工内耳も手話も、読話も補聴器さえも一緒に使う子供たちが育っている。
従来の聴覚障害者像ではとらえられない子供たちだ。
スーパー難聴者だ。ITも使いこなせば新人類だろう。
今重要なことは手話か人工内耳かではなく、それを止揚した聴覚障害者の生きる道をしめすことであり、聴覚障害であるか否かを脱却した人間のあり方を問うことだ。
それが、社会モデルであり、国際生活機能分類ICFが解明する。
ラビット 記
テレビではどうして人工内耳と手話、ろうと人工内耳を対比させるのかということだ。
いま、人工内耳も手話も、読話も補聴器さえも一緒に使う子供たちが育っている。
従来の聴覚障害者像ではとらえられない子供たちだ。
スーパー難聴者だ。ITも使いこなせば新人類だろう。
今重要なことは手話か人工内耳かではなく、それを止揚した聴覚障害者の生きる道をしめすことであり、聴覚障害であるか否かを脱却した人間のあり方を問うことだ。
それが、社会モデルであり、国際生活機能分類ICFが解明する。
ラビット 記










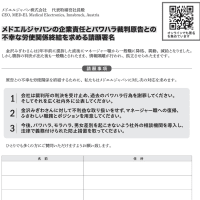

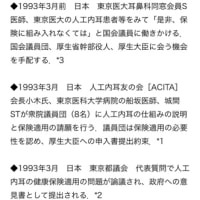






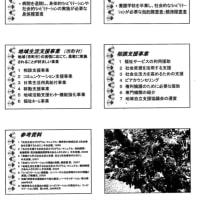

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます