最後の西部劇「ワイルド・バンチ」の鬼才監督の真意に迫る注目の新著
JBPRESS 2019.3.13(水)

サム・ペキンパー監督(左)とウィリアム・ホールデン
かつてはハリウッドの主役であり、ドル箱だった西部劇。何度もアカデミー賞*1に輝いたことのある西部劇。
*1=西部劇でアカデミー賞を受賞した作品は、「シマロン」(1931年、ウエズリー・ラッグルズ監督、リチャード・ディックス主演)、「続・夕陽のガンマン」(1966年、セルギオ・レオーネ監督、クリント・イーストウッド主演)、「ダンス・ウィズ・ウルブズ」(1990年、ケビン・コスナー監督・主演)。
ゲイリー・クーパー、ジョン・ウェイン、クリント・ウッドワードらスターが演ずる保安官やカウボーイに米国人の持つ強さや正義感、優しさを感じ取った日本人も少なくなかったと思う。かくいう筆者もその一人だった。
ところが一世を風靡した西部劇も1960年代後半頃から衰退してしまった。その後も制作はされるのだが、一部例外を除いてそれほど話題になることはなかった。
その要因は公民権法が成立して以降、米社会に人種に対する意識改革が進んだからだとされている。
西部劇では「悪玉」のアメリカ・インディアンは、「先住民族」という表現に代わり、「悪玉」はむしろ先住民族を居住地域から追い払おうとしてきた白人開拓者であるとの認識が定着した。
白人中心主義に対する原罪が問われた(悪いことをしたという認識はあっても白人がそのことについて正式に謝罪したことはない)。
白人たちが迫害し、虐殺したのは先住民族だけではなかった。野生のバッファローを絶滅寸前にまで追い込んだのは白人開拓者だった。自然破壊の張本人だったのだ。
当時、テキサスとメキシコには国境などなかった
日本では、西部劇に引導を渡した「最後の西部劇」と言われているのが1969年に制作された「ワイルド・パンチ」だ。
在ハリウッドの日本人映画通によれば、「最後」とは、西部劇の重要な要素である銃撃戦が、この映画ほど過激なものは以後出てこなくなったという意味と、西部劇にはお決まりのハッピーエンドを抹殺した異色の作品だったことらしい。
(https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/a405359a-0f48-4ac8-ab45-a128df572196.png)
ちなみに「ワイルド・バンチ」は、歴代の西部劇ランキング*2では第17位。
これまで映画評論家の評価は二分されてきた。銃規制に反対する保守派からも過激な暴力表現に対する批判めいた声が出された。銃の怖さが広がるのはヤバイと感じ取ったのだろう。
*2=デジタルメディア世論調査機関「ランカー」の西部劇映画ランキングベストテンは、①「続・夕陽のガンマン」(1966年)②「アウトロー」(1976年)③「許されざる者」(1960年)④「荒野の七人」(1960年)⑤「明日に向かって撃て!」(1969年)⑥「捜索者」(2008年)⑦「夕陽のガンマン」(1965年)⑧「トゥームストーン)」(1993年)⑨「荒野の用心棒」(1964年)⑩「リオ・ブラボー」(1959年)となっている。
(https://www.ranker.com/crowdranked-list/the-best-western-movies-ever-made)
ご覧になった方は覚えていらっしゃるかもしれない。スローモーション撮影による冒頭と最後の壮烈な銃撃シーン。しかもそれが何分も続く。
こうしたサム・ペキンパー監督のバイオレンス描写は何も「ワイルド・バンチ」だけではない。「ゲッタウェイ」(1972年)でも「戦争のはらわた」(1977年)でもその暴力描写は強烈だった。
こうした残酷な作風を好んで撮るペキンパー監督はハリウッドでは「血まみれのサム」(Bloody Sam)と呼ばれた。
監督として精力的な活動を続ける半面、鬼才は映画制作中でもビールを欠かせない。強度のアル中だった。マリファナにも手を出していた。
「ワイルド・バンチ」は、最後に善が勝ち、悪が滅びるというハッピーエンドの伝統的な西部劇ではなかった。
その前に誰が善で誰が悪かもはっきりしない。最後には悪の権化のような主役を除いてみんな死んでしまうのだ。
だが、登場人物の中にはヒローもヒロインもいない。先住民族は出てこないが、メキシコ人がたくさん出てくる。
メキシコ政府軍の将軍もいれば、反政府勢力の戦士も出てくる。貧しい集落に住むメキシコ人の女子供も出てくる。
彼らはブロークンな英語は話さない。みなスペイン語を話す。メキシコ人が皆等身大のメキシコ人として出てくるハリウッド映画は稀有だった。
その理由は、脚本も書いたペキンパーはメキシコが大好きだったからだ。
当時のテキサスとメキシコとの間には、今ドナルド・トランプ大統領が250億ドルかけて建設を目指している「壁」*3などは無論ない。野生の馬もバッファローもそして人間も自由に行き来していた。
*3=250億ドルは壁の建設費用のみ。建設予定用地には私有地が含まれており、その土地の買収には4480億ドルかかるというテキサス州建設専門家の試算もある。
トランプ大統領は、メキシコから不法に入ってくるメキシコ人は「犯罪者」だとのたまうが、当時追っ手を逃れてテキサスからメキシコに入境するのは米国人の方だった。
「ワイルド・バンチ」制作の舞台裏と徹底取材
映画公開から50年経った今春、その「ワイルド・バンチ」を制作した経緯やペキンパー監督の狙いを関係者たちとのインタビューを基に書き上げた本が出た。
著者はテキサス在住の米ジャーナリストのW・K・ストラットン。
オクラホマ州生まれでテキサス育ち。
地方のオクラホマ・セントラル大学を出て、地元紙で勤務しながらボクシングのトレーナーをやり、知り合った全米女子ボクシングチャンピオンになった女性の生い立ちを本にしたこともある。
テキサス州からは一歩も出ず、南部を舞台にスポーツ雑誌に寄稿したりしてきた。本書は3作目だ。
タイトルは、「The Wild Bunch: Sam Peckinpah, a Revolution in Hollywood, and the Making of a Legendary Film」(ワイルド・バンチ:サム・ペキンパー、ハリウッド革命、そしてレジェント映画はいかに作られたのか)だ。
「ワイルド・バンチ」は原案を作ったウォロン・グリーン(もう一人はロイ・シックナー)と監督のペキンパーが共同で脚本を書いた。
主演はウィリアム・ホールデン。助演はアーネット・ボーグナイン。あらすじはこうだ。
テキサス州サンラファエル*4の鉄道事務所に騎兵隊を装った強盗団が入る。鉄道会社は賞金を出して捕まえようとする。
賞金稼ぎの男たちは強盗団を追いかける。銃撃戦の末、生き残った強盗団は国境を越えて、仲間の一人、メキシコ人の郷里の村に逃げ延びる。
*4=テキサス州サンラファエルはトランプ大統領が目指すメキシコとの国境の壁建設地から北に80キロにある。
だが村はメキシコ政府軍が行った反政府分子掃討作戦で焼き尽くされていた。強盗団はメキシコ政府軍の将軍に匿ってくれるように懇願。
将軍は米国の列車を襲い、積んである武器弾薬を盗み出せば匿うと提案。強盗団は首尾よく武器弾薬は手に入れるが、その受け渡しを巡ってメキシコ政府軍との間に激しい銃撃戦となる。
強盗団は主人公を除いて全員射殺される。同様にメキシコ軍200人も壊滅する。主人公はメキシコ反政府勢力の兵士たちに誘われて荒野へ去っていく。
制作を突き動かしたソンミ虐殺
キング暗殺、R・ケネディ暗殺
著者のストラットンは、「ワイルド・バンチ」でペキンパー監督が描きたかったテーマは何かについてこう記している。
「映画というものは常にその世代、その時期に起こっている神羅万象の影響を受けている」
「ペキンパーがこの映画を制作することを決め、俳優やスタッフを選び、メキシコのロケ地に入る数日前に何が起こったか」
「公民権運動の指導者、マーチン・ルーサー・キング師が暗殺された」
「撮影中にはウイリアム・カリー中尉率いる米陸軍小隊がベトナムのソンミ村で無抵抗の村民504人を虐殺するという事件が発覚」
「ソンミ村虐殺の数か月後にはロバート・ケネディ上院議員が大統領選挙中に暗殺されるという事件が起こった」
「『ワイルド・バンチ』は、米国という国が極度に暴力化し、国がよって立つ道徳律が怪しくなってきた当時の状況を反映していた」
「当時、米国には正義と力があるという古きよき神話が危うくなっていた」
「米国人はいけないことだと感じつつもバイオレンスを浮き浮きした気持ちで受け入れていた。正義を貫くためにバイオレンスも仕方がないという雰囲気があった」
「その元凶はベトナムで直面する共産勢力の侵略から南ベトナムを守るという現実にあった。そのシーンは連日のように夕方6時のテレビニュースで流れていた」
著者によれば、「ワイルド・バンチ」が公開された1969年。映画を観たミズーリ州の女性はアメリカ映画協会(MPAA=業界団体)宛に「残虐すぎる映画だ。検閲すべきだ」との抗議文を送りつけた。
カリフォルニア州フレズノでは映画を観た修道女グループが途中退場した。西部劇好きな修道女たちは口々に言った。
「醜くて、ムカつく、百害あって一利なしの血なまぐさい映画だ」
「かってのジョン・ウェインが出る西部劇はどうなってしまったのか」
メディアの映画評論家の中には「この映画はペキンパーのニヒリズムの表現だ」「『血まみれサム』がいつもののようにビールを飲みながら作った駄作」といった一言で片づける者もいた。
それ以上にペキンパー監督の狙いを深読みしようとはしなかった。
60年代に対するセンチメンタル・ノスタルジア
それから50年、ペキンパー監督死後35年経って脚光を浴びているのはなぜか。
南カリフォルニア大学宗教学部講師の宗教学者ポール・グリーソン氏はこう指摘している。
「この映画が注目されているのはニヒリズムなのではなく、当時に対するセンチメンタル・ノスタルジアではないのだろうか」
「友に対する忠誠心や行きどころのない弱者に寄り添おうとする意志。そういった古い価値観が今、見失われていることからくる過去への郷愁とでも言うべきか」
「『ワイルド・バンチ』に出てくる登場人物とは異なるが、(著者の心の中には)映画制作された1960年代末に正義を貫き、バイオレンスの前に倒れたキング牧師やケネディ氏に対するノスタルジアがあるのだと思う」
「映画の登場人物たちのほとんどは犬死したが、キング牧師たちの死は継承者が必要だというメッセージをわれわれに残した」
「50年経った今、われわれは彼らのように正義のために立ち向かうヒローを必要としている」
(https://www.latimes.com/books/la-ca-jc-wild-bunch-peckinpah-history-review-20190226-story.html)
著者も出版社も「ワイルド・バンチ」に関する新著は映画公開50年という節目だからだとしている。果たしてそうなのか。
それともその節目にたまたまドナルド・トランプという「バイオレントで道徳律欠如な大統領」がホワイトハウスに君臨していることと関係があるのか。
こじつけであることを承知で、筆者は3人の米国人に聞いてみた。
2人は「関係あり」とコメント、あとの1人は「分からない」と答えている。前者は民主党支持者、後者は共和党支持者だ。高濱 賛
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55718










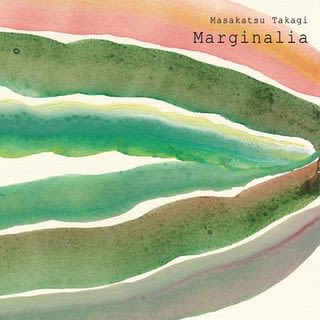

 Utsuwa * The preparatory study of the facade painting | 2018 | © Baptiste François
Utsuwa * The preparatory study of the facade painting | 2018 | © Baptiste François サム・ペキンパー監督(左)とウィリアム・ホールデン
サム・ペキンパー監督(左)とウィリアム・ホールデン




