Wedge infinity2019年3月28日 酒井充子 (映画監督)
私はこれまでの台湾取材で、たくさんの原住民族の方にお会いしてきた。最初の作品『台湾人生』で「台湾の主人は高砂族の原住民たち」と誇りを持って語ってくださったパイワン族の故タリグ・プジャズヤンさんをはじめ、日本語が流暢な人たちは「原住民」を日本語の発音で「げんじゅうみん」と言ったし、私自身も「原住民(族)」という言葉を使ってきた。

©『台湾萬歳』マクザム/太秦
ところが、以前、別のサイトのコラムで台湾の原住民族について言及した際、「原住民(族)」の表記が「差別的なニュアンスを感じる人がいる」として「先住民(族)」と直されて戸惑った。修正の根拠は共同通信社発行の『記者ハンドブック』だという。図書館へ行って開いてみた。「差別語、不快用語」という項目の「人種、民族、地域の表記」の欄に「土人→先住民(族)、現地人」とある。が、「原住民(族)」という言葉は見当たらない。
そもそも、「原住民(族)」という言葉は差別的なのだろうか。というわけで、この「原住民(族)」という呼称について考えてみたい。
「原住民族」は彼ら自身が獲得した呼称
台湾では、太古から台湾に暮らしてきた人びとを「原住民族」と呼ぶ。現在、台湾政府が認定している16部族で約55万人。台湾の全人口のわずか2%ほどだが、17世紀以降、漢民族の移住が盛んになるはるか以前から、彼らは台湾の住人だった。彼らの呼称は時代とともに変遷してきたが、台湾の民主化が進んだ1994年、彼ら自身が主張する「台湾のもともとの主人」という意味の「原住民」が憲法の追加修正条文に明記された。97年には「原住民族」とされ、いまに至る。
彼らが自ら主張する呼称を獲得するまでには、長い道のりがあった。清の時代は「番人」(漢民族化した民族は「熟番」、そうでない民族は「生番」)、日本統治下では当初「蕃人」と呼ばれた。「蕃」は「蛮」の同意語で、「未開の」「野蛮な」といった意味。のちに「高砂族」とされたが、これは台湾総督府が1923年、裕仁親王(のちの昭和天皇)が台湾を訪問したのを記念し、「蕃人」を「高砂族」に改めることを決めたためだ。とはいえ、当時の新聞記事や在台邦人の口から「蕃人」という言葉が消えることはなかった。
第二次世界大戦後、台湾統治を始めた中華民国は、高砂族を「高山族」に変え、のちに「山地同胞(山胞)」とした。台湾のもともとの主人たちは有史以来、時の外来政権により呼称を与えられ、社会の周縁に追いやられ、それらを甘んじて受け入れざるを得ない立場に置かれてきた。2016年、蔡英文総統が就任後、初めて迎えた「原住民族の日」(8月1日)に原住民族の過去四百年の苦難に対して謝罪したことは記憶に新しい。
1980年代に入り、台湾社会全体が民主化への歩みを進める中で、彼ら自身も権利回復運動を展開していく。84年、大学で学ぶ若者や長老教会関係者らが中心となって「台湾原住民権利促進会」を発足させ、88年には17条の「台湾原住民族権利宣言」を発表。「台湾原住民族」の名のもとに、土地の返還や自治の実現などを要求したのだった。
「原住民(族)」という日本語は差別的なのか
それにしても、そもそも、日本語の「原住民(族)」という言葉は差別的なのか。原点、原石、原本などを見ればわかるように、「原」は「もと」や「みなもと」といった意味で、差別的な意味は持たない。国語辞典で「原住民」を調べても、「その土地に、もとから住んでいた民」(広辞苑 第七版)、「(征服者や移住民に対して)もとからその土地に住みついている人々。先住民。」(旺文社国語辞典 第十一版)などと記されており、どこにも差別的な意味は見いだせない。
日本の書物で、「原住民」という言葉を最初に記したのは坪内雄蔵(逍遥)である。1901(明治34)年に出版した『英文學史』(東京専門学校出版部)の第一編「上古期の文学」第一章「英国の原住民及びアングロ、サクソン族」の中で、「英國の原住民と英國の文學史との間には殆ど些の關係も無し」と述べ、そのすぐあとで触れるブリトン族より前に住んでいた民族を「原住民」と呼んだ。さらに坪内は、アングロサクソン族が、「原住民」であるブリトン族を撃退して以降、政治においても文学においても「眞の英國史」が始まったと続ける。本書には、「蠻族」「蕃民」という言葉も出てくるが、明らかに「原住民」と区別して使っていることがわかる。
一方、「先住民」という言葉を探していくと、1907(明治40)年の『地底探検記』(江見水蔭著/博文館)にたどり着く。目次の最初が「先住民の研究」で、「抑も我々大和民族―現在の日本人―その祖先が、此土地に来たらぬ前には、如何なる種族の住民が此所に居たらうか」という課題が掲げられている。明治時代後半の時点で、「原住民」と「先住民」はいずれも「前に住んでいた民族」という意味で使われていた。では、いつから「原住民」に「差別的なニュアンス」が加わったのだろう。
2007年、ある「宣言」が国連総会で採択された。英語で「Declaration on the rights of indigenous peoples」。国際連合広報センターによると、日本では「先住民族の権利に関する宣言」と訳されている。そこからさかのぼること四半世紀、国連の人権小委員会は1982年、この宣言の草案を作成することになる作業グループを設置していた。世界的に「indigenous peoples」の人権問題が注目されるようになった1980年代から、訳語としての「先住民族」が広く使われるようになり、定着していったと言えば言い過ぎだろうか。
かたや「原住民族」は「indigenous peoplesの訳語ではない」という理由で積極的には使われなくなった。そして、同じ「原」という字を使う「原始人」の「未開社会の人間」という負の意味が「原住民」に持ち込まれた結果、「差別的なニュアンス」を背負わされてしまったとは考えられないだろうか。
「すでに滅んでしまった民族」と呼ばないために
「台湾原住民文学選」(草風館)などの翻訳がある天理大学名誉教授の下村作次郎氏によると、台湾研究者の中にも、あえて「先住民族」を使う人もいるそうだ。しかし、下村氏は「彼らが勝ち取った『原住民族』という呼称を尊重したい。どうしても先住民族と言わなければならないなら、“世界の先住民族のうちの、台湾の原住民族”と言います」と話す。そして、「日本語とはいえ、『先住民族』を文字にしたときに、台湾の人がそれを読んでどう感じるか」とも。ある翻訳本のタイトルを付ける際に、「原住民族」という言葉にこだわって取り上げることをためらうメディアがあるのなら、その代わりに「エスニックマイノリティ」という言葉を使って、同書への関心を向けてもらおうと考えたという。
「先住民族」ではなく「エスニックマイノリティ」を選んだのは、台湾で「先住民族」は「すでに滅んでしまった民族」という意味になるからだ。台湾も日本も漢字を使う国である。もちろん、同じ漢字を使っていても意味が違う言葉はたくさんある。しかし、「原住民族」と名乗っている人を「原住民族」と呼ばない理由はない。ましてや、日本語の「原住民族」に差別的な意味はないのだから、わざわざ「すでに滅んでしまった民族」という意味の「先住民族」に言い替える必要などない。
台湾の「原住民(族)」は彼ら自身が獲得した呼称である。もともと日本語の「原住民(族)」に差別的な意味はない。台湾で「先住民(族)」は「すでに滅んでしまった民族」という意味になってしまう。以上の理由から、わたしは台湾の「原住民族」を「原住民族」と呼びたいし、以上の理由を説明しながら、「原住民族」という呼称を使うことを広げていきたいと思っている。もちろん、「先住民族」と呼ぶことを否定しない。「先住民族」と同じように「原住民族」という言葉を自由に使えるようになればいい。読者のみなさんはどのようにお考えだろうか。
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15729
私はこれまでの台湾取材で、たくさんの原住民族の方にお会いしてきた。最初の作品『台湾人生』で「台湾の主人は高砂族の原住民たち」と誇りを持って語ってくださったパイワン族の故タリグ・プジャズヤンさんをはじめ、日本語が流暢な人たちは「原住民」を日本語の発音で「げんじゅうみん」と言ったし、私自身も「原住民(族)」という言葉を使ってきた。

©『台湾萬歳』マクザム/太秦
ところが、以前、別のサイトのコラムで台湾の原住民族について言及した際、「原住民(族)」の表記が「差別的なニュアンスを感じる人がいる」として「先住民(族)」と直されて戸惑った。修正の根拠は共同通信社発行の『記者ハンドブック』だという。図書館へ行って開いてみた。「差別語、不快用語」という項目の「人種、民族、地域の表記」の欄に「土人→先住民(族)、現地人」とある。が、「原住民(族)」という言葉は見当たらない。
そもそも、「原住民(族)」という言葉は差別的なのだろうか。というわけで、この「原住民(族)」という呼称について考えてみたい。
「原住民族」は彼ら自身が獲得した呼称
台湾では、太古から台湾に暮らしてきた人びとを「原住民族」と呼ぶ。現在、台湾政府が認定している16部族で約55万人。台湾の全人口のわずか2%ほどだが、17世紀以降、漢民族の移住が盛んになるはるか以前から、彼らは台湾の住人だった。彼らの呼称は時代とともに変遷してきたが、台湾の民主化が進んだ1994年、彼ら自身が主張する「台湾のもともとの主人」という意味の「原住民」が憲法の追加修正条文に明記された。97年には「原住民族」とされ、いまに至る。
彼らが自ら主張する呼称を獲得するまでには、長い道のりがあった。清の時代は「番人」(漢民族化した民族は「熟番」、そうでない民族は「生番」)、日本統治下では当初「蕃人」と呼ばれた。「蕃」は「蛮」の同意語で、「未開の」「野蛮な」といった意味。のちに「高砂族」とされたが、これは台湾総督府が1923年、裕仁親王(のちの昭和天皇)が台湾を訪問したのを記念し、「蕃人」を「高砂族」に改めることを決めたためだ。とはいえ、当時の新聞記事や在台邦人の口から「蕃人」という言葉が消えることはなかった。
第二次世界大戦後、台湾統治を始めた中華民国は、高砂族を「高山族」に変え、のちに「山地同胞(山胞)」とした。台湾のもともとの主人たちは有史以来、時の外来政権により呼称を与えられ、社会の周縁に追いやられ、それらを甘んじて受け入れざるを得ない立場に置かれてきた。2016年、蔡英文総統が就任後、初めて迎えた「原住民族の日」(8月1日)に原住民族の過去四百年の苦難に対して謝罪したことは記憶に新しい。
1980年代に入り、台湾社会全体が民主化への歩みを進める中で、彼ら自身も権利回復運動を展開していく。84年、大学で学ぶ若者や長老教会関係者らが中心となって「台湾原住民権利促進会」を発足させ、88年には17条の「台湾原住民族権利宣言」を発表。「台湾原住民族」の名のもとに、土地の返還や自治の実現などを要求したのだった。
「原住民(族)」という日本語は差別的なのか
それにしても、そもそも、日本語の「原住民(族)」という言葉は差別的なのか。原点、原石、原本などを見ればわかるように、「原」は「もと」や「みなもと」といった意味で、差別的な意味は持たない。国語辞典で「原住民」を調べても、「その土地に、もとから住んでいた民」(広辞苑 第七版)、「(征服者や移住民に対して)もとからその土地に住みついている人々。先住民。」(旺文社国語辞典 第十一版)などと記されており、どこにも差別的な意味は見いだせない。
日本の書物で、「原住民」という言葉を最初に記したのは坪内雄蔵(逍遥)である。1901(明治34)年に出版した『英文學史』(東京専門学校出版部)の第一編「上古期の文学」第一章「英国の原住民及びアングロ、サクソン族」の中で、「英國の原住民と英國の文學史との間には殆ど些の關係も無し」と述べ、そのすぐあとで触れるブリトン族より前に住んでいた民族を「原住民」と呼んだ。さらに坪内は、アングロサクソン族が、「原住民」であるブリトン族を撃退して以降、政治においても文学においても「眞の英國史」が始まったと続ける。本書には、「蠻族」「蕃民」という言葉も出てくるが、明らかに「原住民」と区別して使っていることがわかる。
一方、「先住民」という言葉を探していくと、1907(明治40)年の『地底探検記』(江見水蔭著/博文館)にたどり着く。目次の最初が「先住民の研究」で、「抑も我々大和民族―現在の日本人―その祖先が、此土地に来たらぬ前には、如何なる種族の住民が此所に居たらうか」という課題が掲げられている。明治時代後半の時点で、「原住民」と「先住民」はいずれも「前に住んでいた民族」という意味で使われていた。では、いつから「原住民」に「差別的なニュアンス」が加わったのだろう。
2007年、ある「宣言」が国連総会で採択された。英語で「Declaration on the rights of indigenous peoples」。国際連合広報センターによると、日本では「先住民族の権利に関する宣言」と訳されている。そこからさかのぼること四半世紀、国連の人権小委員会は1982年、この宣言の草案を作成することになる作業グループを設置していた。世界的に「indigenous peoples」の人権問題が注目されるようになった1980年代から、訳語としての「先住民族」が広く使われるようになり、定着していったと言えば言い過ぎだろうか。
かたや「原住民族」は「indigenous peoplesの訳語ではない」という理由で積極的には使われなくなった。そして、同じ「原」という字を使う「原始人」の「未開社会の人間」という負の意味が「原住民」に持ち込まれた結果、「差別的なニュアンス」を背負わされてしまったとは考えられないだろうか。
「すでに滅んでしまった民族」と呼ばないために
「台湾原住民文学選」(草風館)などの翻訳がある天理大学名誉教授の下村作次郎氏によると、台湾研究者の中にも、あえて「先住民族」を使う人もいるそうだ。しかし、下村氏は「彼らが勝ち取った『原住民族』という呼称を尊重したい。どうしても先住民族と言わなければならないなら、“世界の先住民族のうちの、台湾の原住民族”と言います」と話す。そして、「日本語とはいえ、『先住民族』を文字にしたときに、台湾の人がそれを読んでどう感じるか」とも。ある翻訳本のタイトルを付ける際に、「原住民族」という言葉にこだわって取り上げることをためらうメディアがあるのなら、その代わりに「エスニックマイノリティ」という言葉を使って、同書への関心を向けてもらおうと考えたという。
「先住民族」ではなく「エスニックマイノリティ」を選んだのは、台湾で「先住民族」は「すでに滅んでしまった民族」という意味になるからだ。台湾も日本も漢字を使う国である。もちろん、同じ漢字を使っていても意味が違う言葉はたくさんある。しかし、「原住民族」と名乗っている人を「原住民族」と呼ばない理由はない。ましてや、日本語の「原住民族」に差別的な意味はないのだから、わざわざ「すでに滅んでしまった民族」という意味の「先住民族」に言い替える必要などない。
台湾の「原住民(族)」は彼ら自身が獲得した呼称である。もともと日本語の「原住民(族)」に差別的な意味はない。台湾で「先住民(族)」は「すでに滅んでしまった民族」という意味になってしまう。以上の理由から、わたしは台湾の「原住民族」を「原住民族」と呼びたいし、以上の理由を説明しながら、「原住民族」という呼称を使うことを広げていきたいと思っている。もちろん、「先住民族」と呼ぶことを否定しない。「先住民族」と同じように「原住民族」という言葉を自由に使えるようになればいい。読者のみなさんはどのようにお考えだろうか。
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15729












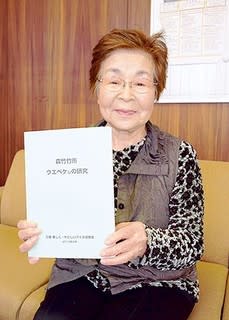
 書名 千島列島の山を目指して
書名 千島列島の山を目指して



