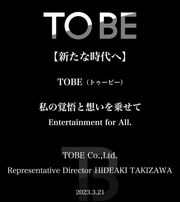8世紀の初め
アヴランシュの司教だった
オベールの夢の中に
二度ほど
サン・ミッシェルが出現し
この地に修道院を建てよ
と告げたらしいのですが
当のオベールは
それを信ぜず
サン・ミッシェルが
三度目に出現した時には
大天使もいい加減にせ~よ
って感じだったらしい
オベールの頭の中に指(だったかな?)を突っ込み
お告げを頭にインプットしたとか
しないとか



1000年から1010年の間に
建築された修道院付属の教会内部
標高80メートルを誇る岩山の頂上
長さ80メートルに及ぶ土台の上にあります
身廊の天井は
薄い板で覆われた板張りで
1421年に崩壊した
ロマネスク様式の内陣は
100年戦争後
ゴシック様式で再建されています

19世紀には
この修道院が
牢獄として使われていたことがあるそうで
当時
この部屋は
囚人の食堂として利用されていました
南壁の司教座で
僧が読唱する間
囚人達が沈黙のうちに食事をとったとか?
バスチーユの牢獄のように
生きて出る事の出来ない
孤島の牢獄だったんのでしょうか…
収容された囚人は総勢14,000人


囚人達が
この監獄から解き放たれるにあたり
作ったと言われる
‘Notre dame(我らの母)’→聖母マリア
因みに
‘Notre dame’をイタリア語にすると
‘ノストラダムス’らしい…


かつて
修道僧の納骨堂だったフロアには
大きな車輪が陣取っています
この車輪を回し
囚人用の食料を引き上げたそうです


車輪の中に
随時6人の囚人が入り
ハツカネズミのごとく
ひたすらに車輪を動かしていた
囚人が命尽きて
死んだ場合は
すぐ脇にある
大きな穴に死体を投げ捨てたとか


穴の底には扉があり
扉の前は
囚人用のお墓になっていたそうです


チャペルにある墓地へ続く階段
死者のためのチャペル
‘ステファヌスのチャペル’
ラテン十字の下には
ギリシャ語の‘ΑΩ’の文字
これは
誰にも平等に
始まりと終わり(生と死)が訪れることを
表しています


騎士の間(修道僧達の仕事場&執務室)
大きな珍しく暖炉があります
これは
寒さ対策ではありません
なんと
ペンのインクが寒さで
固まらない様に
との配慮なのだそうです
ペンさまさま
また
昔は
台所と言うフロアの観念がなかったらしく
暖炉の周辺がキッチンだったそうです
なので
来賓が集まる時には
仕切りを置いて
来賓の目に触れないようにしていたそうです
アヴランシュの司教だった
オベールの夢の中に
二度ほど
サン・ミッシェルが出現し
この地に修道院を建てよ
と告げたらしいのですが
当のオベールは
それを信ぜず
サン・ミッシェルが
三度目に出現した時には
大天使もいい加減にせ~よ
って感じだったらしい
オベールの頭の中に指(だったかな?)を突っ込み
お告げを頭にインプットしたとか
しないとか



1000年から1010年の間に
建築された修道院付属の教会内部
標高80メートルを誇る岩山の頂上
長さ80メートルに及ぶ土台の上にあります
身廊の天井は
薄い板で覆われた板張りで
1421年に崩壊した
ロマネスク様式の内陣は
100年戦争後
ゴシック様式で再建されています

19世紀には
この修道院が
牢獄として使われていたことがあるそうで
当時
この部屋は
囚人の食堂として利用されていました
南壁の司教座で
僧が読唱する間
囚人達が沈黙のうちに食事をとったとか?
バスチーユの牢獄のように
生きて出る事の出来ない
孤島の牢獄だったんのでしょうか…
収容された囚人は総勢14,000人


囚人達が
この監獄から解き放たれるにあたり
作ったと言われる
‘Notre dame(我らの母)’→聖母マリア
因みに
‘Notre dame’をイタリア語にすると
‘ノストラダムス’らしい…


かつて
修道僧の納骨堂だったフロアには
大きな車輪が陣取っています
この車輪を回し
囚人用の食料を引き上げたそうです


車輪の中に
随時6人の囚人が入り
ハツカネズミのごとく
ひたすらに車輪を動かしていた
囚人が命尽きて
死んだ場合は
すぐ脇にある
大きな穴に死体を投げ捨てたとか


穴の底には扉があり
扉の前は
囚人用のお墓になっていたそうです


チャペルにある墓地へ続く階段
死者のためのチャペル
‘ステファヌスのチャペル’
ラテン十字の下には
ギリシャ語の‘ΑΩ’の文字
これは
誰にも平等に
始まりと終わり(生と死)が訪れることを
表しています


騎士の間(修道僧達の仕事場&執務室)
大きな珍しく暖炉があります
これは
寒さ対策ではありません
なんと
ペンのインクが寒さで
固まらない様に
との配慮なのだそうです
ペンさまさま
また
昔は
台所と言うフロアの観念がなかったらしく
暖炉の周辺がキッチンだったそうです
なので
来賓が集まる時には
仕切りを置いて
来賓の目に触れないようにしていたそうです





































































 持ち堪えてね
持ち堪えてね


























 ゴシック様式初期・正面ばら窓
ゴシック様式初期・正面ばら窓