私の乱読癖は、無謀にも加藤周一を真似て「一日一冊」を実行していた高校時代に身に付いてしまった・・・ということはどこかに書いた。若い時に染み付いた癖は、善かれ悪しかれ、簡単には抜けない。
当時の岩波文庫は★の数で価格が決まっていた。★一つが50円の単位で、★三つなら150円、五つなら250円・・・という具合である。また、岩波新書は一冊だいたい180円、それ以上はおよそページ数で値段が決まっていた。
平均して毎日200円程度の金銭を必要としていたわけだが、それは月5000円の小遣いの範囲を大きく超えるものではなく、懐が寂しくなれば、たいがい高校を“エスケープ(こっそり学校を抜け出すこと)”して、近くの図書館で過ごしたり、店主にハタキで邪魔されながら立ち読みするのが、私の密かな楽しみになっていた。
あの頃の今治西高等学校は、猛烈な進学校の一つであったにもかかわらず、奇妙に大らかなところがあって、このエスケープが理由で怒られたり説教された記憶などはない。進学校の常として、当時、国立一期校への道に漏れた、落ちこぼれ的生徒たちは、端《はな》から大きな問題にされていなかったのかもしれない。ただ、一度だけ職員室に呼ばれたのは、数学のS先生の授業中、いつものごとく教科書の間に英語の読本を挟んで読書に浸っていたのが原因だった。
S先生はまだ二十代半ば、新任情熱教師の典型みたいな人だった。いつも白衣を着て右手に鞭(指示棒)を持ち、たぶん理路整然と数学理論を説いていたにちがいないのだが、高校2年にもなった私は、すでに私立文系に進むことを決めていたから、理系のみに必要な数学や物理や化学の教科への興味から遠いところにいた。
しかし、この先生が嫌いだったわけではない。他の日本史や世界史や古文・漢文などの場合と同様、私(だけではなかったろう)は、教科授業の良し悪しと、その教師自体の良し悪しを明確に分けてとらえていた。S先生の授業内容は私に何も教えなかったろうが、彼の単純明快にしてスッキリとした人柄には一種の好感を伴った敬意を持っていた。
ある日、あまりに平然と授業を無視する私の行為に、どこか意所《いどころ》の悪かったらしいS先生の大きな声が怒気を含んで聞こえてきた。「K!ちょっと前へ出て来い!」 私は「あらら?」と呟きながら教壇の横まで進み出た。クラスは静まりかえり、皆の注目は次に起こるS先生の行動とそれに対する私の反応に集まった。
その直後、突然、振り下ろされた小柄なS先生のムチを避《よ》けようと思えば避けられたかもしれない。当時の私は、剛柔流空手を少しかじった硬派としての一面も持っていて「オヤジ」という、もっともなあだ名が付けられていた。しかし、それは私の全く予期していない行動だった。五部刈りの坊主頭はまともにムチを受け、ピシリという乾いた音が教室に響いた。私は一歩間を詰めて「しわくなら素手でしわけ!!」とだけ言って席に戻った。その結果、「あとで職員室に来い!!」・・・となったわけだ。
放課後の職員室には二つの空気が流れていた。どこの組織にもあるだろう「体制順応」の空気と「体制嫌悪」の空気である。あえてもう一つ加えるなら「どっちつかず」の空気もあったであろう。行きたくもない職員室にしぶしぶ出向きS先生の机の前に立つと、先生は複雑な表情を浮かべながら「ムチで叩いたのは私が悪かった。君の気持ちは分かる。でも、少しは私の授業にも興味を持ってほしい・・・」と謝罪とも説教とも同情ともつかないようなことを言った。この時、十七歳の少年の感性はことの全てを把握していたのかもしれない。
私よりも十年ほど早い学生時代を東京の国立大学で過ごした彼は、何らかの形で、あの六十年安保に象徴される反体制の空気に触れていたはずで、狡猾《こうかつ》で理不尽な権力の横暴と、底の浅い学生運動の決定的挫折にも遭遇していたはずだ。そして今、地方の一教職公務員を生業《なりわい》とする自分の立ち位置を、時に悲哀と苛立《いらだ》ちをもって眺めることもあったろうと思う。私の目からなぜか大粒の涙が溢《あふ》れた。
隣の机で一部始終を聞いていた化学の中年教師は「このクソ生意気が・・・!」と吐き捨てるように呟き、少し離れた机の物理の熟練教師は「K!オマエは大物になるぞ・・・!」と明るく笑った。その後、ますます化学の時間が嫌いになり、物理の教師が好きになったのは言うまでもないが、この事件がその後の私の成績の変化に何らかの影響を与えたということはない。
(脱線気味のまま、2へつづく)
最新の画像[もっと見る]











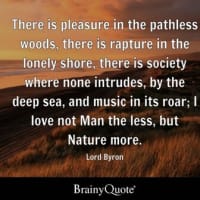














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます