瀬戸内海120kmフライトレメ[ト(愛媛県・長浜町~山口県・宇部市) 1999年8月12日~13日
ルートマップ  |
生まれ育った海の上が飛びたくて10年ほど前にPPGを始めた。大概は程よい海風でテイクオフして、グライダーの滑空比で陸地まで帰ってこれる範囲の空域をフライトするものだが、それでも上空から見下ろした海の様子は海岸から見るものと全く違っていて、海面の乱反射を受けにくいため、魚の群れが観察できたり、数十メートルの海底まで見通せることもある。オープンコックピットのPPGで空と海のブルーの間をずっと飛んでいると、体ごと青い世界に溶け込んでいくような気がしてちょっと不思議な気分になるのだ。
2年前の春、動力飛行と滑空飛行を組み合わせて瀬戸内海を横断したことがある。香川県坂出市から最短距離の岡山県王子ヶ岳付近まで10km余り、海上サメ[トなしで全くの単独飛行だったが、季節的にも良いコンディションに恵まれて、非常に快適なフライトを経験した。それから徐々に「動力飛行を主体とするPPGでどれくらいの海上飛行が可能なのだろう。いつか限界に挑戦してみたい。」という気持ちが私の中で強くなっていた。
そんな折、ほんの1年前にPPGと出合ってその魅力に取りつかれ、それまでの仕事やらなにやらをさっぱり捨てて大空の夢に人生を賭けることにした・・・というちょっと変わった男に出合った。私はその生き方に共感を覚えた。今年の春、彼の小野田でのPPGスクールのオープニングイベントに参加した時、「そのうちエリア前の海からひょっこり現れてちょっと笑わせたいな。」と思いついたのが今回のフライトプランの始まりだった。
「肱川あらし」で有名な伊予灘に面した愛媛県・長浜町から直線距離で約130km。 瀬戸内海の多島美を楽しみながら、島々を跳び石伝いに飛んで行ければ一番楽で安心なのだが、最も近い八島まで35km、西に向かって伊予灘から周防灘に入るともう島影はない。
まず燃料をどうやって増やすか、伴走艇をどうするか、季節はいつが良いか、風をどう読むか・・・。 エンジントラブルが許されない海上を100km以上飛ぶとなると、どうしても解決しなければならない課題がいくつかあった。
ともかくまず徹底的に飛行計画を検討することにした。基準として無風時・燃費10分~15分/リットルで計算を始め、風向・風速のデータから所用燃料と時間が計算できるPCソフト等も使いながら何種類ものバリエーションでフライトプランを作った。簡単に要点をまとめると次のようになる。
直線飛行距離130km 搭載燃料 35リットル |
燃費 | フライト可能時間(分) |
15分/リットル | 525分 | 8時間45分 |
10分/リットル | 350分 | 5時間50分 |
対地速度 | 予想所要時間 |
50km/時間 | 2時間40分 |
45km/時間 | 3時間00分 |
40km/時間 | 3時間20分 |
(平均対気速度)35km/時間 | 3時間40分 |
30km/時間 | 4時間20分 |
25km/時間 | 5時間10分 |
20km/時間 | 6時間30分 |
・35リットルの燃料を積むことが出来れば、燃費が最悪の場合でも5時間50分は飛べるはずなので、対地25km以上で130kmの飛行が可能になる。
・フライト高度は、最も効率的に飛べる位置を選択するが、緊急時に離脱する上での安全マージンを充分取るために最低300m(エンジン停止時に着水まで約3分)を基準にする。
・対地速度が20kmを切る状態が1時間以上続いた場合は、フライトを中止して伴走艇に降りるか、着水するか、近くの陸地に緊急ランディングする。
・その場合、姫島ウエイャCント(75km地点)を越えていれば伴走艇で目的地まで行く。その手前なら伴走クルーと相談して引き返すかどうか決める。
・今回のフライトは常に伴走クルーとの共同作業になる。ダウンウインド(追い風)はスピードが出て良いが、私が早すぎると伴走艇が付いてこれない。そういう時は、上空で旋回しながら追いついてくれるのを待つ。(実際、何度かそうなった。)
・飛行中に風向き、エンジンの調子、燃料消費量等を見ながら臨機応変に対処する。
・考えられる限りの準備をした後は、心配してもしょうがない事は心配しない。
・ともかく「楽しみながら海を渡る」を基本姿勢にして、決して無理をしない。

増量タンクは今回の飛行に合わせてアンダーシートタイプで20リットルを2個、燃料供給の確認の為に中間タンク5リットルをフレームのサイドに1個、メインタンク5リットルと合わせて50リットル積めるようにして、実際にライズアップからテイクオフにかけての動作が可能かどうか確認した。
燃料供給はミクスチャの不具合が心配なので、まずアンダーシートの20リットルタンクから手動ャ塔vで中間確認タンクに移動して次にメインタンクに落とし込む、という2段階方式にした。
30リットル増量でも装備と合わせて40kg近い重量増加になるのでかなり大変だったがタンクフレームに工夫を加えることとアメリカの友人達からヒントをもらったヒップサメ[トを使うことで、問題なくテイクオフできるようになった。(当日は全部で37リットル搭載した。)
伴走艇とサメ[トクルーはクラブの仲間達が引き受けてくれたが、皆の休日を調整してみると実行日はどうしても空気の薄い真夏のお盆休みの数日間ということになった。
「まあ、台風さえ来なければ気圧配置的には安定した夏の青空が広がるだろう。上空の風の本流も読みやすいに違いない。昼前から吹いてくる海風に合わせてテイクオフし、最も適当な風の層を選んで飛んで、向こうに近づいたら高度を下げてまた海風を利用してスピードを稼ごう。」
およそこのようなことを楽天的に考えながら準備を進めるにつれ、様々な不安要素と共に新しいアイデアが次々に湧いて出てきた。それらを一つ一つ検証しながらプランを練り上げていく作業は本当に楽しかった。
「クロスカントリーフライトの楽しさの90%はフライトプランにある・・というのはまったく本当だ。後のことは付録みたいなものかもしれない。」
カメラクルー取材中 |
ところが今年の夏は太平洋高気圧が例年のように張り出すことが無く、四国近辺は梅雨が明けても次々台風がやってきて、予定の8月に入っても荒れた天気が続いていた。
8月12日「今年は無理かもしれないな・・・」と思いながら迎えた8月12日の朝、テイクオフ場の長浜港多目的広場には、この挑戦フライトの話しを聞いた地元の方達が花束を持って前祝いに来てくれていた。
子供さん達のタンデムフライトがきっかけで取材を受けることになったテレビ局のスタッフもなんだか気合がはいっている。
四国地方はごく弱い熱帯低気圧が停滞しているものの、天気は晴れ、本流は弱い東風、小野田の風情報は西風2m、時間と共に穏やかな海風も吹いてきて、総合的なコンディションは徐々にフライトプランの許容範囲に入ってきた。
ギリギリまで良いコンディションを待って午後2時前、テイクオフ。上昇率0.2m/秒とちょっと頼りないが、エンジン音快調。500mまで上がって海上の逆転層を超えると、東風の本流に当たって対
地速度は40kmを超えた。伴走艇がついてこれるぎりのスピード。「この調子なら3時間ちょっとで行けるかもしれない・・」と甘いことを考えながら、燃料供給用のャ塔vを押してみると「あらら・・・」 圧力が無い・・・。

出発地点から40kmほどの地点だったが迷わず八島まで引き返して長い砂浜に緊急ランディング。
原因は確認用中間タンクにあいた直径5cmほどの穴だった。排気口から充分距離を置いて取り付けたはずのタンクに排気熱がローターになって当たり、長時間の加熱でプラスチック容器を溶かしてしまったのだ。
「何たる情けないミス!」 しかし、この日のフライトでマイナス要素の一つが解消したので、「この天気さえ続けば必ず成功する」という確信が更に強くなった。
伴走クルーも「これなら明日は絶対行けるね。」と、元気いっぱいだ。「そうだ、失敗は目標を達成するまで諦めなければ、かえって貴重な過程になるのだ。」
8月13日昨日と似たような空模様だが、低気圧が多少発達しているのだろう、昼になっても海風が安定
(初日 矢島上空750m) |
せずテイクオフ場には弱い東寄りの風が入っていた。相変わらず蒸し暑いが風的には悪いコンディションではない。
ところが、エンジン周りの確認を済ませプラグの増し締めをしようとした途端、ヘッドのねじ山がとんでしまった。非日常的な状況では日常めったに無いことが起きるものだ。急遽別のエンジンからシリンダーヘッドを取って付け替えたが、今度はミクスチャがリッチ気味で回転数が充分に上がらない。かなりリーン絞り込んでやっといつもの回転数に戻した。
今日はなんだかおかしな事が続けて起こる。しかし「これでまたマイナス要素が減ったのだから、プラス要素の割合が増えたに違いない」と考えた。要するにどうしようもない楽天家らしい。
「さて、今日で最後だ。ともかく悔のない飛びをしよう。」
12時39分、テイクオフ。瀬戸内には薄いガスがかかっていて視程10km以下。上昇率は昨日より悪い。エンジンが100%の力を出していない
(伴走艇とペースを合わせて・高度400m) |
。
それでもゆっくりゆっくり上昇し、やっと高度300mに達した頃、突然エンジンが息をつき始めた。
明らかに「かぶり」気味の兆候だ。(ハイニードル、もうちょっと絞り込んでおけば良かった・・・オーバーヒートを恐れて躊躇したのだ・・・と後悔してももう遅い。)クルージングの6000回転を維持できない。高度は徐々に下がっていく。昨日と違って近くに島影は無い。
これまで経験したことの無い真剣さで微妙なスロットル操作に集中しながら、回転数が持ちなおしてくれるように祈るしかなかった。
必死の思いの何分間か・・高度は下がり続けたが、ありがたいことに海面まで200mというところで、また徐々に回転が上がり始め最初の危機を脱することができた。
やがて昨日降りたひょうたん島みたいな矢島が近づいてきた。その向こうの岩礁だらけの祝島も見えてきた。取材ヘリが今日もやってきた。海の上を一人で何時間も飛んでいると、こんな巨大な航空機が昔からの友人みたいに思えるから妙だ。こちらからもビデオ撮影しながら、何度も手を振った。ヘリは私の前後左右を見守るように30分ほど飛んで、帰って行った。
今回のフライトでは主にGPS航法を使った。前もって入力してある通過地点に近づくと、メッセージが表示され次の地点までの距離と方位を示してくれる。
注意深くエンジンの機嫌を取りながら45km地点の祝島沖を過ぎた。高度450m、上空からは細波にしか見えない海面もかなり波立っているのだろう、伴走艇がホッピングしながら白い航跡を引いている。
辺りは薄いもやに覆われていて遠くの島や陸地を確認するのは困難だが、回りを取り囲んでいる薄青い空間と光が自分をしっかり守ってくれているような奇妙な感覚があった。
快走する伴走艇・萩原さんとコックピットの二宮船長、秋山記者

幾分余裕が出来て喉が渇いたので、ハーネスのャPットに入れておいた飴をなめようと思ったが、しばらく前に1個目を口に入れたとたんエンジンの調子がおかしくなったのが気になって、縁起担ぎみたいでおかしかったが到着するまで我慢することにした。
75km地点の大分県姫島ウェイャCントが近づくにつれ、それまで東だった本流が徐々に西に変わり、対地速度が30kmを切るようになってきた。いよいよ今回一番困難を予想していた周防灘に入ったのだ。
残り50km。ここから先は海以外何も無い。「これからが大変だから、気を引き締めて行こう。」無線で伴走クルーに呼びかけた。予想通り西風は徐々に強くなっていった。 海面には薄いブローラインが何本も見え始めた。
あと30km。 はるか前方に淡く本山岬近辺の海岸線が浮かんできたが、速度はついに20kmを切り始めた。ほとんどアップウインド、15km程の向かい風が吹いていることになる。
伴走艇を停めて海上の風を測ってもらう。「2~3m/秒」。ここよりは幾分弱い。緊急の場合の為に高度は下げたくなかったが少しでも速度を稼げるように150mまで降りた。トリムもかなり解放してグライダーのピッチを下げた。
テイクオフしてから3時間以上が経過していた。「燃料は後2時間位は残っているはずだから、風がこれ以上あがらなければなんとか小野田まで届くかもしれない。」確認用の中間タンクを反射鏡で覗いてみた。
なんと・・・空になっていた。何度もャ塔vを押す・・・上がって来ない・・・ということは補助タンクの30リットルをすでに使い切ったということになる。予想した最悪の燃費のリットル当り10分を下回って8分しか飛んでない計算だ。残りはメインタンクだけ・・・どんなに上手に使っても1時間もたないだろう。
しばらく迷ったが、本山岬をまわって小野田まで行くプランを、最も近い宇部市を突っ切ってまっ
ランディングが近い |
すぐ進むプランに切り替えた。進路を北北西に転じると完全なアップウインドになった。宇部セメントのエントツから白い煙がこちらに向かって真横にまっすぐ流れている。見事なオフショアの風、海面のブローラインは黒く波状になって次々押し寄せてくる。
大気は相当荒れている。高度を50mまで下げた。伴走艇のスタッフの心配そうな顔が見える。アクセルを目いっぱい踏み込んでも速度は10kmを超えなくなった。6m以上の風だ。燃料はどんどん減っていく。
ともかくランディング場所を探した。幸い正面の宇部漁港の横にかなりの広さの広場が確認できた。残りの燃料は2リットル。グライダーのピッチは最大限下がっている。波のような乱気流にグライダーはアップダウンを繰り返している。キャノピーを潰されないようにブレーク操作が忙しい。
後1リットル、まだ海の上。広場で風に波打つ木々がもうすぐそこに見えているのに、なかなか近づいてこない。伴走艇に着水の可能性を指示して、アクセルを踏みつづけるしかない。それでも少しづつ少しづつ陸地が近づいてきた。
そして・・・5時28分、やっとランディングした時、メインタンクには300ccの燃料しか残っていなかった。広場は漁港内に設けられた網干し場だった。
目的地の小野田まで10kmほど残したが、海上フライト 5時間弱、120km。ともかく幸運にも恵まれて私にとって全力を出し切った今回のチャレンジフライトは終了した。新しい発見が色々あってほんとに楽しかった。たった24フィートの伴走艇にとっても一つのチャレンジ航海だったのだ。。ほんとによく無事に航海を終えてくれた。
(オノダスカイスクール・格納庫前にて) |
最後に、私の思いつきに忍耐強く最後まで付き合ってくれたLAAの二宮船長とサメ[トクルー、あいテレビの秋山記者、応援して下さった長浜町の皆さん、大歓迎してくれた「オノダスカイスクール」の西村さんはじめクラブの皆さん、私がボランティア参加している難民救援団体AAR・NGOの皆さんに感謝します。有り難うございました。 1999年8月
朝日新聞 99/8/14  | 使用機材
(グライダー)
ハトル・シンフォニーXL
(パワーユニット)
DKウィスパーGT
(増量タンク)
アンダーシート型40リットルタンク(手動ャ塔v加圧式)+確認用中間タンク5リットルタンク
その他の装備
アルチバリオメータ・GPS・無線機・ヒップサメ[トシステム・セイフティメ[チ(自動膨張式)・シーナイフ・撮影機材 ほか |
|











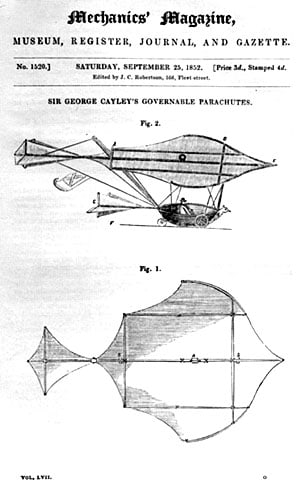


 アレックス・バーブ著/渡辺寛爾訳
アレックス・バーブ著/渡辺寛爾訳 









 幾分余裕が出来て喉が渇いたので、ハーネスのャPットに入れておいた飴をなめようと思ったが、しばらく前に1個目を口に入れたとたんエンジンの調子がおかしくなったのが気になって、縁起担ぎみたいでおかしかったが到着するまで我慢することにした。
幾分余裕が出来て喉が渇いたので、ハーネスのャPットに入れておいた飴をなめようと思ったが、しばらく前に1個目を口に入れたとたんエンジンの調子がおかしくなったのが気になって、縁起担ぎみたいでおかしかったが到着するまで我慢することにした。







 何枚か写真を撮った。
何枚か写真を撮った。