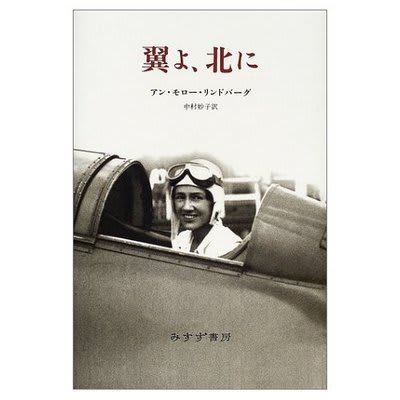C・リンドバーグには心強い同伴者がいた。ベストセラー作家であり、大空では彼の生徒であり時にクルー(搭乗者)でもあった妻のアン・モロー・リンドバーグだ。
彼女の自然観や人生観が集約されているように思える随想集「海からの贈りもの」は、ずいぶん前に、黄ばんだ文庫本を古本屋で見つけて読んでいた。後にC・リンドバーグの「翼よ、あれがパリの灯だ」の原書に目を通した時、その中のかなりの部分に彼女の手が入っているような気がした。もっとも私はまだ彼女自身の原著を読んだことはない。
今、手元にある「翼よ、北に」は彼女の処女作で、ごく最近(2002年)、中村妙子氏によって見事に訳出されたものだ。最初の末{は既に1935年(昭和10年)に原書“North to the Orient”が出て間もなく、深沢正策訳で「北方への旅」が出ている。このころ日本は軍国主義の道をひたすら走っていたわけだが、日本人の多くがまだ大空を見上げていた、ある意味、夢多き時代だったのかもしれない。
C・リンドバーグ同様、彼女についても想う事々が多くあり、これからも幾つかの角度から拙い考察を書き連ねていきたいと考えているが、今回は「翼よ、北に」の末メ・中村妙子氏について、少し驚いたことを記しておく。
彼女は1923年生まれ。私が生まれた1954年に東大の文学部西洋史学科を卒業している。現在83歳、この末ャした時は既に80歳直前の高齢だったのだ!
充分吟味された訳語、全く無理のない日本語、洗練された文体、女性作家の末メとして女性ならではの感性と表現手法・・・私は再び唸ってしまい、その生年を知って大きく肯いてしまった。実に末ヘ件pである。
この本の何章かは、途中立ち寄ることになる日本とその文化への考察に宛てられている。アンの瑞々しい感受性と表現力が充分に発揮されている部分でもある。また後で少し引用しながら、感想を書いてみたい。
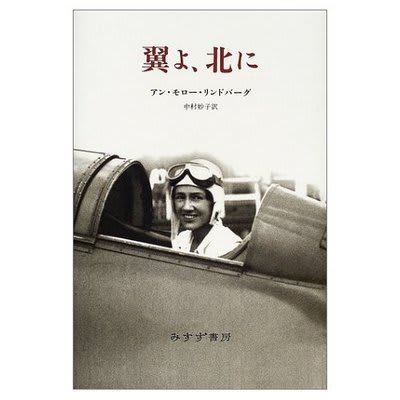
彼女の自然観や人生観が集約されているように思える随想集「海からの贈りもの」は、ずいぶん前に、黄ばんだ文庫本を古本屋で見つけて読んでいた。後にC・リンドバーグの「翼よ、あれがパリの灯だ」の原書に目を通した時、その中のかなりの部分に彼女の手が入っているような気がした。もっとも私はまだ彼女自身の原著を読んだことはない。
今、手元にある「翼よ、北に」は彼女の処女作で、ごく最近(2002年)、中村妙子氏によって見事に訳出されたものだ。最初の末{は既に1935年(昭和10年)に原書“North to the Orient”が出て間もなく、深沢正策訳で「北方への旅」が出ている。このころ日本は軍国主義の道をひたすら走っていたわけだが、日本人の多くがまだ大空を見上げていた、ある意味、夢多き時代だったのかもしれない。
C・リンドバーグ同様、彼女についても想う事々が多くあり、これからも幾つかの角度から拙い考察を書き連ねていきたいと考えているが、今回は「翼よ、北に」の末メ・中村妙子氏について、少し驚いたことを記しておく。
彼女は1923年生まれ。私が生まれた1954年に東大の文学部西洋史学科を卒業している。現在83歳、この末ャした時は既に80歳直前の高齢だったのだ!
充分吟味された訳語、全く無理のない日本語、洗練された文体、女性作家の末メとして女性ならではの感性と表現手法・・・私は再び唸ってしまい、その生年を知って大きく肯いてしまった。実に末ヘ件pである。
この本の何章かは、途中立ち寄ることになる日本とその文化への考察に宛てられている。アンの瑞々しい感受性と表現力が充分に発揮されている部分でもある。また後で少し引用しながら、感想を書いてみたい。