最近、ますます「どうすれば、楽しくカイトサーフィンできるか。つまり楽ができるか」・・・ということを考えながら練習している。楽しむのが目的であり、練習は手段ということになるが、私の場合、もちろんその手段も楽しむ。
こないだから始めたのが、片手でャbプやループをすることで、これなら片手は自由になり、空中でのバランスが取りやすくなるだけでなく、少なくても片手分の楽はできる。
他にもいろいろと便利なことが起こる。たとえば、私はランディング(着岸)の際に板を海上に残し、浜までの何mかをジャンプして帰着することがある。ところが、これをやると後で板を取りに戻らないといけなくなり、これがけっこう面唐ュさい。片手が自由になり、空中で板を掴むことができれば、その必要がなくなる分だけ楽ができるだろう。
19㎡・30kmほど

こんなコンディションの良い時は、まず30km以上、時には50km以上走ることもあるのだが、今回はなんでかなぁ・・・と、考えてみても良く分からない。私の身体がそれで満足したから・・・というしか他ない。
身体を使うスメ[ツは皆そうだと思うが、その最中は大概「感覚」で動いている。全身感性と言ってもいい。
飛行前に「フライトプラン」を練るように、私はしばしば、カイトサーフィンで海に出る前にも「カイト走行プラン」とでも言うべきものをイメージとして頭の中に描く。その内容は、時々の体調やエリアのコンディションや使用機材によって様々だが、いったん走り始めると、後はほとんど感性だけの世界になる。
風や波やカイトや板の相互作用をほとんど瞬間的に感知しながら、自分のイメージに沿った運動を続けるには、今ここでやっている言葉を使うような論理的思考では間に合わない。かえって邪魔になる。この種のスメ[ツの最中にゴチャゴチャ考え事をしていると、まずロクなことはない。
目や耳、時には鼻や触覚などの五感をフルに稼働して、更には第六感みたいな非日常的な直観力や反射力を引き出すには、ブルー・スリーじゃないけど、「考えるんじゃない、感じるんだ!」・・・ということになるのだろう。
F君に習ってリサイズしたリーシュ・ノブが功を奏したのか、今日も何回か急激にバーを引き込んでのジャンプを繰り返したが、不用意なリーシュ開放は起こらなかった。

ただ、だいぶ安定度を増してきたハイジャンプやループの際に、まだ、バーの引き込みに余計な力が入っているのが原因なのだろう、今日は2回も予期せぬリーシュ開放があって、リランチに時間がかかった。
 大きすぎるリーシュ・ノブが誘因になっていることも分かった。早速、削り加工を施して適当にリサイズする予定でいる。
大きすぎるリーシュ・ノブが誘因になっていることも分かった。早速、削り加工を施して適当にリサイズする予定でいる。1度目は岸近くの浅瀬だったのでどういうことはない。2度目はちょっと沖でカイトがきれいに折れてしまい、そのままではどうにもならないので、カイトまで泳いで形を整えている間に、かなりの量の海水が侵入した。
これがラムエア・カイト最大の欠点と言えるだろう。長時間水に着けると、何がしかの量の水が入り、相当に重量が増す。今回は順風に助けられてリランチできたが、順風未満だったらまず不可能で、岸まで数百メートルは泳ぐことになっていたと思う。まあ、それも良い水泳トレーニングになるので、そう辛いことでもないのだが・・・。

19㎡・約30km
昨日、いくぶん面唐ュさいこと考えていたら、ふたたび、若くして逝ったT君のことを思い出した。青春時代の彼は、私が還暦に近くなっても、二十歳過ぎの、あの同じ姿で現れる。有り難くもあり、悲しくもある。
彼が私に与えた影響はほとんど計り知れないものがあり、彼が静かな口調で語った言葉の断片は、ことあるごとに私の脳裏に蘇る。その一つが「他人(ひと)の身になって考えろ」ということだった。
つまりは「思いやりの心を持て」ということだ。これは西洋風にいうと「愛」であり、仏教的「慈悲」を和風に言い換えたものに他ならない。
こんな、ある意味深遠な教えを、わずか10代の若者が真顔で語り、実際その指針にマジメに従って生きていたことを、私はよく知っている。T君とはそういう男だった。
そして、それは昨日書いた世界宗教の「黄金律」そのものでもある。「人を思いやってその身になる」とは、愛や慈悲の発露そのもので、キリストと孔子は、まったく同じことを反対側から表現したにすぎない。
ただ、その中に釈尊の言葉が入っていないのは、彼の慈悲が人間に限らず全ての「生命」に向けられていたからで、もし彼が同様のことを言ったとしたら、「自分がしてもらいたくないことは、全ての生き物たちに対してもしてはいけない」となったに違いない。まあ、初期経典の中には似たような言葉がたくさん出てくるのではあるが・・・。
私は自分のことを相当に頑固な合理主義者だと思うことが多い。しかし、自然の世界と長いこと付き合っていると、この広大な世界の中で、小さな自分の理性の及ぶ範囲などはたかが知れているという、当たり前の事実に感動したりもするのである。
たぶん、つづく・・・。
信の世界を追求すると、どんな経路を通ったにしても、つまりは宗教の世界に至る。どんな原理でも主義でも、それを信仰の対象にすると、実証可能な合理性から遠ざかり、まずは信じることを強調する宗教の装いに変容する。
人は同時に2つの道を歩むことはできないから、一つの信念なり信仰なりを貫こうとすれば、他の道の路傍に咲く花を楽しむことが難しくなるのも道理だろう。
しかし、人間が何かを信じることなしに生きることができない存在である以上 なんらかの「信仰対象」を求めるのも、きわめて自然な心情の発露だ。
そして、私の拙い観察では、世界三大宗教といわれるキリスト教やイスラム教や仏教での原初の内容は、大方(おおかた)において、合理的で実用的であるという点でよく似ている。
キリスト教とイスラム教はもともと同じ一つの神の啓示から出発しているが、仏教では呆れるくらい多くの神や如来が登場する。儒教の始祖・孔子は仏教の始祖・釈尊より百年ほど前の人物で、これがまた興味深いことに、その教えの本質的な部分において、キリストやムハマンド(モハメット)などと同じようなことを言っている。
その一つは、いわゆる「黄金律」と呼ばれるもので、内容は以下の通り。
イエス・キリスト:「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイによる福音書7章12節)
孔子:「己の欲せざるところ、他に施すことなかれ」(論語 巻第八衛霊公第十五 二十四)
ユダヤ教:「あなたにとって好ましくないことをあなたの隣人に対してするな。」(ダビデの末裔を称したファリサイ派のラビ、ヒルレルの言葉)、「自分が嫌なことは、ほかのだれにもしてはならない」(トビト記4章15節)
ヒンドゥー教:「人が他人からしてもらいたくないと思ういかなることも他人にしてはいけない」(『マハーバーラタ』5:15:17)
イスラム教:「自分が人から危害を受けたくなければ、誰にも危害を加えないことである。」(ムハンマドの遺言)
前置きがずいぶん長くなった。すでに蛇足になるような様な気もするけど、5年ほど前に、私は次のような一文を書いている。
「私が、あえて言葉にすると“宗教”というものを、どうしようもなく必要とした時は、野外に出て星を描く」
<Sッホ
When I have a terrible need of - shall I say the word - religion. Then I go out and paint the stars.
-Vincent Van Gogh
狂気の画家と言われるゴッホの言葉だ。
あらゆる自然の生きものは「信じる」ことによって存在し活動している。樹木は大地を信じ、魚は海洋を信じ、鳥は大空を信じ、子供は親を信じることで、自ずと成長しその分に応じて、この世界での使命をはたすことができる。
この場合「使命」とは文字通り「命を使う」ことであり「生きること」と同義だ。日々大自然の恵みと厳しさの中で生き死にする彼らの世界に、疑いや不信の入り込む隙間はないはずだ。
さて、元々は自然的存在である人間の世界はどうであろうか。人間の作った社会や国家はどうであろうか。あらゆる自然存在が相互信頼の上に成り立っているのに比べて、あまりに嘘やまやかしが多すぎはしないか。それに従って、疑いや不信という伸びやかな成長にとっては阻害要因ともなる不幸が多すぎはしないか。
西洋近代は神に対する疑いと人間理性に対する信頼から始まったとされるが、日本の近代は堕落した仏教を中心とする宗教界への疑いと明治政府が持ち上げた神道への信頼から始まったと言えるのかもしれない。何を疑い何を信じるかによって個人や集団の命運が決まっていくのも当然だろう。
いずれにしても、どこまで行っても大自然の一部である人間が、まっとうに存在を続け成長していくためには、信じるに値する何かが不可欠で、人並み外れて感受性の優れた件p家が、嘘まやかしだらけの人間社会や神の世界に愛想をつかして、天空の星々に祈りをささげようとしたとしても何も不思議なことではない。
今日はたぶん曇り空で涼しくなるだろうから、久々に庭仕事でもしようかなぁ・・・と午後のひと時を予定していたら、なんでかそこそこの北西風が入ってきた。これは・・・やっぱり海に出かけるしかないだろう・・・ということで、潮具合の良い粟井エリアへ。19㎡で20kmほど。
それにしても、一年ほど前からカイトに出かける回数が圧涛Iに増えた。去年の夏、私の体重は80kgを超えていて、もっとも調子の良い70kg前半からすると、かなり際どいところまで来ていたようだ。
その頃のある日、何気ないジャンプをして両脚をグイと引き上げたら、ハーネスで抑えられて行き場を失った腹の脂肪が下から肋骨を圧迫して、肋軟骨が折れた、パキッと音を立てて・・・こんなことは想像したこともなかったことだ。
それから、私は本気でダイエットというかメタボ対策を始め、慣れない腹筋運動などというものを日課に加えたりしたのだが、何といっても効果があったのは、海に出かける回数の増加だった。
ちょうど去年の今頃から、F君の影響やことの成り行きで、愛用カイトをインフレータブルからラムエアに代え、19㎡を手にしてからは、それまでのおよそ2倍に近い時間を海岸や海上での運動に使うことになった。
もともとは、このフライサーファーのラムエア19㎡は、まあ微風用に一枚持っていても良いかな・・・程度の気持ちで購入したもので、これがこんなに頻繁に活躍するようになろうとは夢にも思ってなかった。
私は、カブリナのインフレ15㎡で海上を走り始めたのだが、1年も経って、クロスボウという13㎡を気に入ってからは、もう重たい15㎡は使う気になれず、大概の風はこの13㎡一枚で間に合うようになっていたのだ。
その感覚で19㎡というと、とんでもない面積だから相当に扱いにくいに違いなく、まあ風のない夏の季節に何度かお世話になれば良いかな・・・ぐらいの気持ちでいたのだった。
ところがどっこい・・・何でも自分でやってみないと分からない。この19㎡はとんでもない性能を持ったカイトなのだった。断っておくが、私はドイツのフライサーファー社の回し者ではない。
ノーベル賞のホスト国であり、村上春樹のベストセラー小説の題名の一部にもなった、あの美しい森の国ノルウェーで、やりきれないテロが起きた。
32歳の極右キリスト教原理主義を信条とする男が、ほとんど10代の大勢の若者たちを、恐らく何のためらいもなく射殺した・・・ということだ。
彼(か)の国々で近年増加し続ける移民労働者が、自国民の就職状況を悪化させたり、民族の誇りを傷つけたりすることが気に入らなくて、この残忍極まりない犯行に及んだらしい。
いわゆる「何とか原理主義」・・・私の頭の中のヘッャR辞書では、「原理」は「ある現象を成立させる基本法則」で「主義」は「好み」程度のものなのだが、「現象や法則」は自然界には満ち溢れていて、「好み」は人の数だけある。
ところが、なんとか原理主義者と呼ばれる人たちの中には、往々にして、自らが好みの原理や主義を絶対的に正しいものとし、他の原理や主義の存在を認めようとしない狭量な人間が存在する。
つまりは独善と非寛容ということなのだが、どちらも人間の幸福にとっては無用の長物であることに気が付かない人が、何ゆえに後を絶たないのか・・・すでに数千年を経る私たちの歴史に少し目を通せば、その間違いにすぐにでも気づくはずなのに・・・。
およそ、人間が創(つく)り、認識できるモノゴトの中に絶対的な何かは存在しない。
なぜなら、「あれ」の存在がなければ「これ」の存在もありえないからである。この世界の存在認識は相対化することによってのみ成立する。どんなものでも、絶対化すると、その絶対化した存在そのものが意味を失ってしまうことになる。
いちいち例を挙げるのも面唐ネことだが、例えば、全てが液体でできていて気体も固体もない世界では、液体という概念(考え)自体が存在できない。液体は気体や固体が存在するからこそ、それらと相対され区別されて液体として認識されるからだ。青色しかない世界の住人がどうして赤や白を知ることが出来るだろう。
ガリバーは小人の世界に流れ着いて初めて大男になった。彼が絶対的な神の存在を信じていたかどうかは忘れた。しかし、神が人間を創ったのか、人間が神を創ったのか?・・・と問われれば、私は躊躇(ちゅうちょ)なく後者に一票を入れる。
そして、私は「信の世界」を決して否定しない。この「信」を巡る私の思いつきはまた後で書く。
まるで、ウィンド時代のコースレースの上マークを攻めているような気分とガッチリした体勢で28km。まあ、そう面白いものではないが、非常に良い上りの練習にはなった。
珍しくGPSを一度も水につけなかったので、今回のログはスイッチの回数や、その動き方まで正確に分かる。私の防水GPSは、データをPCに取り込むと速度のグラフ表示がハチャメチャになるのが常なのだが、今回はほぼ実測値のように見える。スイッチ時の速度が10km前後のは、上りを取るために、ギュンとエッジを利かせて下流れを防いだ鋭角的なもので、15km以上は、いくらか滑らかで弧を描くようなジャイブスイッチ・・・ということになる。
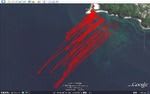

昨夜、テレビの報道番組で最後の部分をちょっとだけ観たに過ぎないが、 瀬戸内寂聴の言葉を重く聞いた。「私は我が身を挺(てい)して原発に反対する。私たちの子孫にこんな浮「ものを残してはいけない。」 もと流行作家で既に九十歳になろうとする天台尼僧の口調は静かで力強く響いた。
その他多くの原発反対者と同様、私もずいぶん以前から原発には反対の意見を持っている。とりあえずどのように「身を挺(てい)し」たら良いのかは、今のところ分からないけれども、日本でも一応「言論の自由」は保障されているので、ここでもハッキリと「原発は一刻も早く廃止すべきである」と発言しておく。
その理由についても、多くの反対者が語っているのとほぼ同じ内容なので、改めて言うまでもない。ただ、一点だけ、「それは大自然の摂理に根本的に反しているからである」ということは、軒の上に何十の軒を重ねることになっても、繰り返して強調しておきたい。
およそ、原発好きな方たちが、??「原発はいらないというが、電気が無くなってもいいのか!?」などと言う口調は、世界の人々或いはその他の全ての生き物たちの生命よりも、国家という人工制度の方が好きな人たちが、「(憲法9条に関して)軍隊はいらないというが、他の国に攻撃された時、黙って殺されてもいいのか!?」という語り口とよく似ている。
私は、日本では自衛隊という世界有数の軍隊組織を作りあげるだけの国家的労力を、一切の敵対国を作らないことに傾注する気持ちが少しでもあれば、このような発言はできず、同じく、大自然が潜在する実に多様なエネルギー源を利用することに少しでも関心を持てば、そのような発言も出て来るわけがないと思うのだが、どうだろう?
興味がある人は、どのような方たちが、その「国家好き」や「原発好き」か、ちょっと突っ込んで調べてみるといい。たぶんビックリするほど明瞭(めいりょう)な事実に気が付くだろう。
この数十年、ナチュラリストの一人として、じっくりと大自然の膨大かつ絶妙な力用(りきゆう)と付き合ってきて得た貴重な結論の一つは、自然と言っても、宇宙と言っても、一切法界と言ってもいいのだが、ともかく「私たち人間はそこから生まれそこに帰る存在であり、一時たりとも、その母体とも言える「大自然」から莫大な慈悲や恩恵を受けていない時はない」という事実である。
英語では、原発は原爆と同じで、頭に"NU-CLEAR"が付く。どこがクリアなの?"NO-CLEAR"にしたら・・・と、ちょっと突っ込みたくもなるが、それはともかく、この広い地球上のどの生命圏を探しても、物質の基本要素を、つまりは大自然やその中で生きる生命の根源的存在である原子を「破壊すること」で、何らかの力を引き出すなんてバカげたことをするものはいない。
人間だけが、その大恩を受け続けている自然世界に無理と不合理の限りを尽くしているとも言える。「恩を仇(あだ)で返す」という言葉があるが、原爆は言うにおよばず、原発もまた全く同様の仕方で、人間は自らを生み出し生かしている存在を裏切り続けているのではないのか。
天に向かってツバを吐くとそのまま自分に返ってくる。これは単なる諺(ことわざ)ではなく、地球の重力作用という厳然たる物理法則でもある。
また、人間や自然を慈愛する人は、いずれ人間にも自然にも慈愛されようになる。人を尊敬する人は人に尊敬される。親切にする人は親切にされる。逆に、人を恨む人は人に恨まれる。バカにする人はバカにされる。騙す人は騙される。裏切る人は裏切られる。苦しめる人は苦しめられる・・・など等の人間社会でよく見られる現象も含めて全て、単に道徳律に反するからというだけではなく、作用に必然的に伴う反作用という普遍の物理法則だからでもあろう。
これが「人倫の基本は自然界の懐(ふところ)に在り」とする私の根本的な原発反対理由である。
ジェントルブリーズ・・・優しい微風・・・といったところで、19㎡と順潮に助けられてそれなりに走れるという程度のコンディションだった。
19㎡・約20km










