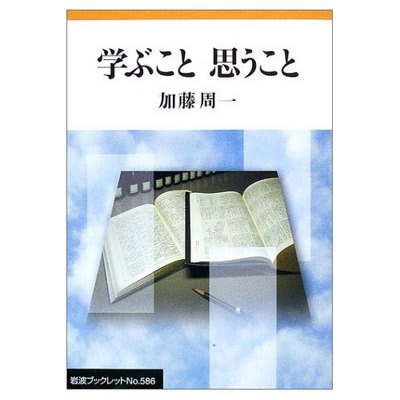アマゾンの空き箱を別の目的に使おうと思って開けてみたら、中から岩波ブックレットが出てきた。単なる広告冊子か何かだと思って放っておいたものだが、よく見たら加藤周一の『学ぶこと思うこと』という、ちゃんと定価が付いた本だった。お得意さんへのサービスだ。アマゾンもなかなか洒落(しゃれ)たことをする。嬉しくなって一気に読了した。
5年ほど前に東京大学の学生自治会が、新入生のために開いた加藤先生の講演を活字にしたもので、第一章が論語の「学びて思わざれば罔(くら)し、思いて学ばざれば殆(あやう)し」、第二章が学ぶためには何が必要か、第三章が日本の社会を変えていくために、という構成になっている。日本を代表する知性が、子供たちの年代を飛び越して孫の年代の人たちに、学び方と考え方の基本、問題意識を持ち自ら考え行動することの大切さを説いたものだ。
しかし、章を進むに連れて、戦争の狂気の時代を強靭な理性で生き抜き、戦後60年以上の今日に至るまで一貫してリベラルな立場で平和を説き続ける彼自身の“訴え”や“願い”がビンビン伝わってくるような内容になる。
彼の孫の世代といえば私の子供の世代だ。20歳前後でこのような講演に接する機会を持てた人たちは幸運だと思う。彼と出会うことによって、多くの人はまちがいなくその人生の基本的な方向性を得ることになるだろう。全体や集団に埋没しない一人の人間(個人)としての自分自身を生きる・・・という方向性である。
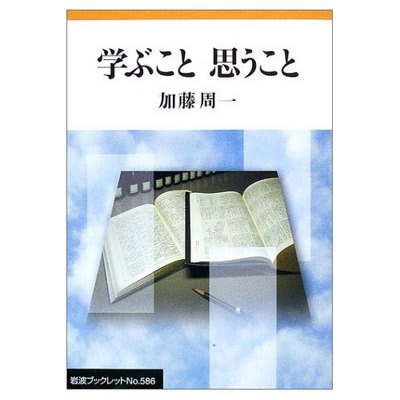
5年ほど前に東京大学の学生自治会が、新入生のために開いた加藤先生の講演を活字にしたもので、第一章が論語の「学びて思わざれば罔(くら)し、思いて学ばざれば殆(あやう)し」、第二章が学ぶためには何が必要か、第三章が日本の社会を変えていくために、という構成になっている。日本を代表する知性が、子供たちの年代を飛び越して孫の年代の人たちに、学び方と考え方の基本、問題意識を持ち自ら考え行動することの大切さを説いたものだ。
しかし、章を進むに連れて、戦争の狂気の時代を強靭な理性で生き抜き、戦後60年以上の今日に至るまで一貫してリベラルな立場で平和を説き続ける彼自身の“訴え”や“願い”がビンビン伝わってくるような内容になる。
彼の孫の世代といえば私の子供の世代だ。20歳前後でこのような講演に接する機会を持てた人たちは幸運だと思う。彼と出会うことによって、多くの人はまちがいなくその人生の基本的な方向性を得ることになるだろう。全体や集団に埋没しない一人の人間(個人)としての自分自身を生きる・・・という方向性である。