
味はともかく、店の装いが面白い。「かき小屋」というビニールハウス。婆さまも一緒に家族四人でたらふく食べた。
ここでは、カキ食えど鐘は鳴らずだったが、北西の強風がピューピュー鳴る中で炭火に跳ねる焼きガキをつつくのはなかなかの趣だった。

ウィンドショップ・テイクオフのMちゃん(といっても私と同年である)。昨日はこの小型のSUPで30分ほどウィンドサーフィンしてきた。3mほどの微風でチャプチャプトと歩く程度のスピードで堀江沖を一往復。
彼とは既に30年の知己になろうとしている。今年は共に還暦を迎える予定で、彼は腰が痛い、私は膝が痛い・・・などと、それなりの身体的老化は否応なし・・・というところだ。
どんな道具も「経年劣化」は避けて通れないのだから、耐用年数たぶん100年に満たない人間の身体という「道具」にもそれなりのメンテナンスが必要なことは言うまでもない。
私が最近ますます面白いと思うのは、年齢を同じくしても、人はそれぞれ相当に異なった容姿容貌を持つに至るという事実である。ちょっと思い付く有名人だと加山雄三・75歳。三浦雄一郎・80歳。日本人男性の平均寿命を80歳とすると、かなり高齢の方々ということになるが、まったくお元気で実に若々しい生き様をしていることは周知の事実である。逆に、20代30代で老人のような若者があまた存在するのも事実。
さて、この違いは一体どこから来るのか・・・結局「生き方の違い」ということになるのだろうが、ではその生き方の違いはどこから来るのか・・・。私の結論は、やはり「人生観・世界観・価値観・・・」など、ものの見方・感じ方・考え方の違いによるのだろう・・・ということになる。そして更に深く、どうしてそのような差異が生まれるのかについて想いを巡らせ始めると、哲学・宗教の世界に至らざるを得なくなる。
しかし、ことの次第はもっとシンプルなような気もする。いつまでも若くありたければ、いつまでも若い精神を保ち続けること。若いということは過去が少ないということであり、未来が多いということだ。未来は夢や目標を内包する。つまり精神がこれからしたいことやすべきことで満たされ得るということだ。
私は加山雄三が挙げる3K主義に全面的に賛同する。つまり、関心・感動・感謝の3Kである。そしてこれらは真に若き精神と生き方の極めて重要な属性のように思える。



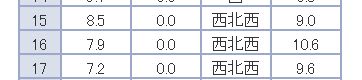


大海は絶え間ない流れだ。その中で多くの時間を過ごすと、人は中にメッセージを入れて漂う瓶《びん》のようなものになる。どこかに向かっていることは分かる。目的を持っている感覚がある。しかしまた、人は風と潮流に身を任せること、任せきることが唯一最善の方法であることも知る。
=w塩水のブッダ:サーファーが海で求める禅の道』
ジャイマル・ヨギス著
The ocean is in constant flux, and when you spend a lot of time in it you become like a floating bottle with a message inside; you know you’re going somewhere, sense you have a purpose, but you also know you’re at the mercy of the winds and currents, that surrendering may be your only good option.
-"Saltwater Buddha: A Surfer's Quest to Find Zen on the Sea"
by Jaimal Yogis

昨日は煙草を買いに高島屋まで。私のパイプ煙草は近在ではここにしか置いてない。自転車で30分、往復でちょうど1時間ほどの軽いサイクリングだ。
道中、東天、城山上空に白く輝く月が目に入ったので一枚。これが例えば十年に一度しか見られないとしたら、どれほど深い感慨を持って眺めることになるか・・・宇宙の奇跡は常に日常の中にある。
他の惑星や星への旅の体験は、しばしばUFOや地球外生命体による旅の手段として、また旅の案内役として関係付けられる。地球外知的生命体が存在するか否かの問題は、哲学者や神学者や科学者たちを魅了してきた。『神の仮説』のジョー・レーウェル博士によれば、「それが人間の形を持ったものであれ、精神的な伝達《コミュニケーション》によるものであれ、世界中の全ての宗教は人類と地球外生命体との相互交流に基づいている」例えばキリスト教の起源と聖母マリア(マタイ伝1:18)のいわゆる「無原罪懐胎」について考察すれば、聖母マリアの懐胎は地球外生命体の機関を通して引き起こされた。イギリスの作家、パトリック・ハーパーによれば「全ての伝統的な文化圏では、人々は神々のまた神に似た人間≠サの多くは空からやって来た≠フ子孫であると信じられている」
 歴史を通して全ての文化圏で、人類は空からの奇妙な物体や飛行体の目撃や接触を記録している。これらの記録の研究は、通常、未確認動物学や宇宙生物学や民俗学の分野に落ち着くが、また、妄想とか病理とか神話とか空想とか想像とか病的興奮《ヒステリー》の結果とかに分類される。しかしながら、多くの研究者は目撃者や接触者が心理学的に健全である証拠を提供しており、その研究成果は社会学や行動科学の主流を成す機関紙で発表されている。
歴史を通して全ての文化圏で、人類は空からの奇妙な物体や飛行体の目撃や接触を記録している。これらの記録の研究は、通常、未確認動物学や宇宙生物学や民俗学の分野に落ち着くが、また、妄想とか病理とか神話とか空想とか想像とか病的興奮《ヒステリー》の結果とかに分類される。しかしながら、多くの研究者は目撃者や接触者が心理学的に健全である証拠を提供しており、その研究成果は社会学や行動科学の主流を成す機関紙で発表されている。
(画像:山の上を飛んでいるように見える物体=山形県川西町で2014年1月7日午前11時40分ごろ、小林孝さん・小学校長撮影)
1997年のタイムやCNNの調査では、アメリカ人の22パーセントは地球が地球外生命体によって訪問されていると信じていることが明らかになっている。2000年、世界で最も傑出したUFO研究家の一人であるリチャード・ドーランは「軍の高官や科学者の多くがエイリアン《地球外生物》はずっとここにいると信じている」と述べ、2005年にはプロのUFO研究家のスタントン・フリードマンは次のように語っている。
「私は地球外生物のUFOは存在していて地球を訪問しており、政府はそのことを知っていると強く確信している。これは希望的観測ではなく、私は千年紀の末に天空から救いの神が降りてくるなどという終末論者でもない。私の確信は私や他の研究者が多年に渡って収集した事実を科学的に分析することから生まれた。この山のように集積されるデータは、おそらく近在の銀河に存在する他の文明が、近いところから我々を観察しているという考え方を、圧涛Iに支えている。
しかし、伝統的な科学界の傾向性は、そのような報告を無視するか捨て去ってしまう。科学的主流を成す見方を覆すような証拠をまともに考察しようとする科学者はごくわずかである。勇気を持って他の惑星での経験を報告する人々は、私たちの文化圏の支配的な世界観からは、良くても異常、悪ければ桃メとみなされるのである。そのような体験は簡単には合意的現実とはならないし、伝統的な科学から支持されることからは程遠いのである。
しかし、実際のところ科学的「事実」は教条主義や信念に基づいている。宇宙物理学者のハルトン・アープによると:
「専門誌での記事の査読《さどく》の伝統は、ほとんど完全に検閲に堕落している。元々或る記事を審査する者は、計算や参照文献や明晰性などの間違いを指摘することで、それがより良いものになるを助けるはずのものだが、科学者たちは自らの理論に固執するために、好みに合わない記事の発行を拒否するのである。もちろん出版社は強力な財政基盤や現状に合う確立された学術団体からの最新情報を扱う。その結果、真に調査研究に値する科学はほとんど地下活動的なものになる」
この『科学的探究ジャーナル』での言葉は、今日の現代世界においても支配的な世界観に反する多くの着想や研究結果は伝統的な学会誌には載らないということを現している。その結果、多くの科学者はUFOや遠隔透視《リモートビューイング》といった話題に関して集積された証拠を知ることがないのである。科学者たちがこれらオーソドックスでない話題について実験しない理由はまず常識的なもので、彼らが財政的支援を失い、その経歴を危ういものにするというのが最たるものだ。