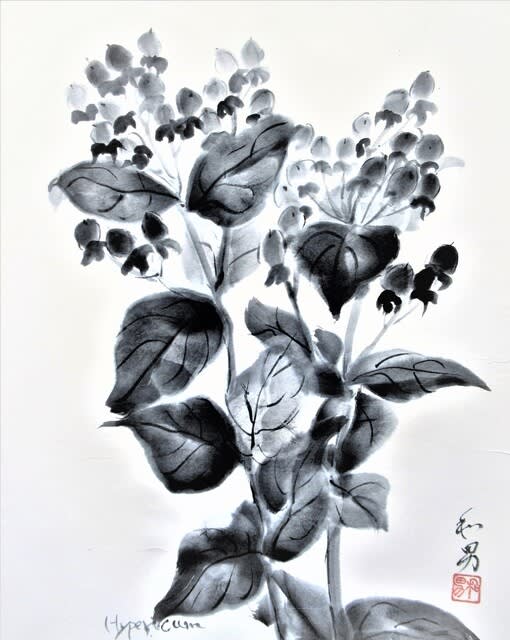真夏の暑い時の食欲増進にはモロヘイヤが最適です。

このモロヘイヤはナスの畝の一部に播いたもの。

今年は間隔25㎝と狭く株数も15株と少ない。
種播きは5月18日。例年より若干早めの直播きです。
高温性の作物なので、温度が低いと発芽しません。水分不足でも発芽しにくい。ですから苗を育てるのが普通。
小生は昔から簡易な直播きです。発芽が不安定なのであまりお奨めはしません。
ただし、7、8粒と多めに播き、しっかり灌水します。播いた後にオガクズを掛けました。
今年は種播き後の気温が高く、発芽は良好でした。
高温性の作物なので、温度が低いと発芽しません。水分不足でも発芽しにくい。ですから苗を育てるのが普通。
小生は昔から簡易な直播きです。発芽が不安定なのであまりお奨めはしません。
ただし、7、8粒と多めに播き、しっかり灌水します。播いた後にオガクズを掛けました。
今年は種播き後の気温が高く、発芽は良好でした。
発芽後も本葉数枚になるまでは弱い。その後は、一転非常に丈夫な作物です。

発芽が良かったため1株2本立てにしました。

株間も狭かったので、1本立てにすべきところかもしれません。
特別な管理はせず、専ら穫るだけ。病気や虫もほとんど付きません。
7月半ばに高さ5、60㎝になったところで、主枝の芯を摘み最初の収穫。
7月半ばに高さ5、60㎝になったところで、主枝の芯を摘み最初の収穫。
穫り跡が見えます。後はわき芽が次々に伸びてきます。

小さいわき芽も沢山出ていることが分かります。

混んできたので茎が少し細くなってきました。

穫り頃に伸びてきた茎が沢山あります。

葉を数枚付け、20㎝くらいで摘み取ります。

モロヘイヤは「野菜の王様」と言われ、エジプトの王様がモロヘイヤのスープで病が治ったという逸話で知られます。
事実、ビタミン含量は、ホウレンソウの数十倍とされます。
味に癖がないので、おひたし、天ぷら、和え物、汁物など多用途。
我が家の定番は、サッと湯がいた後、包丁で小さく刻み叩くかミキサーに掛けてとろみを出し、だし醤油で味を整えます。

真夏の暑くて食欲の落ちたときに、これをたっぷり乗せてご飯をかき込みます。
喉ごしが良く、あっという間に胃袋に直行です。
喉ごしが良く、あっという間に胃袋に直行です。