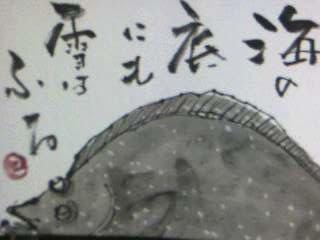七輪の余すちからに手を炙る
感覚的な話
俳句の学びの中で修練だけでは身につかないものが有る
それはお洒落の如く、何気ないポケットチーフだったり、ハンカチ
だったり、意識の外に当たり前にあるその人の感覚で俳句においては
漢字、ひらがな表記、十七音のリズム、季語の斡旋などに出ている
ように思われる。
これは教科書に載らないものだから会得しがたい
ことに季語においては、見出しの季語か傍題の季語かの選択が
俳句をゴタゴタしたものに感じさせてしまう
この話も私だけの感覚で書いているのでけして正解ではない
少なくとも自分の判断としている
例えば十七音 五 七 五 の上下五に季語が有る場合
十二音で動詞、形容詞を使った詩には見出しの季語のほうが
全体的に締まった形に思える
見出しの季語 「春暁」 傍題の季語「春の暁」
すでに傍題の季語の斡旋には作者の思いが入り込む、つまり
一句に二つの物語が存在するかのように感じてしまう
かの昔、150名ほどの句会に盲目の俳人が奥様を同伴して
来られた。 選句に入り奥様が一句一句側で読まれてその方に
聞かせていた。 音だけが選句の対象ともなることを知った
全てを備わった俳句作りは難しいけど、そんな事も今の自分には
とても勉強になっている
しもばしら (シソ科)
今日は大寒、雪をまのがれた東京です
写真は「しもばしら」という植物の茎に結氷したものです
花期は秋に虎尾草のような白い小さな花が集まって咲きます
冬の今ごろ(昨日20日赤塚植物園AM10時頃撮影)になると
枯れた茎が夜中に地中の水分を吸い上げ、朝方の冷え込みに
結氷します、例年なら植物園の開園時間には解けてこのような
姿は見られませんが昨日の寒さに見ることが出来ました
約50cmほどのものです。2月中旬まで見られるようですよ
大寒の一戸もかくれなき故郷 飯田龍太
大寒のゆるぎなき空日渡る 上村占魚