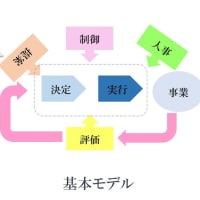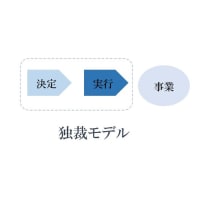人類史にあって、イスラエル・ハマス戦争は紛争の平和的解決に向けた転機となるかも知れない、と申しますと、多くの人々は首を傾げることでしょう。現実には、ガザ地区におおけるイスラエル軍の残虐行為を、嫌という程に見せつけられているのですから。悲劇的な状況下にありながら、僅かなりとも希望の光を見出すとしますと、それは、南アフリカによるイスラエルを相手取ったICJ(国際司法裁判所)への訴えなのではないでしょうか。
昨年の12月29日、南アフリカは、イスラエルのガザ地区のパレスチナ人に対する行為をジェノサイドとして批判し、ICJに対して軍事作戦の全面停止を命じるように要請しました。南アフリカは紛争当事国ではありませんので、ICJの対応が危ぶまれたのですが、同裁判所は、この問題をICJの管轄権の範囲にあるものと認めて受理しています。そして、凡そ一ヶ月後の2024年1月26日、ICJは、注目の判断を下します。ICJは、イスラエルに対ししてジェノサイド並びにその扇動行為を防止する策を採ること、並びに、ガザ地区住民に対して緊急の必要物資や人道支援を提供し得る措置をとることなどを命じたのです。
今般のICJの判断は、暫定措置命令の形で発せられており、法廷での審理を経た判決ではありません。国内の司法制度で言えば仮処分のようなものなのですが、証拠に基づく事実確認が済んでいない段階ですので、被害の拡大を最小限に抑えるための暫定措置命令であったことは頷けます。そして、この‘仮処分’は、今後、正式な訴訟が提起されれば、中立公平な立場にある機関等による証拠集めがなされ、公判の準備が整えば、正式な司法手続きのもとで判決が下され得ることを意味します(ただし、何らかの妨害がなければ・・・)。その判決が何時であれ、イスラエルは、‘裁き’を受ける立場となったのです。
もっとも、即時停戦を求める国際世論からしますと、ICJの暫定措置命令が、防止的措置や妨害の禁止等の生ぬるい措置に留まったことには、落胆の声もありました。しかしながら、イスラエルのガザ地区における軍事行動そのものが住民虐殺を伴っていますので、ジェノサイドの防止措置を実行しようとすれば、軍事行動、少なくとも住民の殺戮を停止せざるを得なくなります。この点、同暫定措置命令は、一定のイスラエルの軍事行動を抑制する効果が期待されるのです(ただし、イスラエルが誠実に同暫定措置に従えば・・・)。
かくして、南アフリカが先陣を切ったことにより、紛争当事国以外の国でも、司法的手段によって現実に起きている戦争や紛争を抑止あるいは制御し得る道が拓かれたることとなりました。つまり、国際法秩序全体に関わる問題であれば、紛争当事国以外の国でも原告適格が認められ、かつ、単独訴訟も可能となったのです。一般的には仮処分と本訴とは一連の訴訟の流れですので、仮処分の訴えが認められたのですから、本訴が受理されないはずもありません(ただし、不当な外圧あるいは内圧がかからなければ・・・)。
そして、この手法は、パレスチナ紛争自体をも司法解決に用いることができるはずです。何故ならば、イスラエルとパレスチナ国との法的な国境線は1947年11月29日に成立した国連総会決議(決議181号Ⅱ)によって引かれていますので、同決議が、司法解決を可能とする法源となるからです(1967年の国連決議やオスロ合意については、1947年の決議を基本点として和解勧告?)。もちろん、パレスチナ国は既に国連においてオブザーバーの地位を得ていますので、同国が訴訟当事国として最も相応しいことは言うまでもありません。その一方で、南アフリカと同様に、何れの国の政府も、パレスチナ問題についてICJに提訴し得るのです。
国際社会における積極的に法の支配の確立を訴えてきた日本国政府も、パレスチナ問題の法的解決をICJに対して求めることができるはずです。日本国憲法の前文には、「・・・われらは、平和を維持し。専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。・・・」という下りがありますが、真に名誉ある国家が平和に貢献する国家であるならば、日本国政府こそ、パレスチナ問題の司法解決を実現すべく、イスラエルによるパレスチナ国の領域侵犯を、国際法上の侵略の罪としてICJに提訴すべきとも言えましょう。あるいは、百歩譲って‘侵略’という表現がイスラエルを‘刺激する’として避けるならば、せめて領有権確認訴訟の形でイスラエルとパレスチナ国との国境線の確認を求めるという、より温和な方法もあります。
何れにしましても、何れかの国による勇気ある行動が、人類史において繰り返されてきた戦争の惨禍から人類を救い出すのではないかと思うのです。