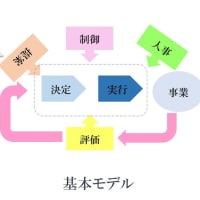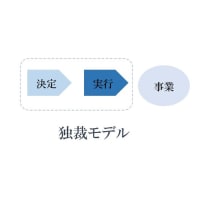グローバリズムとは、‘規模の経済’が絶対的な優位性を与えますので、規模の如何が企業間並びに国家間競争に多大なる影響を与えます。その一方で、もう一つ、グローバリズムにあって圧倒的な優位性を約束するのがテクノロジーです。テクノロジーにあって他に先んじる企業は、国境を越えて易々と自らのシェアを拡大してゆきますので、規模とテクノロジーの両者は車の両輪のような働きをするのです。このテクノロジーに注目しますと、今日のコンピュータを含む情報処理・通信産業の発展は、グローバル時代における経済植民地化に拍車をかけたとしか言いようがありません。
第一に、上述したように、テクノロジーが競争上の優位性を約束する要因ですので、これは、高度で先端的なテクノロジーを有する国や企業にしか、同産業に参入するチャンスが殆どないことを意味します。今日のIT大手の顔ぶれを見れば一目瞭然であり、その大半は、アメリカ並びに国策として同国の技術を積極的に導入し、短期間でキャッチアップに成功した中国の企業で占められています。先進国企業とされる日本企業の場合、テクノロジーのレベルでは然程の大差はないかもしれませんが、規模の要件を欠きますので、米中企業の後塵を拝せざるを得ないのです。
第二に、情報処理・通信分野、すなわちIT産業にあっては、OSの提供であれ、検索サービスであれ、SNSであれ、サービスの提供に際してユーザーとの永続的な契約関係や広範囲のプラットフォームの構築を伴います。言い換えますと、特定企業によるユーザーの‘囲い込み’を伴うのです。このため、一端、ユーザーとして組み込まれますと、不可能ではないにせよ、他社への乗り換えには手間やコストがかかります。つまり、インフラ事業の一種ともなるITサービス事業には、‘先手必勝的’な側面があり、後から同産業に参入しようとする企業は、競争上、常に不利な立場から出発しなければならないのです。このため、先に自らの製品の普及やプラットフォームの構築に成功した事業者は、長期的に収益を確保できるのです。しかも国境を越えて、他国の人々の個人情報をも飲み込みながら。
もっとも、今日では競争法があるのだから、IT大手による独占や寡占は規制されるのではないか、とする反論もありましょう。実際に日本国の公正取引委員会をはじめとする各国の競争当局は、IT大手に対する規制の強化に動いています。しかしながら、デジタル技術を基盤とするIT産業は、農業、商業、工業といった既存の産業ではなく、人類史にあって全く新しい産業分野として20世紀に登場しています。このことは、同産業では、既存の競争相手が存在しない状態で起業が行なわれたことを意味しますので、スタート時点においては凡そ独占状態が否が応でも出現してしまうのです。事業の新規性に鑑みて、アメリカの連邦最高裁判所も、同事業分野についてはIT大手に対して好意的な判決を下す傾向にあります。第三の経済支配加速化原因は、更地の上に新たな事業を広げ、ネットワークをも独自に構築できる‘自由自在さ’にあります。そしてこれも、国境を越えて広がってゆくのです。
また、企業買収を許す今日の経済システムでは、たとえ先進国であれ、途上国であれ、小規模ながらも独自技術を開発したスタートアップが設立されても、マネー・パワーによってIT大手に買い取られてしまいます。企業としての独立性を保つことは難しく、何時、大手に飲み込まれてもおかしくはないのです。
これらの要因が重なりますと、領域支配を伴わないとしても、IT大手は、あたかも‘仮想帝国’のような様相を呈することとなります。全世界の人々をユーザーとして囲い込む、あるいは、自らのプラットフォームに取り込むことで、永続的に収益を吸い上げることができるのですから。植民地時代にあって、宗主国が植民地の課税権等を掌握したのと、然して変わりはないようい思えます。しかも、サービスの内容や使用料金、あるいは、製品の価格や品質を決める決定権は、IT大手側にありますので、ユーザーは一方的に‘支配される側’となるのです。OSを例にとれば、企業側の一方的なモデル更新や仕様の変更により、過去のデータさえ読み出せなくなる事態に直面するかも知れないのですから、ユーザーの不利益は計り知れません。
かくして登場したIT大手、あるいは、グローバリスト連合が、その絶大なるマネー・パワーをもってグローバルレベルでデジタル化をさらに推し進め、人類に未来ヴィジョンを押しつけ、挙げ句の果てに、ワクチン事業等をもって‘現地住民’に対する生殺与奪の権まで握ろうとするのであれば、これは、かつての植民地時代よりも専制的で冷酷な支配となりましょう。グローバリズムについては、その負の実態から目を背けることなく、人類は、より安全な別の道を模索すべきではないかと思うのです(つづく)。