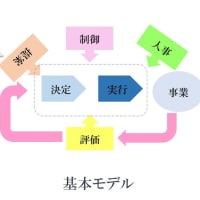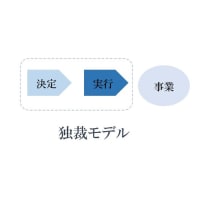ジョージ・オーウェルが没してから既に70年を超える月日を経た今日、同氏の代表作である『1984年』は、再び脚光を浴びています。ITが発展し、‘政府の嘘’が露呈してきた現代という時代が、同作品に描かれているディストピアに酷似してきたからです。オーウェル自身は同書の出版も1984年をも待たずに47歳の若さでこの世を去ったものの、国民監視装置としてのテレスクリーンの発想などは何処に由来するのか、極めて興味深いところです。
政治思想の観点から見ても、オーウェルの『1984年』は、貴重な作品であるように思えます。現代の政治理論家や政治思想家が面と向かっては書かなかった、あるいは、‘書けなかった’支配者の側の統治術が記述されているからです。今日にあっては、理論や思想を評価する場合、民主主義、自由主義、基本権の尊重といった普遍的価値を基準としますので、‘邪悪な支配’そのものを対象とした研究や考察が疎かにされてきた側面あります。本来、悪政をもたらすメカニズムといった悪を直視した研究や分析こそ悪政を回避するために必要とされるのですが・・・。こうした悪から目を背けがちな現状からしますと、『1984年』は、ディストピアの形をとりながらも深読みすれば悪の統治や体制を客観的な視点から理解し得る希有な存在なのです。
それでは、『1984年』において描き込まれている‘悪の統治術’とは、どのようなものなのでしょうか。その第一の特徴は、徹底した国民管理を実施するためのイデオロギーと装置を備えている点です。そして、思想管理の中核に置かれているのが、‘二重思考’という名の‘思考能力’の国民に対する強制です。‘二重思考’とは、「相反し合う二つの意見を同時に持ち、それが矛盾し合うのを承知しながら双方ともに信奉すること」と説明されています。同作品に登場する反体制派の思想家エマニュエル・ゴールドスタインの解説によれば、‘二重思考’を‘常に虚構を真実より前に置くことで、党は歴史の流れを阻止することができる’とされ、国民が真実を見ないようにするための思考管理術(洗脳術)なのです。
いささか難解な説明なのですが、例えば、現実は非民主的な独裁体制でありながら、独裁者自身が国民の誰もがその価値を認める民主主義を掲げることで、独裁体制を民主主義体制と信じ込ませるというような手法です。‘我が国は偉大な民主主義国家である!’と高らかに宣言する独裁者を前にして、整列した国民が‘民主主義、万歳!’と叫んで手を挙げている光景が目に浮かびます。
‘二重思考’のからくりが理解できますと、政治家が民主主義を連呼しても、どこか違和感が漂う理由も分かってきます。前回のアメリカ大統領選挙では不正選挙疑惑が持ち上がり、深刻な事態に発展しましたが、疑をかけられた側の民主党バイデン陣営が、不正疑惑そのものを民主主義の危機として訴えたとき、その言葉を素直に受け止めることができなかったのも、‘二重思考’という思考管理術が存在するからなのでしょう。日本国でも、言動からすれば全体主義や権威主義との間に親和性の高い政治家が、平然と民主主義を口にする光景が見られます。
‘二重思考’は、支配政党によって矛盾を矛盾と認識せず、虚偽を事実と信じ込むことができる‘高度な’思考能力とされています。ペダンティックに理論化されていますが、その本質は、国民を騙すところにあります。否、同訓練を繰り返せば思考能力そのものが壊され、精神が破綻してしまいます。もとより思考力の破壊を目的とした不可能な要求であるならば(大多数の国民は、政府の虚偽性に気がついている・・・)、‘二重思考’とは、決して難解な理論なのではなく、有り体に言えば、むしろ、中国の「馬鹿の故事」に近いと言えましょう。「馬鹿の故事」とは、秦帝国にちなむ逸話です。始皇帝没後、二世皇帝の治世で実権を握った宦官趙高が、皇帝に一匹の鹿が献上された際に、‘これは馬でございます’と述べたところ、生殺与奪の権を握る趙高の機嫌を損ねることを恐れた廷臣達も、鹿を馬と認めてしまったというお話です。
‘二重思考’が馬鹿の故事の現代版であるならば、今日にあって同統治術を用いている‘支配者’は、秦帝国の滅亡にこそ注目すべきかもしれません。「馬鹿の故事」は、馬鹿という言葉の語源の一つともされると共に、秦帝国の滅亡こそが主要なテーマであったからです。多くの人々が事実を事実として認めることができず、恐怖によって悪を善と言いくるめることができる体制は、程なく滅びる運命にあるのではないかと思うのです。