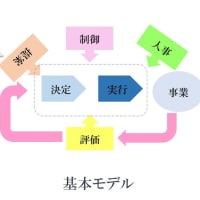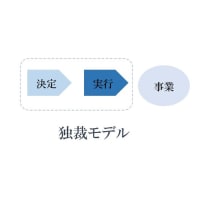ジャン・ジャック・ルソーといえば、根強い全体主義批判はあるものの、民主主義の理論化に貢献した思想家の一人に数えられています。そのルソーが、かのニコロ・マキャベリを評価していることを知ったら、多くの人々がその意外さに驚くことでしょう。マキャベリが執筆した『君主論』には、徹底した合理主義あるいは合目的主義の行き着く先の、目的のために手段を選ばない倫理なきリアルポリティークの世界が待っているからです。ところが、ルソーは、マキャベリは‘善人’であったと確信しているのです。‘君主’への指南書を装いつつ、人民に重大な警告を与えたとして。
ルソーの表と裏を反転させた見方に因れば、『君主論』は、君主のためではなく、君主達による暴政や狡猾な手段に警戒すべく、人民に予防的な知恵を与えたために書かれた書物と言うことになりしょう。そして、この‘隠された意図’という側面において、ルソーの著作も共通しています。この点に注目しますと、富者の狡猾な誘導などの他に、もう一つ、ルソーの著作には、興味深い文章を見出すことができます。それは、政治制度に関する人類の側の弱点を指摘したものです。
「だれもかれも自分の自由を確保するつもりで、自分の鉄鎖へむかって駆けつけた。何故ならば、政治制度の利益を感ずるだけの理性はもっていたけれども、その危険を見通すだけの経験を積んでいなかったからです。その弊害をもっともよく予感しえたのは、まさにそれを利用しようと思っている者たちであった。・・・」
以上の文章からしますと、ルソーは、‘自然に帰れ’という端的な標語で表されてきたように、原始時代を人類の理想郷と見なし(ただし、各自が自給自足の孤立状態にあると想定・・・)、政治制度そのものを堕落した人類の産物として完全に否定していたわけではないことが分かります(そもそも、‘社会契約’も、人類に理性が備わっていなければ成り立たない・・・)。理性を備えた人類がその有用性を認識してはいたけれども、同制度に隠されている危険性に気がつくには経験不足であったと述べているのです。そして、制度的欠陥に逸早く気がついたのが、むしろ、同制度の悪用を企てる人々であったが故に、人類は‘政治制度’の悪用者の餌食となり、奴隷的な状況に貶められていると論じたのです。
ルソーの思想には、理性の評価からして一貫性に欠けるところがあるものの(『人間不平等起源論』では否定的であり、その後に執筆された『社会契約論』では肯定的・・・)、ルソーの作品は、マキャベリの『君主論』と同じように、‘裏読み’する必要があるのかも知れません。ルソーが執筆活動を通して真に人々に伝えたかったことは、善を装った悪への警戒を怠ってはならないこと、そして、人類は悪を見抜くだけの経験を積むべきことであったようにも思えてきます。制度の悪用を見破るだけの洞察力と経験知を持たないことには、人類は、何時まで経っても悪人に悪用されうる制度から抜け出ることはできないのですから。また、ルソーは、別の箇所でこうも述べています。
「このような進歩の必然性を理解するためには、政治体が設立された動機よりも、むしろそれが実施に際して取る形態と、それが後に引き起こす様々な障害とを考察しなければならない。なぜならば、社会制度を必要とする悪徳は、社会制度の悪用を避けがたいものにした悪徳と同じものだからである。・・・」
18世紀に執筆された書物でありながら、ルソーの指摘は、現代という時代にも十分に通用するように思えます。例えば、民主的選挙制度がむしろ国民を政治から遠のけているのは、世界各地で見られる極め残念な現象です。また、日本国政府を含む各国政府とも、グローバリズムの推進機関として、国民のためと称しながら様々な制度導入を試みていますが、その多くは悪用のリスクに満ちています。メリット面は説明されても悪用の余地や制度的欠陥については、取るに足りない陰謀論として排除したり、理解不足として片付けてしまおうとするのです。そして、人々は、制度が導入された後になって、後悔することになります。
政治制度の悪用リスクについては兎角に国民の意識から外されがちですが、将来に向けて人類が必要とする有用な政治的な知識とは、案外、悪用に関するものなのかもしれません。悪用する者など存在しないとする性善説の前提こそ、悪用を狙う者達の誘導あるいは詐術的な‘プロパガンダ’であり、本当のところは、その存在を認め、悪用の手段や手法を知らなければ、改善のしようもないのです。政治制度が、全ての国民に対する統治機能の提供というその本来の存在意義を取り戻すには、グローバリストが振りまく行き先不明の‘未来ヴィジョン’に踊らされるよりも、悪用防止の制度改革という現実的な視点こそ必要なのではないかと思うのです。