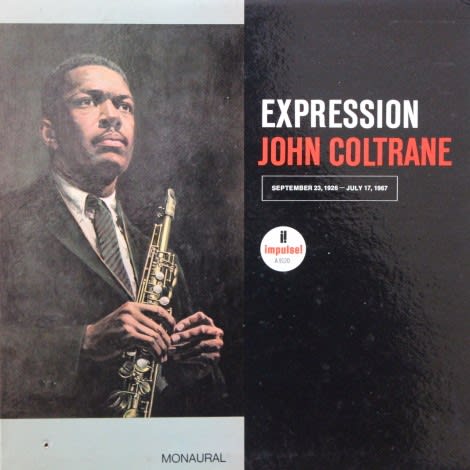Keith Jarrett / Backhand ( 米 ABC-Impulse ASD-9305 )
この時代の代表作と言われている "死と生の幻想" と同日に行われた録音で、明るい色調の楽曲がこのアルバムにまとめられた。2枚組としてリリースしても
よかったのかもしれないが、それでは重いと判断されたのかもしれない。結果的に "死と生の幻想" は名盤とされ、こちらは忘れられる存在となった。
その理由は、A面に収録されている、メロディーの無い、延々とエスニックなリズムが10分間続くような楽曲のせいだろう。聴いている側からしてみると、
「一体、これは何ですか?」と問いたくなる。規模の大きなアルバムの中で出てくるならその意味もわかるだろうが、単発のアルバムの中ではこの楽曲の
存在理由は希薄だ。
B面には出来のいい演奏が収められているので、おそらくはこれらを捨てずに残すために、止む無く1枚のアルバムとしたのではないだろうか。
A面の2曲はクオリティーに問題があるが、アルバムとしての体裁のために収録されたように思う。残念ながら、これでは残飯処理と言われても仕方がない。
このバンドのウィークポイントは、言うまでもなく、デューイ・レッドマンというサックス奏者の凡庸さだ。なぜ、彼をメンバーにしたのかよくわからないが、
ガルバレクのようにサックスがバンドを牽引するような芸当はできないので、楽曲の良さに頼らないとこの人はまったく生えない。
そういう意味で、このアルバムでの彼はまったく冴えない感じだ。こういう時こそ、サックスという楽器の力が爆発していれば別の聴き方もできたと思うが、
あまりに従属的な演奏で、才気の無さが痛々しい。
あまりこういうことは言いたくはないが、このアルバムは私には失敗作を通り越して、存在の意味がよくわからない内容だった。残念だが、嘘は書けない。