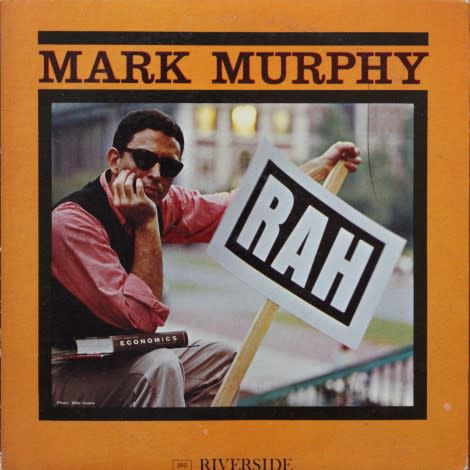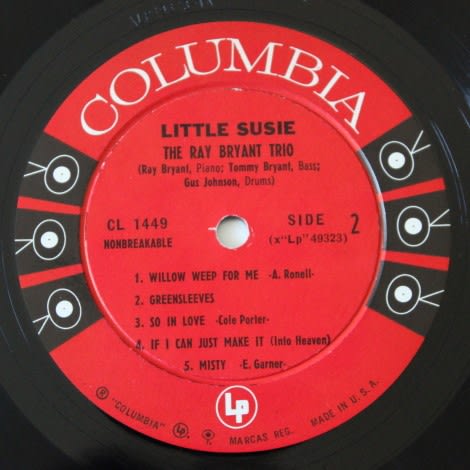Kamasi Wasington / Harmony Of Deference ( 米 YTCD171 )
楽しみにしていたカマシ・ワシントンの新作、さっそくプレミアム・フライデーの夕刻に新宿に寄って買ってきた。 前作とは打って変わって今回はミニ・アルバムで
1,000円+税である。
単純にとてもいい出来だ。 都会的な洗練さに満ちている。 たくさんの楽器を集めて分厚く雄大なサウンドを作っており、如何にもこの人ならではの音楽だ。
カマシのテナーを先頭にして、大勢のリード楽器群を従えて重厚なユニゾンでテーマをゆっくりと吹き進めていく、独特のスタイルが際立つ。
この人はイマドキにしては珍しい総合音楽を志向する音楽家である。 テナーのプレイを追求したり、音色に磨きをかけたり、フレームワークの取り扱いに
いろいろ凝ってみたり、というようなことはせず、自分の中から溢れ出して止まらない世界観をそのまま音楽として提示してくる。 そのためには弦楽器の重奏でも
荘厳な合唱隊でも、何でも抵抗なく取り入れる。 使えるものは何だって使って、自分の音楽にしていく。 そのためにそこには巨大な楽想の塊が立ち現れるのだ。
更に新世代のジャズに通底するソウル・ミュージックの流れに腰のあたりまでつかったような艶めかしくむせかえるような濃厚な質感にコーティングされたその様が、
我々には中々手が届かないような遠い世界の音楽のように響き、憧れと諦めが複雑に入り乱れた感情を湧き立たせることになる。 そういう不安げな情緒に
耐えられなければこの音楽にはついて行けないし、そういうもやもやとも上手くやっていけるのであればこの音楽の愉しさを享受できる。
不思議と懐かしい感情を呼び覚まされるようなムードが全体を覆っているのもこの人の音楽の特徴で、我々のようなおっさん世代にはかなり取っ付き易いはずだけど、
そこは一癖も二癖もあって、そういう雰囲気をエサにして独自の世界観に引きずり込んでいく暴力的なほどの力に満ち溢れている。
ミニ・アルバムなので30分程度とコンパクトな作りで、前作のような過剰さに圧し潰されるようなこともなく、一気に聴けるところも良い。
これはきっと売れるだろうな。