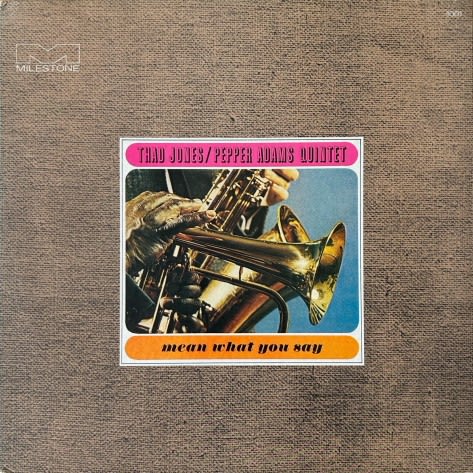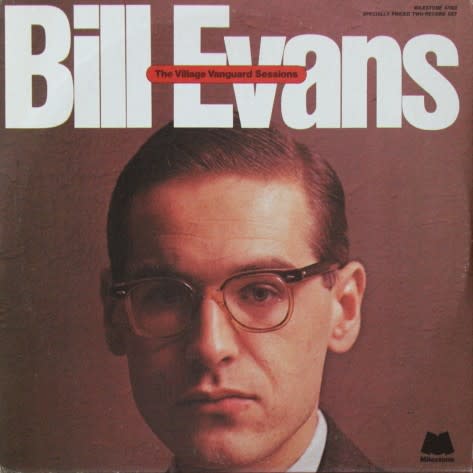Joe Henderson / Power To The People ( 米 Craft Recordings / Concord CR00655 )
Kevin Gray がリマスターして再発されるレコードの勢いがすごい。筆頭はブルーノートのシリーズだが、それだけにとどまらず、痒い所に手が届く
ようなタイトルも手掛けていてなかなか目が離せない状況となっている。本当なら片っ端から買って聴いてみたいところだが如何せん値段が高過ぎて
簡単には手が出せず、大抵は指をくわえて見ていることが多いのだが、このタイトルだけは反射的に手が出た。
数年前にジョー・ヘンダーソンのアルバムを聞き直そうといろいろ物色した時にこのアルバムはどうしても見つからず聴けず仕舞いだった。
最近海外のジョー・ヘンダーソンの値段高騰が凄まじく、右に倣えで国内の中古価格も異常な値段が付けられるようになっており、もう聴けない
かなあとあきらめかけていたところだったので、これには小躍りした。元々60年代末の作りが安っぽくなった時期のレコードだからオリジナル盤
にこだわる必要はなく、却って現代の丁寧な作りのものの方がいい。音質もケヴィン・グレイが関与しているのだから大丈夫だろうと思ったが、
これが大当たりだった。
このアルバムの肝はハービー・ハンコックのエレピで、幻想的で浮遊感溢れるサウンドが凄い。ハービーはエレピを従来のジャズピアノのような
使い方ではなく音楽の背景を描くように使っていて、こういうところがロック的な発想で音楽の建付けが根本から違っている。そういう中を
ヘンダーソンのサックスが硬質に引き締まった音色で切り裂くように鳴っており、快楽的である。全体的には叙情的な雰囲気ながらも芯は非常に
硬派なジャズが展開されていて、そのバランス感が絶妙で素晴らしい。
そういう音楽的な感動を支えるのがこのレコードから流れてくる音質。楽器1つ1つの音が丁寧に磨かれたかのように輝いていて艶やかで、
この音楽の実像がありありと浮かび上がってくる。オリジナル盤は聴いていないので比較はできないが、この音質であれば変にオリジナルなど
聴かない方がいいのではないかと思えるくらいに生々しく仕上がっていて、これは素晴らしいレコードだと確信できる。
日本が復刻する場合はいかにオリジナルに近づけるかという発想になりがちだが、それだと結局オリジナルを探せばいいじゃんということになる。
しかし、Tone Poetシリーズに代表される海外の最近の復刻は既存の音源からまったく別の良さを引き出そうとしていて、根本的に発想が違う。
そこには新しい価値が提供されており、かつてのジャズが別の魅力を携えて蘇えるという創造的な仕事をしている。それは、古いSP録音の音源に
磨きをかけてまったく新しい録音であるかのように仕立て上げたヴァン・ゲルダーのやったことに似ている。今まさにその中心をケヴィン・グレイが
担っているのだろう。彼は新しい時代のヴァン・ゲルダーになれるだろうか?