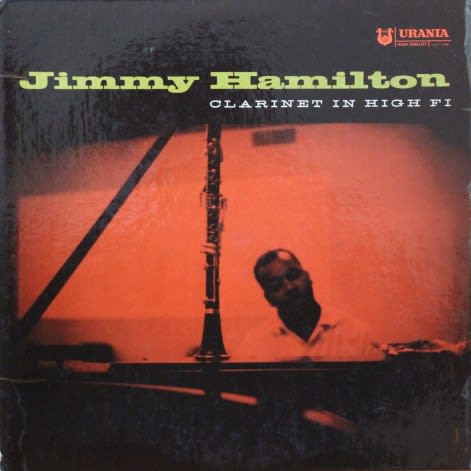Cecil Taylor / Garden ( スイス Hat Hut Records ART 1993/94 )
1981年11月、バーゼルで行われたコンサートの模様を収録した、レコードは2枚組のボックスセット。 それだけで、もう聴く前から嬉しいではないか。
まずは、歌のような、唸りのような、祈りのようなヴォーカル・ソロで幕が開く。 そして、ゆったりとピアノが始まる。 不協和音の少ない濁りの無いコードが
流れていく。 コード自体は濁っていないが、その進行(というか羅列というか)が互いの関係性を断絶した並びになっている。 それらがコマ落としで繋がれた
フィルム映像のように、連続性を失った流れる静物画のように進んで行く。 徐々にスピードがアップしていくが、打鍵は正確で、ミスタッチもない。
ピアノを触ったことがある者からすれば信じ難い神技にしか見えないが、まあいつものセシル・テイラーのピアノであり、彼の演奏としてはどちらかと言えば
落ち着いた雰囲気の第一楽章である。
続いて、内省的な雰囲気のフレーズとコードの組み合わせで第二章が始まる。 ここではコードは控えめで、両手で旋律を紡いでいく面積が大きい。
アルバムタイトルにもなっている "Garden" という言葉から連想されるある種のイメージ、例えば休暇で訪れた見知らぬ土地の宿泊客のいない寂れた古いホテルの
よく手入れされた広い中庭に1人佇み、眺めるともなくぼんやりと眺めながら物思いに沈んでいるような、そういう何かを伝えようとしてくる演奏に感じられる。
明らかに何か明確なイメージがセシル・テイラーの頭の中にはあるような、そういう雰囲気がある。 曲の終わり方も、さあ、これで終わりますよ、という
段取りを踏んでいる。 その場の思い付きの即興ではなく、予め1つの楽曲として構想されていたのはまず間違いない。
第三章は、多量の雨を含んだ重い雨雲が拡がる低い空を見ているようなムードで始まる。 空気は湿り始め、風が吹き、雨の予感がする。
低音域で旋律が唸っている中、高音域へ移ったかと思うと、雨が降り出したかのように粒立ちのいい単音の乱舞が始まる。 雨脚が強くなったかと思えば
すぐに弱くなり、更に風に流されて横殴りになる。 途中、風は弱まり小雨へと移行するが、最後はまた雨脚が強くなるなど、大きな起伏を描いていく。
調子が出てきたこの楽章は、流れるフレーズのなめらかさ、劇的なコードの響きが素晴らしい。 曲想の展開も良く、この章が一番内容が優れている。
最後は小さな断片を集めた短編集。 「Zへのイントロダクション」「ドライヴァーは語る」「ペミカン(先住民族の携帯保存食品)」「点」、どれも魅力的な
タイトルではないか。 小品には小品だけの良さがある。 エッセンスだけを抽出した一滴のアロマオイルのようなものかもしれない。
指折り数えてみればもう40年近く前の演奏になる。 この頃の演奏は何かを強く表現したがっていて、それは「表現主義の時代」だったのかもしれない。
何となくセシル・テイラーを聴くなり語るなりする場合は初期のアルバムになることが一般的には多いように思う。 そちらの方が取っ付き易いということなのかも
しれないが、実際は後年の方が音楽的には落ち着きがあり、まとまっていると思う。 怖れることなく、中期以降も広く聴かれるようになればと思う。