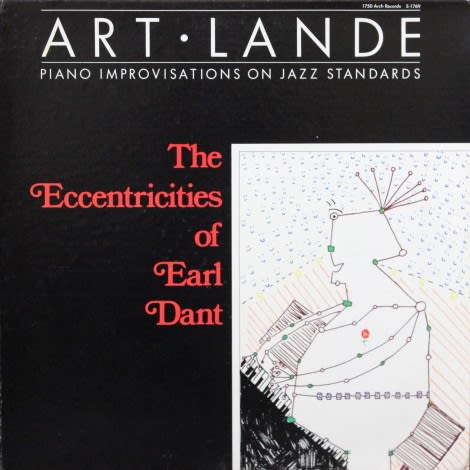Joe Henderson / Relaxin' at Camarillo ( 米 Contemporary 14006 )
チック・コリアの素晴らしいピアノが全編に渡って聴けるのが印象的だ。 コンテンポラリーの高品質な録音がチックのピアノの音を眩しく輝かせている。
こうやってテナーのワンホーンの中で聴くと、チックという人は本当に過去の巨匠たちからの影響を感じない人だ。 一体どうやってジャズピアノを
習得したんだろう、と不思議に思う。
このアルバムはゲッツの "Sweet Rain" に似ている。 窓が大きく解き放たれて部屋の空気を入れ替えたような感じがあり、そういうところが"Sweet Rain" に
似ているのだ。 その新鮮で汚れていない空気の中で、ヘンダーソンのテナーはよく鳴っている。 彼のプレイは以前のそれよりもずっと上手くなっている。
ヘンダーソンのテナーは旋律がはっきりしないところはベニー・ゴルソンと似ている。 ベニー・ゴルソンのテナーを嫌う人は多いけれど、ヘンダーソンは
唯一ゴルソンの系譜を継いでいる人だ。 ヘンダーソンのテナーは褒められて、ゴルソンのテナーは褒められないというのは私にはよくわからない。
ゴルソンは作曲家のイメージが強く、ヘンダーソンのように演奏家として見られることは少ないからなのかもしれない。
また、ドラムスにトニー・ウィリアムスとピーター・アースキンが参加していて、これが演奏全体を強力にグルーヴさせている。 トニーはいつものように
煽情的なシンバルワークで全体を煽るし、アースキンはスティーヴ・ガッドとよく似たドラムの叩き方をしていて、これがなかなか板についている。
このアルバムは1979年のロス・アンジェルス録音だが、ちょうどこの70年代はアメリカでも過去のバップ系は1度きれいに清算されて、新しい雰囲気を持った
ジャズが始まった時期。 それは世界を席巻したロックの影響も大きいし、60年代のフリージャズがバップを焼け野原にした後の必然でもあっただろうけど、
このアルバムはそうやって自浄的な新陳代謝として最初の新しい現代ジャズが始まっていた時期に作られた作品で、その当時の新鮮さを愛でることができる
絶好の内容だと思う。 演奏力の尋常ではないレベルの高さ、クリアな音場を提供する好録音、どれをとっても文句なく愉しめる。