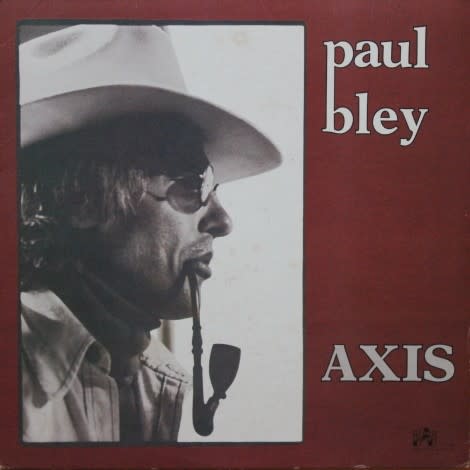The Modern Jazz Quartet / Plays The Music From Porgy And Bess ( 蘭 Philips 840 234 BY )
どのアーティストがどんなスタイルでやっても素晴らしい音楽になるのは、やはり原曲が素晴らしいからに他ならない。 決定的名盤はたくさんあるけれど、
このMJQのアルバムも他とは一線を画す。 様式美と自由なアドリブラインの混ざり合い加減はもはや神業と言いたくなる。 必要最小限の音数で静かに
進んで行くこの音楽には究極の洗練がある。 ジャズという音楽にこういうアプローチで臨むこのグループの姿勢には逆説的なアブストラクトさが充満しているけど、
それが嫌味なく徹底されていて高次元に音楽として結実しているというのは驚き以外の何物でもない。
ゆったりと静かで優雅にスイングする。 まるで、眠っている赤ん坊を起こさないように静かに揺り籠を揺らすように。 原曲のメロディーを大事にしながら
ジョン・ルイスの音楽の統制とミルト・ジャクソンのひんやりと冷たいシリンダーの音色が音楽全体を支配する。 パーシー・ヒースとコニー・ケイのデリケートな
リズムが背景に映し出された影絵のようにゆったりと動いている。 ガーシュインのメロデイーがゆっくりと流れて行く。
MJQのアルバムは結構出来不出来があって何でもかんでも素晴らしいと言うわけにはいかないけれど、これは無条件に素晴らしい。 楽曲の良さを上手く
描いていて、このグループにしかできない新しいポーギーとベスの世界を作っている。 オリジナルのアトランティック盤は未聴だけど、このフィリップス盤は
音質も良好で、雑念に気を取られることなく音楽の世界観に集中できる。