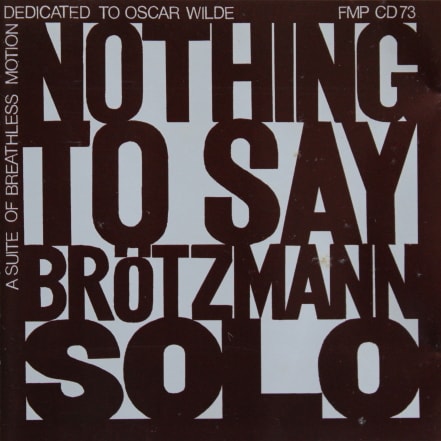Herb Geller / Fire In The West ( 米 Jubilee JLP 1044 )
苦手な西海岸モノだが、ハーブ・ゲラーはあまりちゃんと聴いたことがなかったし、安値で転がっていたのでダメもとで聴いてみることに。
ケニー・ドーハム、ハロルド・ランドを加えたセクステットで、ルー・レヴィー、レイ・ブラウン、ローレンス・マラブルという珍しい顔合わせになっている。
予想通り、アレンジが施された軽快でコンパクトな演奏だが、アレンジ自体はさほどガチガチではなく、各人のアドリブパートではそれぞれがしっかりと
演奏しているので、思ったよりも聴き応えがあった。 ベニー・カーターがアイドルだったというだけあって、ハーブ・ゲラーのアルトは太い音でなめらかに
流れていく。 直感や閃きに頼るタイプではなく、ある程度のシナリオを前提にしたようなフレーズになっている。
自身のリーダー作なんだからもっと前に出てしっかりと吹けばいいのに、そうはなっていない。 とにかく、ハロルド・ランドの硬質で重心の低いテナーと
ルー・レヴィーの見事なソロばかりが印象に強く残る。 これじゃ一体誰がリーダーなのかよくわからない。 まあ、こうやってソロを出すまでにいろんな
ビッグバンドで仕事をしてきた人なので、公平にソロを取れるアレンジをするのが本人には当たり前だったのかもしれない。
このアルバムを作るにあたり、当初はドラムはフランク・バトラーがやる予定だった。 ところがリハーサルをやる約束の時間になってもバトラーは現れない。
せっかく招いたドーハムの手前もあり、急遽マラブルをスタジオに呼んでリハーサルを行い、本番もバトラーはクビにしてマラブルでやることになった。
それを知ったバトラーは怒り、レコーディングの2か月後のある日、ゲラーが自宅に帰ると窓ガラスがこじ開けられてTVやシャツや現金が無くなっていた。
ちょうどその頃マイルスのバンドがLAに来ていて、フィリー・ジョーがゲラーの家にやって来て「フランク・バトラーがお前ん家のTVを持ってるぞ」と
教えてくれた。 そして、しばらくしてバトラーは窃盗の常習者として逮捕・投獄された。 このアルバムにはそういう裏話がある。
ジュビリーは東海岸のレーベルだから、このレコードも西海岸特有の乾いたサウンドではなく、東海岸のレーベルらしい腰回りの太い音がする。
そのせいもあって、音楽の建付けは西海岸のジャズなのにも関わらず、聴いていてそういう感じがあまりしないミスマッチ感がちょっと面白い。
レーベルカラーというのは不思議なものだ、と思いつつも、そういうものを凌駕するほどの個性や力はなかったんだなと切ない気持ちにもさせられる。
愛妻ロレイン・ゲラーが30歳の若さで肺水腫で亡くなり、すっかり気落ちした彼はスタン・ゲッツの助言などもあり、渡欧してドイツに移住してNDRオケなど
地元のビッグバンドに席を得て、アメリカには戻らなかった。 渡欧する直前、バードランドでブッカー・リトル、スコット・ラ・ファロらと演奏する話があったが、
落ち込んでいたこともあってそれを蹴ってしまった、あの時東海岸に行って彼らとバードランドに出ていれば自分はジャズの世界でもっと有名になっていたかも
しれない、と晩年に語っているけど、このアルバムを聴いた限りでは「さあ、それはどうかなあ?」というのが正直なところかもしれない。