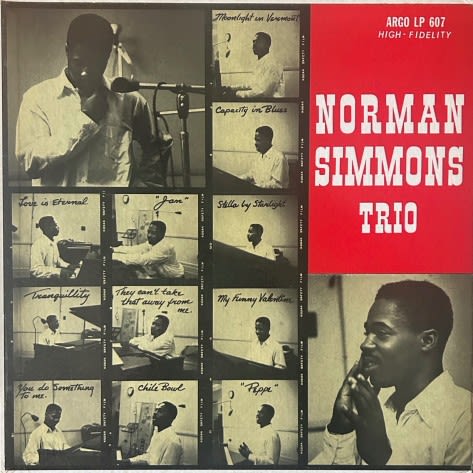Jazz University's New Kicks / Morris Grants Presents J.U.N.K ( 米 Argo Records LP 4006 )
大の大人たちが大真面目におふざけしたレコードだが、失笑して聴きながらも色々と考えさせられるところがある。ジャケットには明記されていないが、演奏しているのは
Jordan Ramin (sax)、Doc Severinsen (tp)、Bernie Leighton (p)、Triggar Alpart (b)、Don Lamond (ds) たちで、ブルーベック・カルテット、マイルス・デイヴィス・グループ
(キャノンボール・アダレイ、ジョン・コルトレーン)、エロール・ガーナー、オーネット・コールマン(ドン・チェリー、チャーリー・ヘイデン)、ズート・シムス、ジェリー・マリガン、
チェット・ベイカー、ジーン・クルーパー、メイナード・ファーガソン、セロニアス・モンクらの物真似をしていくというキテレツさで、J.A.T.P. のパロディー形式でコンサート
MCが曲を紹介し、観客の大歓声がオーバーダブされている。
どの演奏も実によくその特徴を捉えており、そっくりと言ってもいい演奏が次から次へと現れてくるのは圧巻だ。たださすがにボロが出るからか長尺の演奏はなく、どの演奏も
断片的というか短いワン・ショットで、それらをリレー形式で繋いでいく。そういうところもJ.A.T.P.っぽい。デスモンドとブルーベック、マイルス、マリガン、オーネット、
モンクは本人かと思うほどよく似ていて、キャノンボールやコルトレーンはちと苦しいかという感じだが、そこはご愛敬。オーネットのグループの演奏が始まるとブーイング、
終わった後は数人がパラパラと拍手するだけだったり。徹頭徹尾、ジョークが行き届いている。とにかく聴いていてニヤニヤが止まらない。面白いなあ、笑ってしまう。
本人たちは "ジャンク" と言い切っているが、果たしてそうだろうか。これを聴いて思うのは、偉大なスタイリストたちの演奏の特徴は誰でも真似ができる、つまりその人しか
演奏できないような特殊なものではなかった、ということだ。にもかかわらず彼らが偉大だったのは、それを自らの手で誰もが素晴らしいと感じられるような普遍的な形で
生み出すことができた、ということだろう。物真似はその対象への愛がなければ出来ないとはよく言われることだが、正にここにはその理想形があるのだ。ここまで徹底した
形で創り出されるパノラマには大きな情熱が込められているし、嫌みや妬みのような感情は一切なく、純粋な愛情しか感じられない。そこが素晴らしいと思うのだ。
聴いていてこんなにも愉しく幸せな気分になれるレコードが他にあるだろうか。こんなものを作ってしまうアーゴというのは不思議なレーベルである。