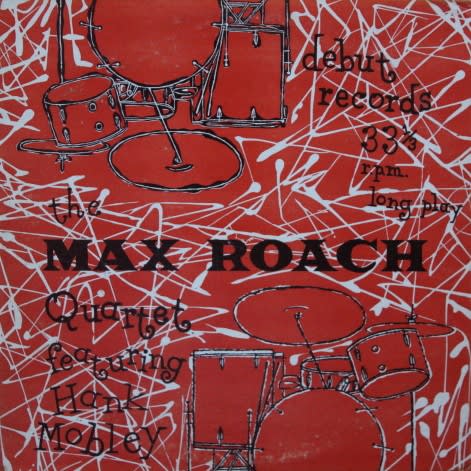Ada Moore / Jazz Workshop Vol.Ⅲ ( 米 Debut DLP-15 )
1991年1月、エイダ・ムーアが癌により64歳で亡くなった際にニューヨーク・タイムズ紙が伝えたところによると、レコード制作には
恵まれなかった彼女も、コンスタントにシンガーとしてずっと活動していたらしい。距離も時間も遠く離れた我々にはそれがどういう
ものだったのかはわからないけれど、歌手として活動していたという話を知ることができるのは嬉しい限りだ。
彼女はこのレコードと、コロンビアにバック・クレイトン、ジミー・ラッシングと共に吹き込んだものしかレコードが残っていない。
その理由はよくわからないけれど、これはあまりに不当な扱いだったのではないか。
ニーナ・シモンとカーメン・マクレーをブレンドしたような声質がビリー・ホリデイのようなフィーリングでぶっきらぼうに歌う様には
圧倒される。1度聴くと、その印象は耳に刻み込まれて忘れることはない。ミンガスが作ったこのレーベルでは唯一のヴォーカル作品で、
ミンガスの鑑識眼の素晴らしさが光る。
このアルバムの素晴らしさは彼女の歌だけに留まらず、バックの演奏の凄さにもある。ジョン・ラ・ポータのアルトの鳴りが素晴らしく、
バックの演奏が歌伴ではなくインスト・ジャズとして通用する演奏で、ヴォーカルと真っ向から対峙している。このアルバムを聴いて
いると、サラ・ヴォーンがパーカーをバックに歌った音源を思い出す。雰囲気がそっくりだ。
音質もビックリするほど良くて、何の手も加えずそのままカッティングしたような生々しく高い音圧が凄まじい。
スピーカーから出てくる音に風圧を感じる。
ヴォーカルも楽器群の演奏も濃厚なジャズのフィーリングに満ち溢れていて、何も手を加えないざらっとした手触りが圧巻。
これこそが、まさに "ジャズ" なのだ。