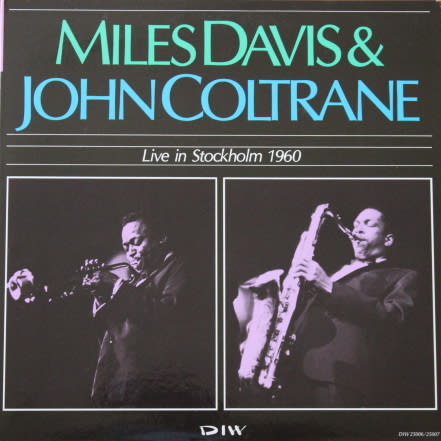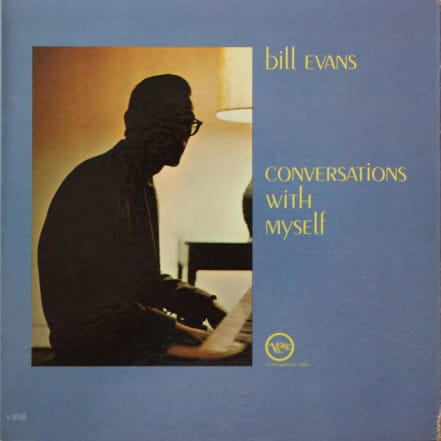Michael Mantler / The Jazz Composer's Orchestra ( 西独 JCOA LP1001/2 )
1968年に制作されたこの作品は、その当時の心あるジャズミュージシャン達の英知のすべてが結集して出来上がった1つの究極の成果となっている。
統制と解放、安定と不安、秩序と混乱、集合と離散、そういうありとあらゆる矛盾と背反のすべてを目の前で次々に片っ端から飲み込んでいく。
オーケストラは知的に譜面上に定義され制御されているにもかかわらず熱狂的で、ソリストとして指定された者たちは用意された限られた小節の中で
すべてを吐き出す。
この作品を聴けば、セシル・テイラーというピアニストの本当の恐ろしさがわかるだろう。 2枚組のアルバムの2枚目の両面がテイラーの受け持つパートだが、
如何にラリー・コリエルが素晴らしい演奏をしていても、1枚目の演奏群はこの2枚目の単なる序曲に過ぎない。 セシル・テイラーの音楽が破壊と脱構の
音楽ではなく、創造と再構築の音楽であることがここまでわかりやすく理解できるケースはちょっと珍しいのではないだろうか。
セシル・テイラー / アンドリュー・シリルの演奏があまりに凄すぎて、オーケストラが演奏を止めて、全員が食い入るようにその様子を見つめている様が
何とも生々しい。 テイラーのピアノそのものはいつもの様子と大きくは変わらないが、マントラーのコンセプトを的確に把握した上での音楽展開をして
いるので、楽曲としての仕上がりの良さはテイラー自己名義の作品群を遥かに上回る。
マントラーの頭の中には当然コルトレーンの "アセンション" やシュリッペンバッハの"グロ-ブ・ユニティー" のことがあっただろうが、幸いなことに
そういう先行事例とはまったく色合いの異なる至高の作品に仕上げることができた。 おそらくそれらを十分に聴き込んで、そこに足りなかったものを
きっちりと対策して臨んだ結果が功を奏したのだろう。
長年CD→iPodという形で音量Maxの爆音で聴いてきたが、これはオリジナルのレコードでも持つ価値があると思い直して西独盤を探して買い求めた。
見開きカヴァーを開くと多数の写真や譜面、解説などが閉じられた手の込んだ作りになっており、気合いの入り方の違いがよくわかる。
真の傑作、という言葉で締め括るしかない。