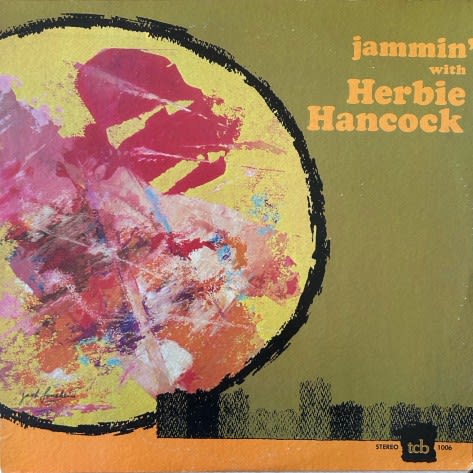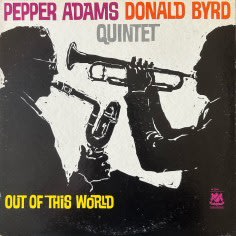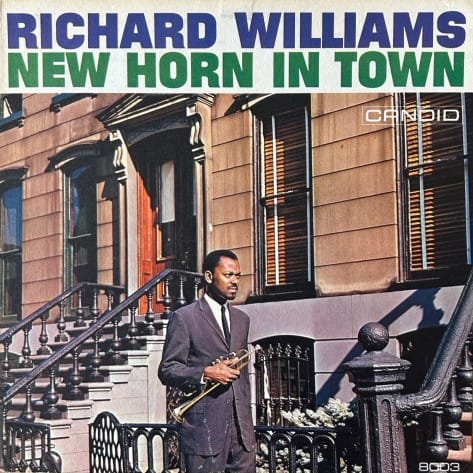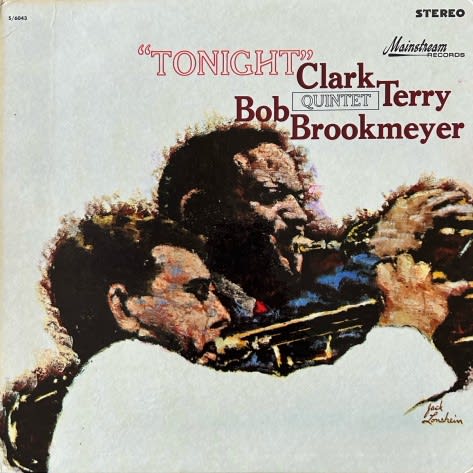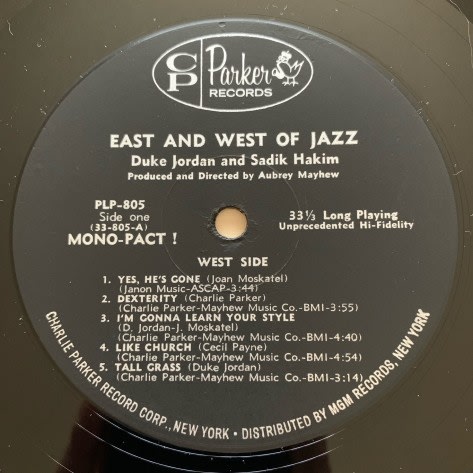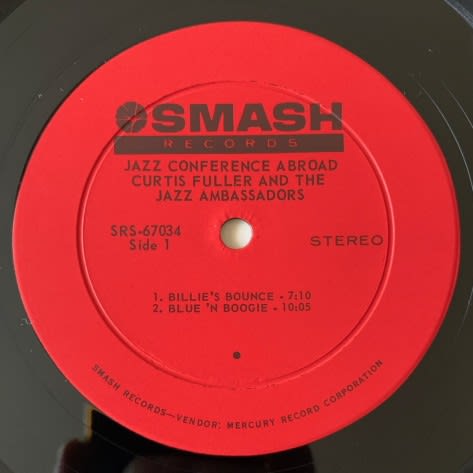The Hank Babgy Soultet / Opus One ( 米 Protone Hi-Fi Records And Recorded Rapes HBS-133 )
ユニオンのセールに出ているのを見て、そう言えばもう何年も聴いていないなあと思い出して久しぶりに棚から取り出してきたレコード。買った当時はよく聴いていたが、
この手のレコードは飽きるとまったく聴かなくなってしまう。おそらく10年振りくらいに聴き返してみると、やはり感銘を受ける内容であることを確認できた。
リーダーの名前も知らなければ他のメンバーもまったく知らない、おそらくはローカル・ミュージシャンの集団で、レーベルも他にジャズのレコードを出してはいないらしく、
とにかく謎だらけのレコードでこういうのは非常に珍しい。にも関わらず、モノラルとステレオの両方をリリースしているらしく、64年という時期を考えれば当然なのだが、
それにしてもその入念な販売状況からもしかしたらこの演奏を残すためにわざわざ立ち上げられたのか?と勘ぐってしまうほどだ。とにかく音が凄くいい。
そういう謎だらけにもかかわらず、欧州ジャズのような楽曲の雰囲気や演奏レベルの異様なまでの高さから一体これは何なのだ?と聴いていいて訳が分からなくなる。
それでも楽曲の出来は当時の欧州ジャズなんかよりも遥かに上回っていて凄いとしかいいようがないし、演奏も誰か名うての名人が覆面で演奏してるのかと思うような
レベルだが、ジャケットの裏面を見ると彼らの写真が載っていてそういうことでもないらしい。
そういう何が何だかさっぱりわからないところが常に居心地の悪さを誘発するが、それでも呆気にとられながらもあっという間に全編を聴かされてしまう。このレコードが
日本で「発見」されたときはそのモーダルでメロウな雰囲気が大ウケしたようだが、大事なのは最後まで一気に聴かせるその勢いだろう。当時のジャズの主流からは外れた
ところでこういう音楽が演奏されていたという事実が驚異的だし、こういう音楽が発売当時に評価されなかったのは当時のジャズ・ジャーナリズムの荒廃ぶりを物語っている。
無名のローカル・ミュージシャンたちが作ったレコードといえばアーゴのレコード群を思い出すけれど、それらとはまったく違う質感の演奏で、アメリカのジャズの層の厚さを
思い知らされることになる。そういうレコードだから稀少盤になってしまうのも無理もないが、ただこれは弾数が少なくて珍しいだけの中身のない稀少盤ではない。
手元にあるのはモノラルプレスなので、これがステレオプレスで再発されたらおそらくは買ってしまうだろうと思う。